
|
■■ 北海道教職員組合【北教組】へようこそ
|
||
 |
 |
 |
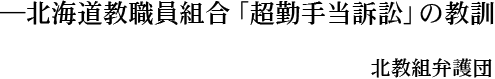
弁護士 江本秀春
同 後藤 徹
同 佐藤義雄
同 横路民雄
同 川村俊紀
同 伊藤誠一
同 新川生馬
中教審の特別部会で審議されている「教員の働き方改革」については、教員の生命・心身の健康を守ることを中心に労働者の人権問題として、長時間労働の解消に向けた実質的な議論がされるべきです。そのためには、教員の業務が正規の勤務時間内で終わることが可能な定員増加、担当する授業時数の削減、部活動の負担解消などの抜本的な対策が必要不可欠であり、単なる業務の効率的な運用改善や組織体制整備等では不十分です。また、教員の超勤(時間外・休日勤務)の抑制に実効性がある法制度の整備、すなわち、給特法の見直しも行われなければなりません。それなくしては子どもの教育を受ける権利の保障もないのです。
教員の長時間勤務が益々深刻化している大きな要因は、給特法の給与月額4%の教職調整額を支給するのみで、それ以外の超勤手当を支給しないことにあります。この給特法のしくみを改善しない限り、教員の長時間勤務は、その解消は覚束ないばかりか、今後も益々肥大化することになります。北教組の「超勤手当訴訟」がそのことを物語っています。
