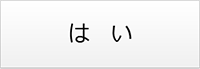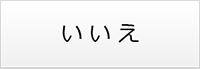私たちの自主編成
1. 平和と民主的教育を守るために
敗戦後の混迷の中、戦前の教育への深刻な反省と批判の下、北海道の教職員は新たに団結し、教育労働者として主体性を持って、北海道の教育を再生させようと1946年に北教組を結成しました。
一方、1947年、戦後の日本は平和憲法といわれる「日本国憲法」にもとづき、「教育基本法」(以下、
「47教育基本法」(※1)を制定しました。
1950年、朝鮮戦争が勃発しました。北教組は1951年、戦前回帰の国家主義教育の復活の動きに対し、「教え子を再び戦場に送るな」のスローガンを採択するとともに、自主的組織的教育研究を推進することを目的に、第1回北海道教育研究討議会を開催しました。
以降、私たちは、この「47教育基本法」の理念にもとづき、「子どもたちの学ぶ権利を保障し、学校・教育における民主主義を確立することを目的に行う自主的な教育研究」として、「自主編成運動」にとりくんでいます。
2. 自主編成運動とは
私たちがすすめる「自主編成運動」の大きな特徴は、「地域や学校の実態、子どもたちの成長段階やその特性を考慮して、各学校の裁量で教育課程を編成する」ところにあります。
このことは「学習指導要領」の「総則」にも記載されており、「学習指導要領」はあくまで「基準」としてとらえ、目の前の子どもたちにとって最もふさわしい「教育課程」を私たち現場の教職員の手で編成していくことが、「自主編成運動」の最大の目標なのです。
3. 捻じ曲げられた教育基本法
ところが2006年の「教育基本法」をはじめ教育関連3法が改悪 (※2)されてしまいました。その大きな目的は、「戦後、学校現場へ任せたはずの教育を国のもとに取り返し、国家に従順な国民をつくるため」であることは明らかです。すでに、全国学力・学習状況調査(全国学テ)によって競争をあおり、道徳によって愛国心を植えつけ、子どもたちの心の中まで介入するとともに、小学校英語やキャリア教育など国や一部企業が求める人づくりが押しすすめられています。
4. 今こそ自主編成運動の推進を
このような危機的な状況だからこそ、私たちは改悪された教育基本法と対峙し、「47教育基本法」の理念を生かした人権と民主主義を根づかせる教育課程を編成していくこと、子ども・地域のための教育を守ること、つまり「自主編成運動」を強化していくことが重要であると考えています。
あなたも、北教組「自主編成運動」にふれ、目の前の子どもたちにふさわしい「真の教育課程づくり」にとりくみませんか。
5. 自主編成運動を考え方
北教組は、1974年から、「ゆとりと、すべての子どものわかる授業を保障する学校5日制」の実現、「差別・選別の学校から共生・連帯の学校へ」の転換をめざしてとりくみをすすめてきました。
その理念の支柱となったのが、数学者・遠山啓(1909~1979)の教育論です。彼は、一人ひとり違う個性をもつ子どもを伸ばしていく教育をすすめる上で、学校教育に浸透している競争原理は妨げになると考えました。「競争心を刺激する教育法は、たしかに手っ取り早く人間をふるい立たせる力を持っている。しかし、その反面、目標を他人におくために自分自身を見失うという欠陥をもっている。『競争原理を超えて(1976)』」
そこでは、学びには「術(知識・できる)・学(理解・わかる)・観(思いめぐらす)」の視点があると仮定し、『分析(人類が歴史的に積み上げてきた文化(各教科)の学習)』では「術・学」を、『総合(各教科で身につけた知識を組み合わせた学習)』では「観」を形成していくことを主張しています。(図参照)
さらに、「観」を形成する『総合』の学習においては、子どもの自主的な判断を促すことで「道徳」を育むことができるとしており、現在の文科省「特別の教科 道徳」とは180度異なる方向性を示しています。
これらの教育理念は、40年を超えてもなお色褪せることなく、競争原理をテコとせずに本来の学びを授業をとおして実現しようとする理想であると私たちは考えています。
6. 自主編成運動の基本的観点
○憲法、47教育基本法の精神に沿ったものであること
○子どもの発達を保障するものであること
○科学的、系統的で精選されたものであること
○組織的・集団的なものであること
○職場闘争と一体的にすすめなければならないこと
○保護者、地域と結びつきを強めてすすめること