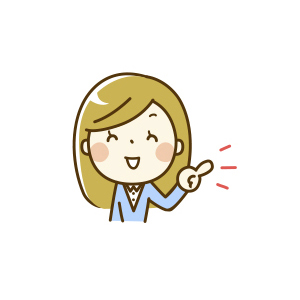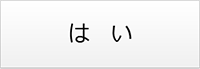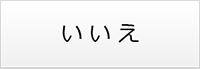「星野君の二塁打」の大まかな内容
逆転チャンスで星野君に打席が回ってきた。
サインは「送りバント」だったが、得意なコースにボールが来たので打ったら、二塁打となりチームは勝った。
しかし試合後、監督に「サインに従うという約束を守らなかった」として、次の試合は出場停止にさせられた。
学校図書の6年生の教科書には、題材名とともに「よりよい学校生活、集団生活の充実」という「内容項目」(徳目)と、「チームの一員として」というサブタイトルが記されています。さらに文中には、「チームの輪を乱した」「ぎせいの精神が分からない人間は、社会に出たって、社会をよくすることなんて、とてもできないんだよ」などと監督が星野君を叱責する言葉があります。
「悪質タックル」問題の後にこの「星野君の二塁打」を読むと、「この話が正義だと子どもたちに刷り込んでいいの?」という疑問が生じます。この教材の指導書どおりに授業を行い、「決まりを守り義務を果たすことの大切さ」について子どもたちに考えさせ、「監督に言われたことを守ることが正しい」との結論に帰着するべく議論を展開させるのだとしたら、子どもたちに対し、規則やルールへの盲従を強いるだけでなく、時には集団のために自己犠牲を払うことを「善」として刷り込んでしまいます。
ですから、「星野君の二塁打」を扱う際には、「悪質タックル」問題も現実の題材として扱うことが大切になります。また、災害時などに思考停止して誰かの指示を待つことのリスクなども合わせて検討し、多様な意見を出し合いながら、「考え、議論する」時間にしていかなければなりません。
文科省は「教科化」に際し、「考え、議論する道徳」を掲げ、「特定の価値観を押し付けたり、主体性をもたず言われるままに行動するよう指導したりすることは、道徳教育が目指す方向の対極にある」として、「教科化」をごり押ししました。しかし、文科省が検定した教科書には、「星野君の二塁打」のような「道徳教育」の目的と対極にあるものや、特定の「価値」へと誘導する設問が多くあります。特に、「権利と義務」を扱う教材を見ると、「一方的な価値観の押し付けになる」という「教科化」に対する懸念が、より現実のものになっています。その手法は、「集団生活等において他者に迷惑をかけない」というルールを「権利行使」と対立するものと設定し、集団生活を円滑に行うために権利行使を控えるように誘導するものとなっています。いわば、権利行使を「わがまま」と同視し、集団のために我慢することが「義務」であるかのように教える内容となっているのです。
私たち教職員組合は、「道徳教育」を否定しているのではありません。子どもたちが、学びや生活をとおして様々な価値と出会い、自分にとり入れていくこと。そして、様々な状況に合わせて行使すべき価値を選び出し行動していく。さらに、試行錯誤しながら自らの道徳性を確立していく、その道程こそが「道徳教育」であり、「人格の完成」そのものだと考えます。
先行実施された「特別の教科 道徳」は、子どもたちに新自由主義を是とする社会での適応を学ばせるものであり、その社会のあり方自体は疑わせないように構成されています。しかし、本来「道徳」とは、自らの生き方を問うとともに、社会のあり方にも向けられるべきものです。また、何を「善」とするか、いかなる生き方を「よい生き方」とするかは、一人ひとり異なるもので、方向づけられるものではありません。憲法及び「子どもの権利条約」は、一人ひとりの価値観や生き方が異なることを当然の前提として、自らの判断で選び取るものとし、そこに国家が介入することを禁じています。よって、学校は、まだ自分の個性を十分発揮できない子どもに、特定の価値や命令を押しつけるのではなく、子どもの気持ちに寄り添い配慮していくことが必要になります。
「大切なものは目には見えない」サン・テグジュベリの「星の王子様」の一節です。教育は、子どもたちとともに、「目には見えない大切なもの」を探す営みです。そして、私たち教職員はその営みの中で、子どもの心の中にある「目には見えない大切なもの」を見つけ、私たちの心の中へも取り込んでいきます。教職員の日々は、子どもたちのことで頭も心もいっぱいになります。そんな生き方がすばらしいと思えるから、ブラックな労働環境に声を上げつつも、子どもとともに学校で学び続けています。
「道徳の教科化」に対しては、歴史的な事実と子どもたちの権利を守る視点から、授業の工夫が必要だと考えます。しかし最も大切なことは、教職員が、子どもの人格形成の場としての学校のあり方を問い直し、目の前の子どもにとって何が最善かをともに考えながら日々の実践を充実させていくことです。