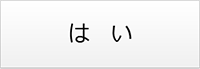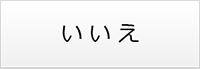2024年度 道教委「全国学力・学習状況調査
北海道版結果報告書」に対する北教組声明
2024年11月7日
2024年度 道教委「全国学力・学習状況調査 北海道版結果報告書」に対する北教組声明
道教委は11月6日、2024年度「全国学力・学習状況調査北海道版結果報告書」を公表した。その中で、「平均正答率が全国平均に達していないものの、中学校の国語は全国平均とほぼ同水準で、小学校の国語及び中学校の数学は全国平均との差が縮まるといった改善傾向が見られ成果が現れている」「一方で、小学校の算数では全国平均との差が広がっている(差2.8)」とした。なお、昨年度の報告書では「小学校の算数(差1.5)及び中学校の数学と英語の3教科で縮まり、07年度の調査開始以来初めて、全ての教科で2.0ポイント以内となるなど改善の傾向」としていた。改めて、毎年調査対象の子どもが異なる中で数ポイントの差があることに対して「評価・分析」し、恣意的に「ICTの効果的な活用、家庭学習の定着が必要」と結論づけること自体に、何ら意味がないと言わざるを得ない。
文科省は調査の目的を「義務教育の機会均等とその水準の維持向上の観点から、全国的な児童生徒の学力や学習状況を把握・分析し、教育施策の成果と課題を検証し、その改善を図るとともに、学校における 児童生徒への学習指導の充実や学習状況の改善等に役立てる」としているが、先述したように全く教育施策の成果と課題の検証になっていないのが実態である。
学校では「得点をとること」が目的となり競争を煽られ、1年を通じて対策としてのチャレンジテストを強制されるだけでなく、「学力調査」の結果がともなわないと「加配教員が減らされる」と発言する管理職すら存在する。北教組の調査では、「学力調査終了後、子どもは疲れ果て、寝てしまったり集中力が極端に減ったり授業にならない」「過度なプレッシャーを理由に欠席や不適応行動をとる子どもがいる」など、子どもが精神的に追い詰められている様子が寄せられている。
本来、教育行政の責務は、子どもが安心して通える居場所としての学校づくりのための人的・物的両面での環境整備を行うことである。しかし、この数年、教員の欠員に対する不補充は悪化するばかりで一向に改善の兆しすら見えない。また、文科省23年度調査では全国小、中学校で不登校の児童生徒数が34万6482人となり過去最多を更新し、増加は11年連続、30万人を超えたのは調査開始から初めてとなった。また小、中、高校などのいじめの認知件数が73万2568件、いじめの重大事態1306件、暴力行為の発生件数は10万8987件といずれも過去最多となっている。これらは子どもたちの苦悩の現れである。文科省・道教委は、国連子どもの権利委員会の日本に対する「あまりにも競争的な制度を含むストレスフルな学校環境から子どもを解放すること」とした勧告を真摯に受け止め、競争的・管理的な学校から子どもたちを解放すべきである。そのため「学力調査」ではなく、不登校やいじめ認知件数増加の要因分析として07年の「学力調査」開始以降の教育政策・施策の検証こそが教育行政のまず行うべきことであることを指摘しておく
北教組は、教職員の自発性・創造性を尊重し、子どもたちが「わかるよろこび」を感じることができる学校をめざす観点から、「報告書」「結果公表」に断固抗議するとともに「全国学力・学習状況調査」に反対し、子どもたちの「学び」を矮小化する「点数学力」偏重の「教育施策」の撤回を強く求める。
私たちはこれまでと同様、今後も、憲法・「47教育基本法」・「子どもの権利条約」の理念にもとづく「ゆたかな教育」の実現のため、子どもの主体性・創造性を尊重し、意見表明権を保障した教育実践を積み重ね、市民とともに教育を子どもたちのもとへとりもどすための広範な道民運動をすすめていくことを表明する。
2024年11月7日
北海道教職員組合
道教委2025年度「公立高等学校配置計画」および「公立特別支援学校配置計画」に対する北教組声明
2024年9月6日
道教委2025年度「公立高等学校配置計画」および
「公立特別支援学校配置計画」に対する北教組声明
道教委は9月3日、25年度から3年間の「公立高等学校配置計画」(以下、「配置計画」)と25年度および26年度以降の見通しを示した「公立特別支援学校配置計画」を公表した。
「配置計画」では、6月の「配置計画案」で示した通り、①南茅部を27年度に募集停止、②市立札幌藻岩と啓北商業を再編統合、③北見商業、釧路江南を1学級減、④入学者数が2年連続20人未満となった苫前商業を再編整備留保、とした。また、24年度入学者選抜の結果、第2次募集後の入学者に1学級相当以上の欠員が生じ学級減とした16校のうち、芦別、深川西、倶知安、静内、士別翔雲、留萌、湧別、清水、別海、中標津の10校は1学級増に戻したのに加え、広尾は町内中卒者数の状況などから1学級増としたものの、札幌西陵、札幌あすかぜ、伊達開来、池田は1学級減のままとした。24年度「配置計画」では、広尾を1学級減、池田を1学級増としたが、25年度「配置計画」では広尾を1学級増、池田を1学級減としており、地域や学校、子どもや保護者は、学級増減に毎年翻弄されることとなる。
24年度留辺蘂、25年度穂別、26年度奈井江商業に続き、今回、27年度の南茅部の募集停止が示され、毎年1校ずつ高校が廃校となる。南茅部の入学者数は、21年度に9人まで落ち込んだものの22年度は14人。しかし、23年度9人、24年度4人となり、「再編整備留保の集中取組期間中に2年連続10人未満」とした「指針」が適用された。
函館市では、合併前の旧4町村の地域から高校がなくなり中心部に一極集中することとなる。募集停止とされる地域の子どもたちは、遠距離通学や下宿などをせざるを得ない。北海道の多くの地域は公共交通機関の便が限られることから保護者による送迎で通う子どもが少なくなく、特に冬期の道路状況などを鑑みると、財政面だけでなく、時間、安全、体力、精神面など様々な観点で子ども、保護者に負担が大きい。家族全員の転居を選択する家庭もあり、高校がなくなることで地域社会の停滞なども懸念される。
各市町村では、通学費の補助やタブレット端末・制服等の購入補助金の措置、地域住民や地元の小中学校との連携など高校存続および高校の魅力化発信のため既に様々な努力を重ねている。毎年、「指針」が示す生徒数を超える・超えないに翻弄され、学級減や募集停止につながらないよう足繁く札幌へ通い、道教委に要請している。道教委は、「地元市町村や企業等と連携し、地域課題の解決等に取り組む学習活動を推進するなど、一層魅力ある高校づくりに努める」としているが、「公立高等学校配置計画地域別検討協議会」では、真に地域に寄り添い高校存続のために何ができるかを「協議」をする場になっているとは言い難い。
この20年間で60校の公立高校が廃校となり、子どもの遠距離通学や転居、地域経済・文化の活力が奪われるなどの問題が生じた。少なくともこれ以上は中卒者数の状況、募集定員に対する欠員の状況、地元からの進学率」などを口実にした機械的な「削減ありき」の姿勢ではなく、地域との丁寧な協議による「存続ありき」の姿勢に改めるべきである。
「公立特別支援学校配置計画」は、25年度の進学希望見込数を1,439人、定員を全しょうがい児学校(本科)60校で1,712人とし、職業学科を含む知的しょうがい児学校(高等部)24校では、25年度に道南・道北圏で既設校活用による2学級増を計画し定員を896人(昨年比16人増)とした。また、26年度には「道央圏で8学級」「オホーツクで1学級」相当の定員の確保を検討し、既設校で対応するとした。
中学生の人口が減少しているにもかかわらず依然として増加している要因は、「特別支援教育」により分離・別学をすすめていることにある。「特別支援学校」への通学は、保護者の遠距離送迎や寄宿舎生活となることが多く、地元での進学を望む子どもや保護者は少なくない。「国連・障害者権利委員会」から「すべての障害のある児童に対して通常の学校を利用する機会を確保すること」とした勧告を受け止め、「合理的配慮」のもと、地元の高校に進学できるようにすべきである。
少子化がすすんでいる実態があるものの、少人数でも運営できる学校形態を確立し、地域からこれ以上学校をなくさないことが重要である。北教組は、近隣複数校が連携し、1年次は共通科目を地域の校舎で、2年次以降進路希望に応じて子どもが他校舎を行き来できる「地域合同総合高校」を提唱してきた。
北教組は、「指針」「配置計画」の撤回・再考を求めるとともに、希望するすべての子どもがしょうがいのある・なしにかかわらず地元で学べる「地域合同総合高校」の設置など、子どもの教育への権利と教育の機会均等の保障を実現させるため、道民運動を一層強化していくことを表明する。
以上
2024年9月6日
北海道教職員組合
中教審「『令和の日本型学校』を担う質の高い教師の確保のための環境整備に関する総合的な方策について~全ての子供たちへのよりよい教育の実現を目指した、学びの専門職としての『働きやすさ』と『働きがい』の両立に向けて~(答申)」に対する北教組声明
2024年8月27日
中教審は8月27日、「『令和の日本型学校』を担う質の高い教師の確保のための環境整備に関する総合的な方策について~全ての子供たちへのよりよい教育の実現を目指した、学びの専門職としての『働きやすさ』と『働きがい』の両立に向けて~」を文科大臣に答申した。
「答申」は、「審議のまとめ(2024.5.13)」に示された内容とほぼ変わらず、「答申」の内容を進めるための工程表を作成し、「学校・教師が担う業務に係る3分類」に基づく「対応策の例」を付加するとともに、今後の検討が期待される事項として「スポーツ・文化芸術活動に継続的に親しむ機会の確保に向けた、地域の環境整備の中での部活動改革の在り方等」を追記したものになっている。
文科省は「答申」をまとめるにあたり、「審議のまとめ」に対してのパブリックコメントを行い、2週間で18,354件の意見が寄せられた。その中には、①「審議のまとめ」では、教職員の長時間労働は改善しない、②給特法の廃止・抜本的な見直しを求める、③長時間労働の一層の是正のためには、学習指導要領の内容の精選とそれに伴う標準授業時数の削減など確実な業務削減と大幅な教職員定数改善が必要、などの声が多く寄せられていた。しかし、こうした意見は、答申にほとんど反映されていない。「教員のなり手不足」や欠員不補充が一層深刻化する中にあって、学校現場の当事者からの意見をないがしろにする文科行政のあり方に対して改めて最大限の懸念を表明する。
「教師の持ち授業時間数の在り方」では、小学校高学年の教科担任制の推進については、定数改善と既存の加配措置を合わせ、あたかも全ての学校において3.5単位時間程度の軽減がはかられるかのような記載をしている。しかし、かねてから指摘している通り、3,800人の加配であり、その効果を得るのは、全国で18,000校を超える小学校の2割程度にすぎない。
「新たな職と級」「学級担任手当」については、教育現場にさらなる分断をもたらすものであって、教職員の「働きやすさ」「働きがい」に結びつくことはなく、多様な教職員の協働体制で子どもたちを育てる学校の創造をむしろ阻害するものである。
「答申」では、週当たりの授業時数を減少し、授業日数を増やすことで、「教員」や「児童生徒」の負担軽減をはかった具体的な例を紹介するとしている。しかし、教職員の負担軽減のみならず子どもの負担軽減をはかるために必要なことは、学習指導要領の内容と標準時間を削減することであり、教職員定数を大幅に改善することである。
「答申」では、「各主体が自分事として、取組のスクラップアンドビルドを改めて徹底し」と教育委員会、管理職によるマネジメント強化、自助努力の強化をさらに促している。これまで指摘してきた通り、教職員の長時間労働の常態化に至った大きな要因は、文科省が「基礎定数」の改善を行うことなく、「学習指導要領」において次々と新たな課題を積み重ねてきたことにある。まさに文科省が「ビルドアンドビルド」で新たな業務を学校に上乗せし続けててきたにもかかわらず、自らの責任を曖昧にし、学校現場にさらなる自助努力を求める姿勢は断じて容認できない。
北教組は、すべての子どもの学習権を保障し、学校がゆたかで実りある学びの場となるよう、「長時間労働の常態化」をはじめとする学校現場に山積する諸課題の解決に向け、「給特法」の廃止・抜本的な見直し、「基礎定数改善」など国における教育予算の拡充などを求め、広く地域や保護者と連帯し、抜本的な超勤解消に向け運動を強化していく。
以上
2023年6月27日
北海道教職員組合
北教組第128回中央委員会 中央執行委員長あいさつ
2024年6月30日
北教組第128回中央委員会 中央執行委員長あいさつ
北教組第128回中央委員会の開催にあたり、一言ご挨拶を申しあげます。まず、日々子どもたちのために奮闘している中央委員、役員、組合員の皆さんに、本中央委員会に全道から結集いただいたことに対し感謝申しあげます。
さて、イスラエルによる大規模なパレスチナ攻撃がはじまってから、半年を超えました。 イスラエルの圧倒的な軍事力によるガザ攻撃は熾烈をきわめ、ガザは未曾有の人道危機に陥っています。ガザ保健省の6月の発表によると、ガザで死亡したパレスチナ人は3万6,000人を超えました。このうち約4割を子どもが占めています。ガザでは少なくとも1万5,500人以上の子どもたちの尊い命が失われたとされています。また、ユニセフによると、ガザでは今年の2月の時点の推計で約1万7,000人の子どもが親を失い、家族と離ればなれになっているといいます。5歳以下の乳幼児のうち、丸一日食事をとれなかったことのある子どもは85%に上り、重度の急性栄養不良状態にある子どもの数は3万7千人に達しています。このような著しい恐怖と欠乏に陥った場合、子どもたちの心の中に、イスラエルに対する憎悪の感情が生じても不思議ではありません。武力攻撃は、憎しみの連鎖、報復の連鎖を生じさせます。武力で平和はつくれないことを改めて確認することが重要です。また、一端戦闘がはじまってしまうと、そう簡単に終息することはなく、多くの民間人の命が奪われ続けます。とりわけ子どもの命が無残に奪われ続けていくのが戦争や国際紛争の実相です。「国家の論理」のために「個人の命・人権」が犠牲になるのが戦争であることも改めて確認する必要があります。さらには、「他国を侵略しない」「民間人を攻撃しない」とした国際法の規範が破られるなど、法やルールが簡単に破られ秩序がなくなるのが戦争や国際紛争の実態であることにも留意する必要があります。加えて、イスラエルはガザ攻撃を「自衛戦争」と主張し、プーチンロシア大統領はウクライナ侵攻を「祖国を守る戦い」と正当化しています。このように「自衛」と称して多くの戦争や紛争が行われていることも忘れてはなりません。私たちは、一刻も早く武力による攻撃を止めなければなりません。また、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないようにしなければなりません。
しかし、岸田政権は、政治と金の問題や国民が苦しむ物価高の問題等には何ら有効な手立てを講ずることなく、「戦争する国づくり」だけは閣議決定という国会・国民軽視の手法ですすめており、許されません。例を挙げれば、「敵基地攻撃能力」保有の閣議決定による専守防衛の原則の空洞化にはじまり、世界3位の軍事大国となるGDP2%5年間で43兆円に及ぶ防衛費の大幅増額、殺傷能力のある武器の最たるものである次期戦闘機の第三国への輸出解禁、「台湾有事」を口実にした沖縄・南西諸島の基地要塞化、自衛隊や海上保安庁が平時から民間の空港や港湾を円滑に利用できるよう「特定利用空港・港湾」に北海道5ヵ所を含む計16カ所を指定するなど、枚挙にいとまがありません。外交政策においても、日米同盟の強化と中国に対抗するような多国間連携の枠組みづくりに腐心し、「敵・味方」を色分けしようとしているとしか思えません。
このままでは、限りない軍拡競争に陥りかねないばかりか、周辺国に徒に緊張をもたらすだけです。戦後日本は、平和国家としての信用を外交上の大きな財産としてきました。今まさに、平和国家としてその内実が問われていると言えます。やはり、軍拡ではなく、近隣国との意思疎通に努め、緊張緩和や信頼醸成をめざす努力を惜しまず、外交力を高め平和外交を展開すること、その信頼をもとに和平に向けて当事者に働きかけることこそが、恒久の平和を念願する日本が行うべきことと考えます。私たちは、「教え子を再び戦場に送らない」の決意の下、反戦・平和の運動を一層強化していく必要があります。
次に教育に目を向けると、学校が益々国や財界にとって都合のよい「人材づくり」の場に変質させられようとしています。子どもたちは、画一的なものさしで優劣を決められる過度な競争環境の中に置かれています。また、世界的な教育の潮流が、思索型・探求型のクリティカル・シンキングの育成に主な目的を置くようにシフトしているにもかかわらず、日本は「いかに早く一つの正解にたどり着くか」を競い合っている状況にあります。文科省は「主体的・対話的で深い学び」をめざすとしていますが、その内実は、きわめて形式的であり、現実に起こっている社会的事象について批判的に考えることついては、極力遠ざけようとしています。現在の日本の教育は、いわゆる「コスパ」「タイパ」を最優先する若者の志向を助長しているように思えてなりません。同時に、物事を創造していく力、物事を多面的に捉える力、多様な意見を聞き熟議を行う力などを育てることがおろそかになっているように感じます。私たちは、改めて民主主義に貫かれた「主権者への学び」をめざして、子どもたちを権利主体として捉えた学びの実現に向け、実践を重ねていく必要があります。
一方、教職員の長時間労働が、こうした実践をすすめる上で大きな妨げになっています。教職員は過酷な長時間労働が常態化することで、日々の業務に忙殺されるだけでなく、過労死と隣り合わせと言っても過言ではない状況に置かれています。また、学校が「ブラックな職場」であると社会で認知されるようになり、教員採用試験の倍率が年々下がり続けています。2025年度の北海道の公立学校教員採用試験の志願状況では、札幌市を含む志願者は前年度比483人減の3,582人となり、過去最少となりました。深刻なのは教員の「なり手不足」だけではありません。新卒教員が1年を待たずして離職する、高齢層職員が60歳前に離職する、定年延長を望まないなど、現職の離職者が年々増加し、欠員不補充の問題に拍車をかけています。これらは、子どもたちの学習権保障に直結する問題であり、教育の機会均等を脅かしかねないきわめて重要な問題です。
言うまでもなく、教職員の長時間労働常態化の抜本的解消には、基礎定数増による教職員定数改善と現行「学習指導要領」の内容削減とそれに基づく年間の標準授業時数の削減による業務削減が必要不可欠であり、法的な措置として「給特法」の廃止・抜本的な見直しが必要です。中学校・高校においては、平日を含めた部活動の社会教育への移行が必要です。
しかし、5月に示された中教審の「「令和の日本型学校教育」を担う質の高い教師の確保のための環境の整備に関する総合的な方策について(審議のまとめ)」は、教員の長時間労働の解消、「なり手不足」解消、欠員不補充解消の何れの問題に対しても、まったく実効性が期待できないものとなっています。文科省調査によると、教職員の精神疾患による病気休職者数は、6,539人(22年度)と過去最多を更新し、精神疾患による1カ月以上の病気休暇取得者を含めると1万2,197人にも上っています。日本の公立学校は既に持続可能なシステムとは言えない危機的な状況にあります。教育に予算かけずに、これを放置することは許されません。そのためには政治を変えなくてはなりません。
北教組は、組織拡大はもとより、子どもたちのゆたかな学びの保障に向け、当面、教職員の長時間労働解消、「学習指導要領」の内容・時数過多など「カリキュラム・オーバーロード」の解消、子どもをとりまく過度に競争的な環境の解消、この3つの解消に重点を置いて、今後も組織の総力をあげてとりくんでいくことを約束し、開会の挨拶に代えさせていただきます。ともにがんばりましょう。
2023年6月27日
北海道教職員組合
中教審「質の高い教師の確保特別部会」の「審議のまとめ(素案)」に対する北教組声明
2024年4月19日
中教審「質の高い教師の確保特別部会」の「審議のまとめ(素案)」に対する北教組声明
中教審「質の高い教師の確保特別部会」(以下、「特別部会」)は4月19日、第12回部会において、「時間外勤務手当・割増賃金及び休日手当」を支給しないとする現在の「給特法」の基本的な枠組みを存置した上で、「教職調整額」を「基本給の4%から少なくとも10%以上にする」ことを柱とする「審議のまとめ(素案)」(以下、「素案」)を公表した。「素案」は他に、①「学級担任手当」を創設する、②若手教員をサポートするため「教諭」と「主幹教諭」の間に「新たな職」を設ける、③小学校中学年に教科担任制を導入する、などとした。
これらは、喫緊の課題である教職員の過酷な長時間労働の常態化と教職員のなり手不足・欠員不補充の双方に対して、何ら実効ある対策となるものではなく、むしろ、現状維持あるいは悪化させ、結果として子どもたちの学習権を著しく侵害することになりかねないことから、最大限の懸念を表明する。
第一に、過酷な長時間労働常態化の抜本的解消策は、定数改善と業務の削減に他ならないにもかかわらず、「素案」ではその本丸に手をつけずに避け、賃金改善のみにとどまっている。昨年8月の中教審「緊急提言」による業務削減においても実感できる効果は微々たるものであった。また、小学校中学年への教科担任制も、基礎定数化されるものではなく、わずかな「加配」措置にとどまることが想定され、効果はきわめて限定的なものである。
第二に、教職員志望者が激減している大きな要因の1つは、学校が「ブラックな職場」と受け止められていることにあるが、「素案」は全くそれを払拭するものとなっていない。
第三に、「給特法」の基本的な枠組みが維持されることで、①所定の勤務時間外に授業準備・ノート点検など翌日の授業までに必要不可欠な業務を行ったとしても「自発的勤務」として評価されることに何ら変わりがない、②「定額働かせ放題」が維持され、調整額が上がれば時間外勤務を行うことが当然との雰囲気が一層強まりかねない、③文科省・教育委員会による業務削減に向けたインセンティブが働かない状態を継続するものである、など「給特法」の根本的問題を何ら解決するものとなっていない。
この間「特別部会」では、委員から、「(残業代を支払えば)長時間労働を助長する危険がある。業務の質の違いを無視した不公平を生じかねない」「一定の裁量を任されている教員に対し、(どこまでが業務かを)切り分けることは学校現場の状況になじまない」など、自発性・創造性が期待される教員の特殊性から、時間外勤務手当化がなじまないとする意見が示された。しかし、時間外勤務手当を支払わないことで、これまで文科省・教育委員会から学校現場に「ビルド アンド ビルド」で業務が上乗せされてきたのが現実であり、「労基法」の時間外勤務を抑制する「割増賃金」の趣旨を否定することは許されない。また、翌日の授業準備や教材研究など必要不可欠・急迫の本来業務が所定の勤務時間外で行われていることが大きな問題であり、日常多くの場合「どこまでが業務か」など峻別が必要な事例は稀である。さらには、自発性・創造性にもとづく勤務を期待することと、勤務時間管理を行うことは、他の職業と同様に十分両立可能であり、難しいことではない。
学校現場からは、「お金の問題ではなく、業務を減らし、人を増やして欲しい」「人間らしい生活を保てる職場を望む」「もっと教材研究をする時間が欲しい」「子どもたちとゆとりをもって接することができる職場にして欲しい」といった切実な声が寄せられている。これは、ひとえに「教員を増やさない」予算の抑制と「教育内容と授業時数は減らさない」という的を射ない方策に終始しているからであり、このままでは教員は疲弊するばかりで学校現場の崩壊を止めることができない。ひいては、子どもたちの学びを阻害することになる。
北教組は、引き続き、①労働基準法の適用除外を認める「給特法」廃止・抜本的な見直し、②教職員定数を増やすための「義務標準法」改正、③年間標準授業時数を削減するための「学習指導要領」改訂、④「部活動」の社会教育への移行、などを求め、広く地域や保護者と連帯しながら抜本的な超勤解消策に向けた運動を強化していく。
北教組は、組織拡大はもとより、子どもたちのゆたかな学びの保障に向け、当面、教職員の長時間労働解消、「学習指導要領」の内容・時数過多など「カリキュラム・オーバーロード」の解消、子どもをとりまく過度に競争的な環境の解消、この3つの解消に重点を置いて、今後も組織の総力をあげてとりくんでいくことを約束し、開会の挨拶に代えさせていただきます。ともにがんばりましょう。
以上
2023年6月27日
北海道教職員組合