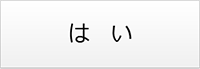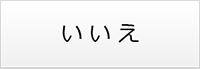中教審「新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のための学校における働き方改革に関する総合的な方策について(答申素案)」及び文科省「公立学校の教師の勤務時間の上限に関するガイドライン(案)」に反対する声明
2018年12月6日
中教審「学校における働き方改革」特別部会は12月6日、「第20回学校における働き方改革特別部会」において、中教審「新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のための学校における働き方改革に関する総合的な方策について(答申素案)」(以下「素案」)及び文科省「公立学校の教師の勤務時間の上限に関するガイドライン(案)」を公表した。
「素案」は、昨年12月の「中間まとめ」で示した「学校及び教師が担う業務の明確化」と様々な専門スタッフの配置や勤務時間を客観的に把握し集計するシステムの構築などに加え、①月45時間を上限とする「勤務時間の上限に関するガイドライン」の作成、②一年単位の変形労働時間制の導入、③主幹教諭の配置を促進しミドルリーダーとしてリーダーシップを発揮できるような学校運営体制の見直し、④ストレスチェックの全校実施など労働安全衛生管理体制の整備、⑤人事評価においてより短い在校時間で成果をあげた者に高い評価を付与するなど教職員の働き方の意識改革、などを骨子とするものである。
「素案」は、一人あたりの持ち授業時間数が多いことで本来業務自体が過多となり超勤が常態化している実態に対して、何ら具体的な業務削減を示さず、業務の平準化や本来業務以外の精選、サポートスタッフの配置、「学校の組織運営体制」の見直しとマネジメントの強化などをすすめるとするもので、根本的要因を解決するものとなっていない。また、抜本的な勤務・教育条件の改善に向けた教職員定数増も行わず、超勤を助長する元凶となっている「給特法・条例」の時間外勤務手当・休日手当・割増賃金の不支給も一切見直さず、文科省が第一に行うべき必要な法改正と予算措置など、問題の核心には手をつけずに放置するもので、断じて容認できない。強く抗議する。
「1月の時間外勤務の上限を45時間」とする「勤務時間の上限に関するガイドライン」の導入は、何ら法的拘束力がなく違法を厳格に排除するものとなっていない。これでは1日の勤務時間を7時間45分と規定した「勤務時間条例」や「時間外勤務は原則命じない」と規定した「給特条例」の規定を形骸化して月45時間までの超勤を許容するためのガイドラインになりかねず、許されない。
「素案」で示された「1年単位の変形労働時間制」を導入は、教員には「給特法」が適用され時間外勤務手当・割増賃金、36協定による超勤抑制が機能しない中で、さらに1日8時間・週40時間以内の労働時間規定までも除外し、労基法における労働者の権利を守る根幹となる規制のほとんどを教職員から剥奪し、「健康で文化的な生活」を脅かすものである。「過労死ライン」相当の超勤が常態化している中で、何ら業務量を削減せずに「一年単位の変形労働時間制」を導入することは、「超勤」を「正規の勤務時間」へと評価を変えるだけで、超勤実態を固定化・恒常化させ、むしろ現行の「給特法」以上に超勤が認黙され、超勤手当不支給の違法を容認するシステムとなりかねない。
総じて「素案」は、超勤の根本要因と現行の「給特法・条例」の下での法と現場実態との乖離から目を逸らし、「教員の職務と勤務態様の特殊性」「教員の専門性」を口実に、「給特法」を維持し超勤手当不支給による長時間労働政策の継続とその合理化に向かうとともに、超勤問題に乗じて学校の管理統制を一層強化しようとするものである。
文科省は、市町村教委・学校には「働き方改革」の着実の実施を求める一方で、改訂「学習指導要領」の円滑な実施を標榜し、授業時数の更なる増加や競争と管理の教育など超勤解消に逆行した施策をおしすすめようとしており、自らの責任は棚上げし、教育行政としての責務を放棄していると言わざるを得ない。
北教組は、引き続き文科省・道教委に対して授業時数増やゆとりのない教育課程、過密な日課など、子どもたちからゆとりを奪い学校現場に超勤・多忙化を強いる学習指導要領体制、「点数学力向上策」の押しつけなどの教育政策の転換を求めるとともに、「持ち授業時間数削減」に向けた教職員定数改善や現場実態と大きく乖離している「給特法・条例」の抜本的な見直しなどを求め全力でとりくんでいく。
2018年12月6日
北海道教職員組合
2018年度道教委「全国学力・学習状況調査北海道版結果報告書」に
対する北教組声明
2018年11月8日
道教委は11月6日、2018年度「全国学力・学習状況調査北海道版結果報告書」(以下「報告書」)を公表した。今回の報告では、175市町村が結果公表に同意し、19市町(昨年比10市町増)が実数での平均正答率の公表となった。これは、道教委が各市町村教委に対して執拗に「結果公表」を求め続けてきた結果で、こうした一層競争・序列化を加速させる姿勢は、断じて容認できない。
「報告書」では、「中学校の国語Aと理科で全国平均を上回り、他教科では全国平均に達していないものの差が縮まっている」とした8月の「北海道 調査結果のポイント」をもとに、全道状況として、①平均正答率の推移、②各領域の平均正答率、③学習・生活・規範意識などの質問紙調査結果、④正答数の状況、を示し全国との比較に終始している。また、14管内の平均正答率の分布と市町村規模別の平均正答率の比較を行い、175市町村の状況及び「学力向上策」を列挙している。これは、「平均正答率は、都市部を含む管内よりも町村部だけの管内で低い傾向が続いている」「都市に比べて地方では1日当たりの学習時間が少ない」など、地域間「格差」を煽る単なる点数の比較にとどまるものであるにもかかわらず、「学校全体での授業改善が必要」「学習習慣の確立に向けた取組をすすめる」など、学校現場に対してさらなる努力を求めている。
また、継続的に成果を上げているとする3県(秋田・福井・石川)について、「主体的・対話的で深い学びの視点からの授業改善に関する取組」をはじめ「教員研修」「カリキュラム・マネジメント」「家庭学習」など、改訂「学習指導要領」の観点から詳細に取組状況を北海道と比較し、「点数学力向上」の取組を促している。同日公表した「資料編 北海道の学力向上関連の取組と検証及び改善に向けた取組」は、何ら因果関係が明確になっていないにもかかわらず、①主体的・対話的で深い学びの視点からの授業改善、②検証改善サイクルの確立、③小学校と中学校が連携した取組の充実、④望ましい生活習慣の確立、の4点に課題があると一方的に結論づけ、「組織的な授業改善」が必要であるとして、授業内容・方法をマニュアル化し、子どもの実態と乖離した画一的な指導を押しつけようとしている。
道教委の分析は、「学校が検証改善サイクルの確立に取り組んでいるものの教科に関する調査結果にその効果が十分に現れていない」「ゲームなどをしている児童生徒の割合が全国よりも高い」ことをもって、全道一律に「授業」や「研修」さらには「家庭生活」の改善を求めている。これは、極めて短絡的であり、一層競争主義にもとづく施策をすすめようとしているものである。
道教委はこの間、各学校における教育課程編成権を蔑ろにし、教育内容・方法・評価にまで詳細にわたって不当に介入し、学校に対して画一的な「学力向上策」の押しつけをくり返してきた。こうした「授業改善」「検証改善サイクル」の名のもとにすすめる「学力向上策」は、子どもの多様性・主体性や教職員の専門性・創造性を阻害し、これまでの北海道における地域に根差したゆたかな教育を破壊するものである。子ども一人ひとりの「学び」は、ゆとりをもって見守り支えていくべきもので、「管理と競争」「点数学力」によって培われるものではない。「貧困と格差」の拡大・固定化など子どもの実態や社会状況について一切分析せずに、一方的に現場に責任を押しつける道教委の姿勢は、子どものゆたかな学びの保障や教育の機会均等の確保という教育行政の本来の目的すら見失っていると言わざるを得ない。
今、道教委がすべきことは、地域や子どもの実態に即し、ゆたかな教育を保障するため、押しつけの「学力向上策」直ちに止め、①経済格差がもたらした子どもの「貧困」を解消すること、②子どもの多様性を生かした「学び合い」を可能とする少人数学級を実現すること、③教育課程の弾力化や学校の裁量権を保障すること、④教職員定数を改善し教職員がゆとりを持って子どもと接することができるようにすること、など教職員の超勤・多忙化解消と教育条件の整備・拡充をすすめることである。また、新聞をはじめマスコミも、全国や全道・地域の平均正答率の比較など「点数学力」を煽る報道ではなく、政府・文科省・道教委の差別・選別の教育が子どもや学校を追い詰めていることを直視し、批判・分析するなど、本来の報道の役割を果たすべきである。
以上のことから、北教組は、「学力調査・結果公表」に断固反対し、子どもたちの「学び」を矮小化する「点数学力」偏重の「教育施策」の撤回を強く求める。
私たちは今後も、憲法・「47教育基本法」・「子どもの権利条約」の理念にもとづく「ゆたかな教育」の実現のため、一人ひとりの子どもに寄り添う教育実践を積み重ね、市民とともに教育を子どもたちのもとへとりもどすための広範な道民運動をすすめていくことを表明する。
2018年11月8日
北海道教職員組合
第68次合同教育研究全道集会
集会アピールに関わる声明
2018年11月4日
北教組・道私教協は、帯広市において11月2日から11月4日までの3日間、全道各地よりのべ4000人の組合員・保護者・地域住民の参加のもと、第68次合同教育研究全道集会を開催しました。
安倍政権は、歴代政権が憲法違反としてきた「集団的自衛権の行使」を容認する閣議決定を行い、「特定秘密保護法」「戦争法」「共謀罪法」を矢継ぎ早に強行成立させるなど、「戦争する国」づくりのため邁進しています。臨時国会の所信表明において安倍首相は、「9条への自衛隊明記」を「国防の根幹」であるとし、国会の憲法審査会において「改憲」議論を加速させようと目論んでいます。また、柴山文部科学大臣は、「教育勅語」について「現代風にアレンジして教えていくことは検討に値する」「普遍性を持っている部分が見て取れる」などと発言し、戦前回帰の教育をめざしています。
私たちは、憲法改悪を断固阻止するとともに、国民を無視し、立憲主義を蔑ろにする安倍政権の暴挙を断じて許してはなりません。
こうした動きと一体的に、安倍政権は4月から移行措置が始まった改訂「学習指導要領」によって、「小学校外国語」の導入など政財界に都合の良い「資質・能力」の育成を目論み、また「道徳の教科化」によって「愛国心」「規範意識」など特定の価値観を押しつけ、教育内容・方法・評価にまで詳細に介入し、「競争と管理」の教育をめざしています。
文科省は2017年度に「いじめ」「不登校」が過去最多となり、小学校低学年の暴力行為も急増していることを公表しました。しかし、これは、授業時間数の増加や「学力向上策」などの政策によって分断・孤立化させられている子どもたちの苦悩を何ら顧みず、根本的な分析や対策を怠っています。教職員も「過労死レベル」の勤務実態の中、子どもたちと向き合う時間が奪われ、管理強化により創意ある教育実践が阻害され、孤立・分断させられています。
私たちは今次教研において、今まさに危機に直面している「平和を守り真実をつらぬく民主教育」の確立をめざし、全道各地の「抵抗と創造」の自主編成にもとづく教育実践について論議を深め、未来の主権者であるすべての子どもたちに民主教育を保障するため、次のことを確認しました。
第1に、「戦争法」「共謀罪」など「戦争する国づくり」の施策に断固反対し、平和憲法を守り、「教育基本法を元にもどす運動」をはじめ「教育を語る全道250万人対話運動」を基盤に地域住民・保護者との連携を一層強化し、「みんなで平和憲法を守り、教育を創る道民運動」をさらに広げること。
第2に、競争による差別・選別教育をおしすすめる改悪「学習指導要領」や、これにもとづく「学力向上策」「特別の教科 道徳」「小学校外国語」に抗するとともに、教育内容・方法・評価への不当な介入を許さず、個人の尊厳を尊び平和を希求する主権者を育むため、人権教育・主権者教育や憲法学習などをすすめ、子どもの多様な「学び」を保障する自主編成運動を強化すること。
第3に、過酷な勤務実態を解消し、子どもと向き合う時間の確保とゆとりある教育活動をすすめるため、抜本的な業務削減をはじめ、教職員定数増・欠員解消、持ち授業時数減、部活動の社会教育への移行とともに、無制限・無定量の超過勤務につながる「給特法・条例」の廃止・見直しを求めること。また、道教委に対して「北海道アクション・プラン」の見直しと実効ある超勤解消策を求めること。さらに「通報制度」「実地調査」など主体的・創造的な教育活動を阻み、教育の自由を侵害する不当な圧力をはね返し、民主教育の確立に向けて組織の総力をあげてたたかうこと。
第4に、憲法・「47教育基本法」・「子どもの権利条約」にもとづく子どもを主人公とした自主・自立の学校づくりをすすめること。また、「子どもの権利条例」の早期制定に向けた保護者・地域住民と連携する運動をつくり、さらに、連合・平和運動フォーラム・民主教育をすすめる道民連合など民主的諸団体や保護者・地域との共闘を強め、「日の丸・君が代」強制に反対する運動などをねばり強くとりくむこと。
第5に、文科省「特別支援教育」を実態化させず、「分けることは差別である」ことを確認するとともに、共生・共学をすすめインクルーシブ教育を実現すること。また、国連「障害者の権利条約」や「障害者差別解消法」の理念にもとづき、しょうがい者の社会参加を阻む社会的障壁を除去するために「合理的配慮」を行い共生社会の実現に向けてとりくむこと。
第6に、評価結果を賃金・任用・分限等へと反映させ、学校現場の協力・協働を阻害する「学校職員人事評価制度」については、撤廃を基本に、差別賃金・管理統制強化とさせず、すべての教職員の賃金改善とするよう、各級段階におけるとりくみを強化すること。
第7に、「主任制度」「主幹教諭制度」や「事務主幹制度」「新たなミッション加配」、「学校における働き方改革に関する緊急対策」などにもとづく教職員の差別・分断、管理強化に反対し、自律的・民主的職場づくりと、主任手当の社会的還元を含め、組織強化・拡大を組織の総力をあげてすすめること。また、「協定書」破棄の実態化を許さず、諸権利定着・拡大、超勤・多忙化解消をはかること。さらに、「教員免許更新制」の早期撤廃に向けてとりくむこと。
第8に、財政論に依拠した道教委「これからの高校づくりに関する指針」の撤回・再考を求め、希望するすべての子どもたちが地元の学校へ通うことができるよう地域の高校を存続させるとともに、「地域合同総合高校」の実現など、受験競争の解消とゆたかな高校教育改革をめざすこと。そのため、保護者・地域住民と連携した道民運動を強化すること。また、公私間の学費格差を解消するため、私学助成拡充をはかるよう求めること。
第9に、教育の機会均等を保障するため、「高校授業料無償化」への所得制限および朝鮮学校の無償化適用除外の撤廃、義務教育費国庫負担制度堅持・全額国庫負担を基本に、当面、負担率2分の1復元に向けて全国的な運動を展開すること。また、経済格差による「教育格差」の是正や「子どもの貧困」を解消するとともに「30人以下学級」の早期実現をめざし、当面、「新・教職員定数改善計画」の完全実施や「道独自の少人数学級」の実施拡大、給付型奨学金制度の拡充、「就学援助」の拡大、教育費の保護者負担の解消など、教育予算増額に向けたとりくみを強化すること。
第10に、「生涯健康管理体制」の押しつけに反対し、集団フッ素洗口中止、食物アレルギーに特化した対応の一方的な導入阻止、HPV・日本脳炎などワクチンの定期接種化の中止などを求め、子どものいのちと健康を守るとりくみをすすめること。また、特定の健康観の押しつけや差別につながる「全国体力・運動能力調査」の中止・撤回を求めること。さらに、個人情報保護の問題が危惧され、一層多忙化を助長させる道教委「校務支援システム」の早期撤廃、一方的な導入阻止に向けてとりくむこと。
第11に、「女性差別撤廃条約」の理念にもとづき、女性参画を推進し、学校や社会における性差別や性別役割分業の撤廃に向け、とりくみを強化すること。ジェンダー平等に対する攻撃を排し、学校教育のあらゆる場面で「ジェンダーの視点」を取り入れた実践をすすめること。
第12に、未だに収束を見ない「フクシマ」の現状から、「人類と核は共存できない」ことを再確認し、反核・反原発の学習をすすめるとともに、泊・幌延・大間をはじめとしたすべての原子力施設の廃止・建設中止を求め、「核・原発のない社会の実現」に向けてとりくみを強化すること。また、「被ばく」により、いのちを脅かされている子どもたちの状況の改善を求めるとともに、再生可能エネルギーへの政策転換を求め、自然との共存をめざす教育をすすめること。さらに、辺野古新基地・高江ヘリパッド建設阻止のたたかいを沖縄と連帯してすすめること。
世界の恒久平和を誓った憲法とその理念の実現をめざす民主教育は、今、戦後最大の危機に直面しています。私たちは、平和・人権・国民主権など憲法の原則を守り、個人より国家を優先する政府と文科省の政策を厳しく批判・分析し、「自分らしく」「よりよく生きる」教育の創造をめざして、地域・保護者と連帯して自主編成運動をさらに押しすすめる重要性を再認識しました。
「教え子を再び戦場へ送るな!」の決意を新たにし、憲法改悪に断固反対するとともに「47教育基本法」・「子どもの権利条約」の理念にもとづく「平和を守り真実をつらぬく民主教育の確立」に向けたとりくみを一層前進させていくことを確認し、集会アピールとします。
2018年11月4日
第68次合同教育研究全道集会
第68次合同教育研究全道集会
中央執行委員長あいさつ
2018年11月2日
子どもたちの学ぶ権利を保障し、平和を守り、真実を貫く民主教育の確立をめざして
第68次合同教育研究全道集会に参加された組合員・保護者・共同研究者の皆さん大変ご苦労様です。また、集会の成功に向け準備万端を整えていただきました帯広市支部の組合員をはじめ、地元、会場校など関係者の皆様に心より感謝申し上げます。
まず、9月6日に発生した「胆振東部地震」は、全道各地に甚大な被害をもたらしました。被災した皆様に心よりお見舞い申し上げます。
今回の地震では、直接的な被害とともに、「ブラックアウト」によって道民の生活や北海道経済に大きな被害がありました。「停電」が厳冬期だったら、泊原発が再稼働していたらと考えると戦慄が走る思いです。徹底した原因究明と再発防止を求めるとともに、原発再稼働を許さず、すべての原発廃炉と再生可能な自然エネルギーの推進に向け運動を一層強化していかなければなりません。
さて、第4次安倍内閣が発足しました。就任早々柴山文科大臣は、「教育勅語」について、「同胞を大事にする。国際的協調を重んじるなど基本的な内容、現代風にアレンジして教えていくことは検討に値する」「普遍性をもっている部分が見て取れる」などの暴言を吐きました。「教育勅語」は、「神話的国体観に基づいている」「基本的人権を損なう」など、憲法・教育基本法の理念に反することから、1948年衆・参両院で排除・失効確認がされています。
特に、参議院の失効確認では、「教育勅語等が従来の如き効力を今日なお保有するかの疑いを懐く者あるをおもんばかる」として、政府に教育勅語その他の詔勅の謄本をもれなく回収するよう求めています。文科大臣の発言は、こうした国会決議の内容に悉く反し、「道徳教育で教える」など論外で、断じて許されません。
この夏に、私は鹿児島県の知覧を尋ねました。それは、今話題となっている「不死身の特攻隊」という鴻上尚史(こうかみ しょうじ)さんの本を読んだことがきっかけです。9回出撃して、生きて帰ってきた「当別町出身」の「佐々木友次(ともじ)」さんを描いたものですが、当時、「特攻」で華々しく散ることは絶対的命令で、体当たりすること自体が「自己目的化」される中で、死ぬことよりももっと大事な使命があるとの確信にもとづき、これに背き続けた人物の実話です。
今、「特攻隊」をはじめ、かつての戦争を題材にした本が話題となり、「教育勅語」の復活を願う動きがある中で、「忠君愛国」「国のために身命を投げだして努めよ」という「修身」など戦前・戦中の教育が果たした役割と多くの若者たちを戦争に追いやった現実を、改めて直視することが求められているのではないでしょうか。
「9条改憲」が目論まれ、「特定の教科道徳」をはじめ、「国家に都合の良い人材づくり」をめざす「学習指導要領」の移行措置がスタートする歴史的な転換点の中で開催される今次教研は、私たちがすすめてきた自主教研運動の真価が問われる大事な集会と言えます。
この時にあたり、皆さんとともに、教研集会が何を目的とし、どのような問題意識で始められたのかを振り返り、自主教研の原点を確認したいと思います。
第1次教研は、1951年11月に日光で開催されました。当時の状況は、前年の朝鮮戦争勃発を契機に、自衛隊の前身である警察予備隊が創設され、教員の政治活動の制限、特設道徳と国定教科書が目論まれるなど、国家主義的な政策が急速に強まりました。先輩教職員が、こうした状況を深刻に受け止め、戦前・戦中の教育への痛切な反省のもと、平和への固い決意を出発点として、自主教研をスタートさせました。これに先立つ1月に開催した中央委員会において日教組は、「教え子を再び戦場に送るな」のスローガンを採択し、第1回と第2回の全国教研の講演のテーマは「平和と教育」でした。
教研の基本目標を「平和を守り真実を貫く民主教育の確立」と定めたのも、平和と教育を自らと国民の手で守りつくることが自主教研の原点であると考えたからでした。
今日の情勢を捉えるなら、この重要性がますます増大しています。68次の自主教研の積み重ねは、その時々の教育への攻撃を、地域と現場からの実践に根ざしたエネルギーによってはねのけ、民主教育を確立してきた確かな足取りでありました。
今、政府主導の教育は、子どもたちを孤立・分断化し、排他的な競争意識や自他への不信感を拡大させ、いじめ・不登校・引きこもり・暴力行為・自殺など苦悩を一層深刻化させています。
教職員の超勤・多忙化解消は、待った無しの課題です。現在中教審で論議されているような単なる業務の効率的運用や組織機構の整備ではなく、正規の勤務時間内に業務を終えることが可能な定数増、持ち授業時間数減とともに、「給特法」の廃止・見直しなど抜本的な法整備を求めて行かなければなりません。
私たちはこの間、学校現場の危機的な状況を踏まえ、学校改革・教育課程自主編成推進委員会「報告」などをもとに、組織的に学習を深めてきました。学校のあらゆる場面で、憲法・「子どもの権利条約」の理念にもとづき、学ぶ権利と教育活動への参画を保障し、学校が子どもたちにとって安心して生活し学ぶ場となるよう実践を強化しなければなりません。
教研集会に参加した皆さん。すべての分科会で、持ち寄った実践をもとに交流してください。
今、私たちが置かれている社会・経済状況と政府・文科省の「政策」がめざすものを厳しく分析・批判し、子どもの現実や地域・社会と教育のかかわりなどについて議論を深めてください。平和で民主的な社会を希求する主権者を育むため、「抵抗と創造」の自主編成のとりくみを強化し、地域・保護者と連帯して具体的運動をすすめる方向性を確認していただきたいと思います。
「教え子を再び戦場に送るな」の固い誓いのもと、子どもたちが意欲をもって学ぶことができるよう、「平和を守り、真実を貫く民主教育の確立」にむけて、本集会が、さらなる前進をはかる場となることを願い挨拶とします。ともに頑張りましょう。
2018年11月2日
北海道教職員組合 中央執行委員長
2018北海道人事委員会勧告に
関わる声明
2018年10月10日
1. 北海道人事委員会は10月10日、公民較差で減額前の職員給与より民間給与が637円(0.17%)上回り、一時金についても民間支給月数が0.04月職員の年間支給月数を上回っていることから、月例給および一時金について、人事院勧告の内容に準じ引き上げ改定する勧告を行った。
2. 地公三者共闘会議(全道庁労連、北教組、自治労道本部)は、17年にわたる給与の独自削減が一般職について2016年3月末に終了したものの、長期間、独自削減が行われた組合員・家族の生活実態を考慮した勧告を行うよう求めてきた。本年の勧告は、人事院勧告の内容に準じて給料表および一時金の支給月数を国と同水準となるよう増額し、5年連続の引上げとなった。今年も、一時金を国と同水準の4.45月の引き上げ、また、長年求めてきた獣医師の処遇改善について初任給調整手当の支給限度額引き上げと支給期間の延長は、来年度実施ではあるが、厳しい職場実態を受け止め、組合員の期待に応える内容であり、人員確保の観点からも評価するものである。
3. 月例給について、国同様の給料表改定では、2015年度の給与制度総合見直しや本年4月からの現給保障終了により、中高齢層職員にとっては引き上げの実感が少なく、不満が残るものである。また、再任用職員に対する生活関連手当の支給が勧告されなかったことは、退職後の厳しい生活実態をなんら考慮したものとなっておらず、強く抗議するものである。
一時金の引き上げ0.05月分について期末手当に配分しなかったことは不満だが、今年においても6月期と12月期の勤勉手当に均等に配分したことは、公平性の観点から受け止める。
一方、重点課題であった新規採用者への特地勤務手当に準ずる手当の措置や号俸増設、そして臨時・非常勤職員の処遇改善について、勧告されなかったことは抗議するものである。
4. その他、公務運営に関する報告では、「採用から退職までの視点に立った人事管理」や「その他の勤務環境に関する課題」について触れられている。特に、「定年年齢の段階的な引き上げ」については、「国や他府県の動向を注視」との姿勢に止まったものの、「その他の勤務環境に関する課題」において、長時間労働の是正にむけ、時間外勤務命令の上限時間を設定することや教職員の多忙解消にむけ実効性ある取り組みを着実に進めていくことが必要と言及しており、今後、道および道教委当局へ具体的な取り組みを進めていくよう強く求めていく。
5. 今後、地公三者共闘会議は、道および道教委に対し、北海道の給与決定が多くの民間労働者に波及し、延いては未曾有の胆振東部地震からの復旧・復興に取り組む北海道経済に大きな影響を与えることも十分踏まえ、組合員・家族の実態を考慮した誠意ある労使交渉を行うことを強く求め、諸要求の実現に向けた取り組みに組織の総力を挙げていく。
2018年10月10日
北海道公務員共闘会議地公三者共闘会議
道教委2019年度「公立高等学校配置計画」および「公立特別支援学校配置計画」に対する声明
2018年9月4日
道教委は9月4日、2019年度から3年間の「公立高等学校配置計画」と2019年度および20年度以降の見通しを示した「公立特別支援学校配置計画」を決定した。
「公立高等学校配置計画」の内容は、19年度について、①夕張、松前を地域連携特例校とする、②私立江陵(4学級)と道立幕別(1学級)を再編統合し3学級の新設校を設置する、③1学級相当以上の欠員が生じ学級減とした15校のうち12校は1学級を復活し、2学級減とした深川西は1学級のみ復活、野幌と根室はそのまま1学級減とする一方で、羅臼は管内の中卒者数増を理由に1学級増とした。20年度については、①釧路工業の電子機械科を1学級減じ、深川東など5校についても1学級減じ学科転換する、②岩内の事務情報科を地域産業ビジネス科に学科転換し単位制を導入するとした。さらに、21年度については、①南幌を募集停止とする、②道立女満別と町立東藻琴を再編統合し1学級の町立校を新設する、③滝川など16校で計17学級減とする、④伊達緑丘の1学級減について、今後の市の検討結果を勘案し伊達との再編を含め変更することがある、とした。
これらは、6月に公表した「配置計画案」と何ら変わらず、「これからの高校づくりに関する指針」(以下「指針」)にもとづき、今後3年間で1校の募集停止をはじめ再編・統合、学科転換などによって56校で57学級減の大規模削減を強行するものである。
道立幕別と私立江陵、道立女満別と町立東藻琴の再編統合および伊達と伊達緑丘の再編検討などは、自治体の意向を口実にした「指針」「配置計画」にもとづく機械的削減であり、子どもや保護者の要求を蔑ろにするものである。また、深川西、野幌、根室の学級減を今になって決定したことは、進学を考えていた子どもや保護者にとって、進路変更の検討を余儀なくされるなど、大きな混乱を生じさせるものである。
「公立特別支援学校配置計画」は、19年度について、6月の「配置計画案」に加え、新たに平取養護と旭川養護の普通科重複学級をそれぞれ1学級増とし、全しょうがい児学校61校において6学級23人の定員増とした。さらに、20年度についても全道で5学級相当の定数増を検討するなど、分離・別学を一層加速させるものとなっている。
道教委が「特別支援教育」の名のもとにすすめる差別・選別の施策は、中卒者数が減少傾向にあるにもかかわらず特別支援学校への入学を希望する子どもの数を年々増加させている。「分けることは差別につながる」とした「国連障害者権利条約」の理念にもとづき、希望する子どもたちの地元の普通高校への入学を保障するよう、すべての学校において「合理的配慮」などの教育条件整備をすすめることが、道教委の果たすべき最大の役割である。
本「配置計画」は、高橋道政による中央追随・財政最優先、地方切り捨ての政策にもとづくもので、地域の経済を一層疲弊させ、文化の衰退を招くとともに、子どもたちの遠距離通学や保護者の経済的負担を増加させ、「貧困と格差」を拡大させるもので、断じて容認できない。私たちはこれまで、北教組要請行動や地域別検討協議会において、「指針」「配置計画」の撤回 ・再考を求めてきた。中卒者数の減少期だからこそ道教委は、一人ひとりの子どもたちの要求に応えゆたかな後期中等教育を保障すべきである。
私たちは引き続き、子ども・保護者・地域住民の高校存続を求める声を結集し、希望するすべての子どもがしょうがいのある・なしにかかわらず地元で学べる「地域合同総合高校」の設置など、子どもの教育への権利と教育の機会均等を保障するための道民運動を一層強化していくことを表明する。
2018年9月4日
北海道教職員組合
2018年度 文科省「全国学力・学習状況調査」の結果公表に対する
北教組声明
2018年8月3日
文科省は7月31日、18年度「全国学力・学習状況調査」の結果を公表した。今年度「調査」は、小学6年・中学3年を対象にして毎年実施の国語、算数・数学に3年ぶりに理科を加えたものである。全国の状況について、「地域差が縮小し、改善傾向にある一方で応用力に課題がある」など例年と何ら変わらない分析を行った。
「悉皆」による「調査」は今年度で11回目となったが、この間、各都道府県教委は順位の変動に一喜一憂し、その結果、序列化や過度な競争に拍車がかかり、学校現場は「学力向上」の名の下で、過去問題のくり返しやなりふり構わない事前対策と、学習規律の徹底など画一的な「授業改善」を強いられてきた。これにより、地域や子どもの実態に即した創造的な教育が蔑ろにされるなど学びが矮小化され、子どもたちは競争と管理の中で劣等感を植えつけられ学ぶ意欲を削がれるなど本質的な学びを阻害されてきた。さらに、他県では点数のとれない子どもを排除するなど、子どもの尊厳を傷つけられる事態まで惹起し、断じて容認できない。
しかし、「調査」実施の是非や検証は行われず、表面的・短絡的な寸評に毎年約50億円が費やされ、今年度は3年ぶりの理科の実施とともに「夏期休業期間等も活用した教育指導の一層の改善・充実を図る」として、公表時期が例年の8月末から約1カ月前倒しされた。超勤・多忙化が常態化している中で、さらに「夏休み中の結果分析と対策の構築」「休み明けからの改善方策の実施」を求めることは、学校現場を更に追い詰めるものである。
道教委も同日、文科省の公表に追随し「平成30年度 全国学力・学習状況調査の結果のポイント」を公表した。その中で、「中学校国語Aと中学校理科で全国平均正答率を上回り、他の教科では全国平均に達していないものの、小学校国語A 、中学校数学Bで差が縮まっている」「小学校・中学校共に正答数の少ない児童生徒の割合が減少した」など改善の傾向が見られるとしてとりくみの成果を強調し、「授業改善と望ましい生活習慣の確立に向けた取組を更に進める」とした。さらには、「教員の指導力強化などで効果を上げている学校の実践を周辺校にも広め、道内全体の底上げにつなげる」などとした。
しかし、こうした道教委のすすめる「授業改善」「指導力強化」などは、子ども・地域の実態を一切顧みない画一的な手法の押しつけであり、子どもの思いや願いを置き去りにした独善的な授業・指導に陥りかねないものである。今回の調査結果において、教員が「褒める指導をよく行った」という割合が大きく伸びたのに対し、子どもが「良いところを認めてくれている」と回答した割合が減少するなど相互の認識の乖離が浮き彫りになった。目の前の子どもに寄り添わない管理統制された指導の押しつけは、子どもたちが楽しく学ぶことに結びつかないことは明らかである。
学校現場では「点数」を上げるために、「学習規律」や統一的な授業方法の押しつけ、膨大な宿題、放課後や長期休業中の補習の強制、習熟度別指導の強要、過剰な授業時数確保など子どもたちを追い詰める方策ばかりが優先されている。また、教職員は「チャレンジテスト」実施・採点・報告、「調査」実施直後の解答用紙コピー・自校採点などに奔走させられ、教材研究や授業準備の時間が奪われるなど超勤・多忙化に拍車をかけ、本末転倒の状況に疲弊しきっている。
道教委は、「全国学力調査」「調査結果の公表」や、それにもとづく「学力向上策」の押しつけを即刻中止し、各学校の自主的・創造的な教育活動を尊重するとともに、「子どもの貧困」解消・「教育格差」是正、さらに「過労死レベル」に達している教職員の勤務実態を解消するための業務削減と定数改善、「給特法」廃止をはじめとした法改正など、本来なすべき勤務条件・教育条件整備に徹するべきである。
北教組は、「わかる授業・たのしい学校」「差別・選別の学校から共生・共学の学校」をめざし、憲法・「
47教育基本法」・「
子どもの権利条約」の理念にもとづく「ゆたかな教育」の実現のため、一人ひとりの子どもによりそう教育実践を積み重ねるとともに、教育を市民の手にとりもどすための広範な道民運動をすすめていくことを表明する。
2018年8月3日
北海道教職員組合
第121回 中央委員会
中央執行委員長あいさつ
2018年7月2日
今、YouTube などで、「大迫半端ないって」という動画が話題になっているのをご存知でしょうか。ワールドカップで活躍中の大迫選手が高校の時、試合で負けた対戦相手の選手や監督が悔しがりながらも、「半端ないって」と、大迫選手のプレーを讃える姿は清々しく、評判になったものです。
一方で、日大アメフト部の選手一人に責任を負わせる監督やコーチ、大学のあり方と比較し、批判する声も大きく取り上げられています。
さて、安倍政権の運営はどうでしょうか。森友・加計学園疑惑やイラク日報・セクハラ問題など、国会や国民を愚弄する違法行為が繰り返されています。「公文書」の改ざんや隠ぺい、破棄、虚偽答弁など、官僚個人の責任に転嫁し、政権の責任は頬っ被りして、延命を図る党利党略の姿勢は、「半端なく」姑息で、断じて許されません。
こうした中で、安倍首相は、「9条に自衛隊を明記する」憲法改悪に邁進しています。「自衛隊の明記で何も変わらない」としていますが、これは明らかに「集団的自衛権の全面行使」につなげ、海外での軍事行動を可能とする「国防軍化」をねらう詭弁です。改憲と「戦争する国」づくりに向けた動きは、朝鮮半島での平和に向けた対話の流れにも背を向けるものです。
今変えるべきは、行政が私物され、憲法が定めた民主主義や基本的人権、そして平和や自由・平等など人類共通の価値を蔑ろにしてきた政治です。
平和憲法を守り、民主主義を回復するため、安倍政治を終結させ、政治を国民の側に取り戻さなければなりません。
今、国会では「働き方改革」の名を騙った「法案」が、衆議院で強行採決され、国会を延長する中で参議院でも強行されようとしています。過労死認定基準にあたる残業を認める上限規制をはじめ、一部専門職を労働時間規制から完全に除外し、残業代をゼロにする「高度プロフェッショナル制度」など、企業を優遇し、働く者の権利を奪う「政府案」は廃案しかありません。
「高プロ」同様、私たち教職員の「勤務」も、労基法を除外し、時間外・休日勤務手当・割増賃金も支払わないとした「給特法」の規定のもとで、無定量・無制限の「タダ働き」を強いられてきました。私たちはこの1年間、「連合総研」の調査を契機に、全国的な運動を展開した結果、中教審での議論に漕ぎつけたことは大きな運動の成果です。何としても今次審議を、「給特法」の廃止・見直しと、これにもとづく勤務条件改善に向けた交渉・協議を実現する場とさせなければなりません。北教組は弁護団と協議し、日教組や政党への意見反映をすすめてきました。北海道の運動を起点に、抜本的な勤務条件・教育条件改善を勝ち取るため、引き続き広範な運動を展開しようではありませんか。
一方で、私たちは当面、超勤解消をめざし、「勤務の割り振り変更」による対象業務を拡大させてきましたが、「学力向上」策の押しつけなど業務が増加する中で、必ずしも活用できない現場実態に置かれています。引き続き道教委交渉を強化し、現場の要求に沿う回復を措置させていかなければなりません。
今、一人ひとりの子どもの要求にもとづき「人格の完成」をめざす教育内容よりも、国に都合の良いものを「学習指導要領」と「全国学力調査」によって定着させ、規範意識や愛国心など一方的な価値観を押しつける道徳教育が徹底されようとしています。
こうした政府主導の「政策」は、子どもたちを追いつめ、「いじめ、不登校、ひきこもり」が過去最多となるなど、苦悩を一層深刻化させています。
私たちはこれまで、子どもたちの悩みや叫びに寄り添い、子どもの権利を尊重し、管理主義や体罰を排するなど、「子どもの権利条約」の定着と実践を基盤に、「学校を変える運動」をすすめてきました。しかし、競争と管理の政策が強化される中で、必ずしも学校で実践され定着してきたとは言えません。
改めて、「子どもの権利条約」が、子ども自身をその権利を行使する主体と認める「子ども観」に立つことを確認しあい、学校のあらゆる具体的な場面に、子どもの権利と参画を保障する実践の強化が必要です。学校を、子どもたちが夢や希望をもって学び、他者との関係性を身につけ、自らが主権者意識を自覚して、社会を変えていこうとする意思が生み出されるところに変えていこうではありませんか。
北教組がめざす、教職員の生活と権利を守り、子どもの側に立つ教育を実現するためには、組合の存在と力が必要です。そのことを若い教職員の皆さんに訴え加入をすすめていくことが喫緊の課題です。組織拡大センターや青年委員会、昨年からスタートした「全道臨時教職員の会」のとりくみによって、加入に向けた成果が徐々に表れています。7月から始まるサマースクールや教研活動、日常実践を通して、若い教職員が自ら主体的に北教組の運動に自信と確信をもって参画し、組織強化・拡大を図っていく運動の展開が必要です。
2018年度の運動課題の重点は、第1に、改憲発議を断じて許さず、憲法を守り、民主主義を取り戻す道民運動を強化すること、第2に、「給特法」改廃・定数改善など抜本的な勤務・教育条件改善をすすめること、第3に、改訂「学習指導要領」に対峙し人権や民主主義を根づかせる実践を強化すること、第4に、こうしたすべてのとりくみを若い教職員の加入拡大につなげることです。
今年5月に逝去された絵本作家の「加古里子」さんは、18歳初選挙の2016年に「こどものとうひょう おとなのせんきょ」という絵本を復刊させました。たくさんの子どもが遊ぶ広場を舞台に、「『民主主義』は多数決ではなく、少数でも優れた考えや案を、狭い利害や自己中心的になりやすい多数派が学び、反省する、最も大切な『民主主義の真髄』を取り戻したいとの願いで書いた」とあとがきに記しています。
今、安倍政権のもと、民主主義を履き違えた数の暴力が幾度も繰り返される中で、強いものがどこまでも強くなり、弱いものが守られるどころか虐げられている社会状況がつくり出されてしまいました。私たちは、こうした状況に対し、民主主義の理念が息づく社会をつくるため、子どもたちと学びあい、職場の仲間や保護者・住民など身近な人々と語り、連帯して闘わなければなりません。
2018年7月2日
道教委 2019年度「公立高等学校配置計画案」および「公立特別支援学校配置計画案」に対する北教組声明
2018年6月6日
道教委は6月5日、2019年度から3年間の「公立高等学校配置計画案」および2019年度「公立特別支援学校配置計画案」を公表した。特に21年度については、3月に新たに策定した「これからの高校づくりに関する指針」を口実に、大規模な再編統合など機械的間口削減を示したものである。
「公立高校配置計画案」は、新たに公表した21年度では、①南幌を募集停止とする、②女満別(道立全日制)と東藻琴(町立定時制)を再編統合し、1学級の新設校(町立総合学科)を設置する、③滝川など16校で計17学級の減とする、④苫小牧工業の定時制課程を学科再編し1学級減とする一方で、地域の中卒者増を勘案し、札幌真栄で1学級増とするとした。また、19年度については、①夕張、松前を地域連携特例校とする、②私立江陵(4学級)と道立幕別(1学級)を再編統合し3学級の新設校を設置する、20年度については、①釧路工業は電子機械科を1学級減じ、深川東など5校は1学級減じ学科転換する、②岩内の地域産業ビジネス科(現事務情報科)に学科転換し単位制を導入する、などとした。これらは、今後3年間で1校の募集停止をはじめ再編・統合、学科転換などによって53校で54学級減を強行するものであり、中卒者数減を口実にした機械的な間口削減で断じて容認できない。
私立江陵と道立幕別、女満別と東藻琴の再編統合は地域の要望とされたが、そもそも機械的削減を続ける「配置計画」にもとづく統廃合によって小規模校を抱える自治体が追い込まれ、存続に向けてやむを得ず判断したものである。一方で、蘭越、虻田、苫前商業、常呂、阿寒、置戸の6校については、再編整備の要件に該当するものの「所在市町村をはじめとした地域における、高校の教育機能の維持向上にむけた具体的取組とその効果を勘案し、再編整備を留保する」とした。また、今年度の第2次募集後に1学級相当の欠員が生じ学級減となった長沼など15校の19年度の学級数についても昨年度同様に、9月の計画決定時に公表するとした。これらは、いずれも当該地域に高校存続への努力を求め、ことさら子どもや保護者に不安を与えるものである。また、「新たな高校教育に関する指針」にもとづく「配置計画」が、3年前から再編整備を予告することによって、地域が自助努力を求められ再編を要望せざるを得ないよう追い込まれた結果である。
こうした「公立高等学校配置計画」によって、今後一層高校は減少し地域の疲弊・衰退につながることは明らかである。また、子ども・保護者や地域の高校存続を求める声を顧みず、希望するすべての子どもたちに高校教育を保障する責務を放棄し、教育の機会均等を阻害する道教委の姿勢は断じて容認できない。
「公立特別支援学校配置計画案」は、19年度に高等支援学校(職業学科設置校)において2学級減とし、知的しょうがい47校において3学級19人の定員増など全しょうがい児学校61校で4学級17人の定員増とした。20年度も学級増を計画するなど分離・別学を継続する姿勢を示している。18年度の特別支援学校入学者数は、中卒者が859人の減にもかかわらず1,268人と昨年度同数に上った。このように、「分けることは差別につながる」とする「国連障害者権利条約」の理念に反し、文科省・道教委のすすめる「特別支援教育」によって分離・別学を一層すすめる姿勢は容認できない。道教委は、しょうがいのある子どもたちの地元の普通高校への入学や進級・卒業に向けた「合理的配慮」を行うことが急務である。
北教組は引き続き、「新指針」とそれにもとづく「配置計画案」が、子ども・保護者や地域住民の高校存続を求める声を無視するものであることから、道教委に対し撤回・再考を求めるとともに、受験競争の激化や高校の差別・序列化を加速させる学区拡大・再編統合、エリート校の設置、学校裁量問題等に反対していく。そのため、どの地域に暮らしていてもしょうがいのある・なしにかかわらず希望するすべての子どもが地元で学べる「地域合同総合高校」の設置など、子どもの教育への権利と教育の機会均等を保障するための道民運動を一層強化していく。
2018年6月6日
北海道教職員組合
道教委「これからの高校づくりに
関する指針」に対する声明
2018年3月29日
道教委は3月28日、「これからの高校づくりに関する指針」を公表しました。
この「指針」は、「地域キャンパス校」(「地域連携特例校」と改称)の再編基準を10人未満に緩和するなどの変更を行ったものの、現行「新たな高校教育に関する指針(2006)」同様に、財政論に依拠した機械的な間口削減・統廃合をすすめようとする姿勢は何ら変わっていません。
さらには、学校間格差・受験競争激化の要因となっている通学区などについても改めず、遠距離通学費等補助制度の拡充も行わないなど、子ども・保護者や地域の願いを受け止めたものとなっていません。
これに対して北教組は、平和で民主的な社会を担う主権者教育をめざして、以下の抗議声明を発表しました。
道教委は3月28日、「これからの高校づくりに関する指針」(以下、「新指針」)を公表した。これは2016年12月から北海道教育推進会議高等学校専門部会において検討し、昨年9月20日の「素案」、本年3月19日の「案」を経て決定したものである。
「新指針」は、「地域とつながる高校づくり」として、①多様なタイプの高校づくりなどに関して「活力と魅力のある高校づくり」、②職業学科の在り方などに関して「経済社会の発展に寄与する人材を育む高校づくり」、③地域キャンパス校の在り方などに関して「地域とつながる高校づくり」の3つの視点を掲げている。しかし、その内実は、現行「新たな高校教育に関する指針(2006)」と同様、中学校卒業者数の減少などを口実に、「1学年4~8学級を望ましい学校規模(適正規模)」とし、また、1学年3学級以下の学校を対象に詳細な取扱いを設定するなど、財政論に依拠した機械的な学科再編・統廃合をすすめようとするもので、子ども・保護者や地域の願いを受け止めたものとはなってない。
現行「指針」からの主な変更点は、①「地域キャンパス校」を「地域連携特例校」と改称し、再編基準については現行の入学者20人未満から10人未満に緩和する(入学者が2年連続10人未満の場合は再編整備)、②農業、水産、看護と福祉の学科についても「地域連携特例校」と同様の再編基準とする、③定時制課程についても、5月1日現在の第1学年の在籍者が10人未満となり、その後も増が見込まれない場合は再編整備とする、④農業科、水産科の道外からの推薦入学枠拡大について検討する、⑤基礎的・基本的な知識・技能の定着を図る「新たな特色ある高校」の導入について検討する、などである。
他方、①学校間格差・受験競争激化の要因となっている通学区は改めず、現行19学区を継続する、②スーパーエリート養成教育の一層強化となる「理数科、体育科及び外国語科に関する学科」などを導入する、③「高等学校生徒遠距離通学費等補助制度」の拡充は行わない、④教育活動・内容への不当な介入が懸念される「コミュニティ・スクール」を導入する、など政府・財界が求める「グローバル化や情報化の進展などの社会の急速な変化に対応する人材育成」をすすめる姿勢は何ら変わっておらず、きわめて問題がある。
また、現行「指針」と同様に、高校存続に向けて地域・学校に対して「具体的取組とその効果」を求める道教委の姿勢は、後期中等教育の保障を自治体の努力の問題へとすり替え、自らの責務を放棄するものである。さらには、さまざまな事情を抱える子どもたちの貴重な学びの場である定時制高校についても再編整備の対象としたことは、教育の機会均等の確保の理念に反する行為であり、断じて容認できない。
その一方で、北教組の要求や子ども・保護者や地域の願いを受け止め、「地域連携特例校」の再編基準を緩和した上で、「地域連携特例校」間や「地域連携協力校」以外の高校との連携をすすめるとした。私たちは、これを足がかりに地域に高校を存続させ、「
地域合同総合高校」の実現へとつなげていかなければならい。
北教組は引き続き、子ども・保護者や地域住民の高校存続を求める声を結集し、道教委に対して根本的な問題が何ら改善されていない「新指針」の撤回・再考を求めるとともに、どの地域に暮らしていても希望するすべての子どもがしょうがいのある・なしにかかわらず地元で学べる「地域合同総合高校」の設置など、子どもの教育への権利と教育の機会均等を保障するための道民運動を一層強化していく。
2018年3月29日
北海道教職員組合
道教委「学校における働き方改革 北海道アクション・プラン(案)」に
対する声明
2018年2月16日
道教委は2月14日、「学校における働き方改革 北海道アクション・プラン(案)」を公表し、その中で2020年度末までの3年間で、過労死レベルに相当する「1週間当たりの勤務時間が60時間を超える教員を全校種でゼロにする」とする目標を掲げました。しかし、具体的な方策や必要な予算措置などは示されず、過酷な現場実態を改善するものとなっていません。
以下、「アクション・プラン(案)」に対する北教組声明を発表します。
道教委は2月14日、2020年度末までの3年間で「1週間当たりの勤務時間が60時間(過労死ライン相当)を超える教員を全校種でゼロにする」とする目標を掲げた「学校における働き方改革 北海道アクション・プラン(案)」を教育委員会において公表するとともに、北教組に提示した。
その内容は、2020年度末までに道内のすべての学校において、①部活動休養日については、毎週1日以上、月1日以上の土日など年間73日設定する、②学校閉庁日は、8月15日前後の3日と年末年始の全道一斉とあわせて9日設定する、③月2回以上の定時退勤日の徹底に努める、④スクール・サポートスタッフを含めた専門スタッフを配置する、⑤主幹教諭の配置など学校運営体制の充実を図るなど、「働き方改革」を行うため、業務改善の方向性を示し市町村教委の取組を促すとするものである。
しかし、これらは、努力目標にとどまっているばかりか、実現に向けた具体的な方策や必要な予算措置は何ら示されておらず、全く現場の過酷な超勤実態に対する解消策とはなり得ない内容になっている。
また、昨年12月の中教審「中間まとめ」と文科省「緊急対策」を踏襲し、教職員の「意識改革」に力点を置き、更なる授業時数増となる改悪「学習指導要領」や「学力向上策」の押しつけ廃止などの教育施策の転換や超勤の元凶となっている「
給特法」の見直し、教職員定数増などの抜本的な改善策に一切踏み込んでいない。さらには、「働き方改革」を口実に、文科省に追随した「チーム学校」などの施策をすすめようと企図しており、むしろ超勤の助長が懸念されるきわめて問題のあるものとなっている。
道教委は、具体的なとりくみとして、「本来担うべき業務に専念できる環境の整備」「部活動指導にかかわる負担の軽減」「勤務時間を意識した働き方の推進と学校運営体制の充実」「教育委員会による学校サポート体制の充実」の4つのとりくみの柱を示した。しかし、①「専門スタッフ等の配置促進」「ICTを活用した教材の共有化」「校務支援システム導入促進」「コミュニティー・スクールの推進」など、現場の要求と乖離し、効果が全く見込めないものばかりを列挙している、②スクール・サポート・スタッフなどの専門スタッフの配置・派遣では、職務上の位置づけや職務内容・予算・配置規模などについて全く言及されていない、③「部活動休養日」では、目標をスポーツ庁が示した「週2日」を下回る「週1日以上、月1日以上の土日、学校閉庁日9日の年間73日」にとどめるだけでなく、完全定着に向けた現場への拘束力などの方策がない、④「意識改革の促進」に終始するとともに、学校事務職員への業務の転嫁や文科省「チーム学校」体制の強化など協力・協働体制を阻害するものとなっている、⑤「学校閉庁日」については、服務上の取り扱いについて休暇や校外研修とせず「年休・夏季休暇・振替等」にとどめ、9日のうち6日はそもそも休日である年末年始とし、膨大な超勤の回復措置からほど遠い、などいずれも現場の要求を受け止めたものとなっていない。
以上のように、「案」は数値目標を掲げているものの、総じてその達成に向けた現実の課題と解決に向けた有効な手立てなどの核心を欠くものとなっており、きわめて具体性・実効性・拘束力に乏しいと言わざるを得ない。
北教組は、引き続き「給特法」の見直しや教職員定数改善などの抜本的な解消策を求める「教職員の長時間労働是正キャンペーン」の運動を強化するとともに、道教委に対して、現場教職員の切実な要求を受け止めた実効ある超勤解消策の策定を求めていく。
2018年2月16日
北海道教職員組合