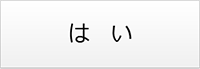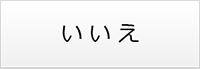中教審「新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のための学校における働き方改革に関する総合的な方策について(中間まとめ)」に対する北教組見解
2017年12月22日
中央教育審議会「学校における働き方改革特別部会」は教職員の超勤・多忙化の解消に向けて9回の審議を重ね、22日「中間まとめ」を中教審へ答申しました。
この内容は、私たちの要請や各界から選出された委員の審議から、過酷な勤務実態の要因や課題について一定明らかにしているものの、抜本的な解決策には踏み込んでおらず、問題点も多々あります。私たち北教組は、今後出される「最終報告」とその後の文科省の動向に対し、「
給特法」の見直しなど抜本的なものとさせるよう引き続きとりくんでいきます。
以下、「中間まとめ」に対する北教組見解を発表します。
中教審「学校における働き方改革特別部会」は12月22日、「学校における働き方改革に関する総合的な方策について(中間まとめ)」を公表した。
これは、4月に公表した「教員勤務実態調査集計(速報値)」において、過労死レベルに相当する月80時間超の残業に相当する教員が、小学校33.5%、中学校57.6%に達していることが明らかとなったことから、文科省が「学校が教員の長時間勤務に支えられている状況には限界がある」として中教審に改善策の検討を諮問し、これを受け「中教審」が「特別部会」を設置して論議を重ね中間報告を行ったものである。
「中間まとめ」は、「10年前と比較して全ての職種において勤務時間が増加している」主たる要因として、「授業や部活動等の業務の時間が増加した」「持ち授業時数を減らすという観点で教職員定数の改善が十分でなかった」「給特法の存在も相まって、勤務時間を管理する意識が管理職や市町村教委において希薄だった」などとし、「国や地方公共団体において、制度的な障壁の除去や学校環境の整備など抜本的な方策や取組を講ずる」としている。
しかし、その内実は、「新学習要領の着実な実施」「日本型学校教育の良さを維持」を前提に「学校教育の質的転換を図る」として、教職員定数改善や改悪学習指導要領による授業時数増、「給特法」の見直しなど、根幹をなす制度の改善に踏み込むことなく、学校・教員の業務内容を学校事務職員や専門スタッフ、外部人材等に転嫁しようとするもので、抜本的な方策となっていない。教職員が異常な超勤実態を強いられることとなった要因は、労基法を骨抜きにする「給特法」の下、新たな教育施策を次々と加えて教職員に負担を積み重ね続けてきたことにある。
「中間まとめ」は、①学校・教師が担う業務の明確化・適正化、②学校の組織運営体制の在り方、③勤務時に関する意識改革と制度面の検討、④「学校における働き方改革」の実現に向けた環境整備の4つ柱で方策をまとめている。その中で、これまでの我々の要求などにもとづき課題は明確になっているものの、解決の方向性・方途は現場実態と乖離していると言わざるを得ず、具体策や財政措置も盛り込まれていないなどきわめて問題である。
第一に、「学校及び教師が担う業務の明確化・適正化」については、①「学校以外が担うべき業務」(登下校に関する対応、放課後・夜間の見回りや補導時の対応など)、②「学校の業務だが、必ずしも教師が担う必要の無い業務」(調査・統計への回答、休み時間の対応、校内清掃、部活動など)、③「教師の業務だが、負担軽減が可能な業務」(給食時の対応、授業準備、評価や成績処理など)に分類し、「中心となって担うべき主体を学校・教師以外の主体に積極的に移行していく」としている。これらは、教員の本務以外の業務の軽減をめざすとしているものの、地域ボランティア、学校事務職員、地域ボランティア・部活動指導員などの外部人材、サポートスタッフ、専門スタッフ(スクールカウンセラー、スクールワーカー)などに担わせるものとなっている。これらは現在学校において職務内容や位置づけが不明確で人材配置や財源の目途が立っていないものが多く、教職員と連携・意思疎通を図る上での課題もあり、一方的な導入は新たな問題を生じさせるものとなりかねない。
また、学校事務職員に教員が担ってきた業務を転嫁しようとすることは、「事務をつかさどる」と法改正された「主体的な学校運営への参画」の趣旨に反するだけでなく、勤務実態を何ら考慮せず一方的に負担を押しつけるものである。
第二に、「学校の組織運営体制の在り方の見直し」については、「鍋ぶた型」の組織を見直すとして、主幹教諭等の配置を促進し、校長、副校長、教頭、主任、主幹教諭、指導教諭などによる組織マネジメントを重視するとしている。しかし、上意下達の体制強化は、教職員を差別・分断して協力・協働体制を阻害するもので、むしろ多忙化を助長させるものである。
第三に、「勤務時間の在り方に関する意識改革と制度面の検討」では、いくら働いても一切時間外勤務手当・割増手当を支払わないことを定め無制限・無定量の超勤の元凶となっている「給特法」見直し議論に踏み込んでいない。また、管理職による勤務時間管理の徹底と適正な勤務時間設定の論議に終始するとともに、超勤を教職員の働き方に関する意識改革の問題に矮小化し、教育現場に問題を転嫁するもので、政府の「働き方改革実行計画」の枠内で勤務時間の「上限の目安を含むガイドライン」検討を求めるにとどまっている。
勤務時間把握については、「ICTの活用やタイムカード」が示されている。校長は教職員の勤務時間を正確に把握すべきであるが、これらは持ち帰り残業を含む正確な勤務時間把握とはなり得ないばかりか、実態にもとづき実効ある超勤解消策に結びつけるものとしなければ何ら意味がない。また、長期休業中に「学校閉庁日」設定を求めているが、教職員の勤務態様については校外研修や特別休暇を保障しなければ、年休の強制となる恐れがある。さらには、保護者からの連絡に対する「留守番電話設置やメールによる連絡対応等の整備」は、学校外での業務負担の増加を招くなど何ら超勤解消に資するものではない。
第四に、「『学校における働き方改革』の実現に向けた環境整備」については、超勤解消をめざすとしているが、「チーム学校」の理念を実現するとして「共同学校事務体制の強化」「コミュニティースクールの導入」「統合型校務支援システムの導入」などにより、文科省による管理強化の施策を後押しするものとなっている。
以上のことから北教組は、引き続き文科省・道教委に対して授業時数増やゆとりのない教育課程、過密な日課など、子どもたちからゆとりを奪い学校現場に超勤・多忙化を強いる「学習指導要領」体制、「点数学力向上策」の押しつけなどの教育政策の転換を求めるとともに、「持ち授業時間数削減」に向けた「教職員定数改善」や現場実態と大きく乖離している「給特法・条例」の抜本的な見直し、長期休業期間中の自主的・創造的な校外研修の保障などを求め全力でとりくんでいく。
以 上
北海道教職員組合
2017年度 道教委「全国学力・学習状況調査 北海道版結果報告書」に
対する北教組声明
2017年11月28日
道教委は11月27日、17年度「
全国学力・学習状況調査北海道版結果報告書」を公表しました。
道教委は、この「報告書」において、子どもに対して「授業」「学習習慣」「生活習慣」の観点で、教職員に対して「指導方法」「家庭学習」「カリキュラムマネジメント」「小中連携・地域の人材活用」などの観点で全国や他県とレーダーチャートを比較して新たな課題をつくり出し、現場に「更なる授業改善」と「望ましい生活習慣の確立」に向けたとりくみを強要しようとしています。これは、本来の「学び」とは乖離した政策により、子どもたちを一層「学び」から遠ざけるものです。
北教組は、道教委の表層的かつ恣意的な分析を批判するとともに、道教委自らが本来行わなければならない超勤解消対策や教育条件整備などを放置していることに抗議の意を示し、一人ひとりの子どもに寄り添った教育実践をすすめていくことを表明する、以下の声明を発表しました。
道教委は11月27日、2017年度「
全国学力・学習状況調査北海道版結果報告書」(以下「報告書」)を公表した。今回の報告では、小中各1校しかない自治体を含む174市町村の自治体が結果公表に同意している。これは、道教委が各市町村教委に対して執拗に「結果公表」を求め続けてきた結果であり、一層序列化を加速させるものであり、断じて容認できない。
「報告書」は、「全国の平均正答率との差が小・中学校ともに改善の傾向にある」とした8月の北海道の「調査結果」をもとに、①全国と全道平均正答率の推移、および、管内のばらつき、②学習の指導方法や関心・意欲・態度、③家庭学習の時間と計画性、④小中連携や地域の人材活用、⑤下位層(全国の下位25%)に含まれる子どもの割合、などを示し、全国と全道・管内、都市部とその他の市町村、全道と他県、との比較に終始している。
子どもに対して「授業」「学習習慣」「生活習慣」の観点で、教職員に対して「指導方法」「家庭学習」「カリキュラムマネジメント」「小中連携・地域の人材活用」などの観点で全国や他県とレーダーチャートで比較している。これらをもとに「今後の改善の方向性」として、①授業の見通しと振り返る活動を位置づける、②主体的・対話的で深い学びの視点による学習指導に取り組む、③学習習慣や生活習慣の確立のため、学校と家庭、地域と連携して進める、④小中連携、一貫教育を積極的に進める、⑤全国学力・学習状況調査等を活用した検証改善サイクルの確立に取り組む、などの課題を生み出し、現場に「更なる授業改善」と「望ましい生活習慣の確立」に向けたとりくみを求めるものとなっている。
道教委の分析では、全国平均が上位である福井県の「家庭学習」のとりくみや、秋田県の「授業の見通しと振り返る活動」がすすんでいることをとりあげ、単に北海道より上位になっていることをもとに、北海道の課題として「家庭学習」と「授業の見通しと振り返る活動」の両方の改善を求める姿勢は極めて短絡的で恣意的と言わざるを得ない。
そもそも、道教委「報告」の視点そのものが、「貧困と格差」の拡大・固定化など子どもの実態や社会状況について何ら分析しておらず、子どものゆたかな学びの保障や教育の機会均等の確保という本来の目的すら希薄になっている。
「学力調査」開始以降、道教委は、教育課程、内容、方法等に不当に介入し、全道すべての学校に画一的な「学力向上策」を強制するとともに、「報告書」等において自らの「施策」を正当化することを繰り返してきた。これは、子どもの多様性や教職員の専門性・主体性・創造性を無視して教育をマニュアル化するもので、子ども・教職員の管理統制強化をすすめ、これまでの北海道における地域に根差したゆたかな教育を破壊するものである。子ども一人ひとりの「学び」は、ゆとりある期間の中で見守り、支えていくべきもので、「過去問題」や「放課後学習」など「点数学力」の押しつけによって培われるものではない。
今道教委がすべきことは、すべての子どもにゆたかな教育を保障するため、押しつけの「学力向上策」を止め、①経済格差がもたらした子どもの「貧困」を解消すること、②子どもの多様な個性を生かした「学び合い」を可能とする少人数学級を推進すること、③教職員定数を改善すること、④教育課程の弾力化や学校現場の裁量権を保障し、超勤・多忙化を解消し、教職員が子どもと向き合う時間を十分に確保すること、など教育条件の整備・拡充こそが急務である。
私たちは、今後も「学力調査・結果公表」に断固反対し、子どもたちの「学び」を矮小化する「点数学力」偏重の「教育施策」の撤回を強く求めるとともに、憲法・「
47教育基本法」・「
子どもの権利条約」の理念にもとづく「ゆたかな教育」の実現のため、一人ひとりの子どもに寄り添う教育実践を積み重ね、教育を市民の手にとりもどすための広範な道民運動をすすめていくことを表明する。
2017年11月28日
北海道教職員組合
道教委「これからの高校づくりに
関する指針(素案)」に対する声明
2017年9月13日
道教委は9月11日、道教委文教委員会に「これからの高校づくりに関する指針(素案)」を報告しました。 この「指針(素案)」は、これまで「 公立高等学校配置計画」を作成する基準としてきた現行の「新たな高校教育に関する指針(2006)」から、「地域キャンパス校」(「地域連携特例校」と改称)の再編基準を10人未満に緩和するなどの変更点を行ったものの、これまでの「指針」を検証・総括せず財政論に依拠した機械的な間口削減・統廃合をすすめようとする基本的な姿勢は何ら変わっていません。これに対して北教組は、以下の抗議声明を発表しました。
道教委は9月11日、道議会文教委員会に「これからの高校づくりに関する指針(素案)」を報告した。
その内容は、昨年10月に公表した「『新たな高校教育に関する指針』検討報告書」にもとづき、「高校づくりの3つの視点」として、①多様なタイプの高校づくりなどに関わり「活力と魅力のある高校づくり」、②職業学科の在り方などに関わり「経済社会の発展に寄与する人材を育む高校づくり」、③地域キャンパス校の在り方などに関わり「地域とつながる高校づくり」を掲げた。
また現行の「新たな高校教育に関する指針(2006)」(以下「指針」)からの主な変更点として、①「地域キャンパス校」を「地域連携特例校」と改称し、再編基準については現行の入学者20人未満から10人未満に緩和する、ただし、入学者が2年連続10人未満の場合は再編整備とする、②1次産業や医療 ・福祉分野を担う人材育成に力を入れるため、農業、水産、看護と福祉の学科についても「地域連携特例校」と同様の再編基準とする、③定時制課程においても入学者が2年連続10人未満の場合は、再編整備をすすめる、④農業科や水産科の道外からの推薦入学枠拡大について検討する、⑤基礎的 ・基本的な知識 ・技能の確実な定着を図るため「新たな特色ある高校」の導入について検討する、などとした。
しかし、これまでの「指針」同様に「生徒の興味・関心、進路希望等の多様化、中学校卒業者数の減少」などを口実として、「1学年4~8学級を望ましい学校規模」とした「適正規模」を一方的に定め、財政論に依拠した機械的な学科再編・統廃合をすすめようとする基本的な姿勢は何ら変わっていない。また、①学校間格差 ・受験競争激化の要因となっている通学区を改めず、現行19学区を継続する、②「理数科、体育科及び外国語科に関する学科」など、スーパーエリート養成教育を一層強化する、③「高等学校生徒遠距離通学費等補助制度」の拡充は行わない、④教育委員会等による教育への不当な介入が懸念される「コミュニティ ・スクール」導入する、など「グローバル化や情報化の進展などの社会の急速な変化に対応する人材育成」を基本に据え、国家・財界が求める教育をすすめるもので極めて問題がある。これらは、子どもたちを早期に差別・選別し、平和で民主的な社会を担う主権者の育成に向け人格の完成をめざす「47教育基本法」の理念を蔑ろにするもので断じて容認できない。
北教組は、現行「指針」「配置計画」により、財政論に依拠した機械的な間口削減・統廃合と差別・選別の教育がすすめられ、子どもたちの学ぶ権利が侵害されるとともに、「貧困と格差」に一層拍車がかかり北海道の地域を疲弊させてきたことなどから「指針」の撤回・再考を訴えてきた。また、地域キャンパス校の再編基準見直しやしょうがいのある・なしにかかわらず希望するすべての子どもたちが地元の高校へ通うことのできる「地域合同総合高校」の設置など、北海道の地域性を活かしたゆたかな後期中等教育の実現を求めてきた。
「本素案」では、①「地域連携特例校」の再編基準を現行の20人未満から10人未満へと緩和する、②「地域連携特例校」間や「地域連携協力校」以外の高校との連携をすすめる、などが盛り込まれた。これは、北教組の要求や子ども・保護者や地域の願いを受け止めたものであり、私たちは、これらを足がかりに「地域合同総合高校」の実現へとつなげていかなければならい。
道教委は、今後行われる北海道教育推進会議高等学校専門部会、パブリックコメントや道内19会場での「意見を聞く会」などを実施した上で、「これからの高校づくりに関する指針」を策定し、2021年度以降の配置計画から適用(実施可能な施策は2018年度から実施)するとしている。
私たちは引き続き、子ども・保護者や地域住民の高校存続を求める声を結集し、道教委に対して根本的な問題が何ら改善されていない「素案」の撤回・再考を求めるとともに、すべての子どもがしょうがいのある・なしにかかわらず地元で学べる「
地域合同総合高校」の設置など、子どもの教育への権利と教育の機会均等を保障するための道民運動を一層強化していく。
2017年9月13日
北海道教職員組合
道教委「教育職員の時間外勤務等に係る実態調査」結果に対する
北教組声明
2017年9月11日
道教委は9月11日、「教育職員の時間外勤務等に係る実態調査」の第1期の結果を公表しました(第1期2016年11月7日~20日、第2期12月5日~18日)。
今回の道教委の結果公表は、学校の繁忙期にあたる12月に行った第2期の結果が示されていないこと、道教委が2011年に行った調査結果との比較が一切行われていないこと、など深刻な状況にある現場実態を十分に反映しておらず、何ら分析もされていないなど多くの問題を含んでいます。
今回公表した第1期は、学校現場において最も超勤が少ない時期とされる11月であるにもかかわらず、週60時間を超える労働時間(過労死ライン)となっている教員の割合が、小学校23.4%、中学校46.9%、高校35.7%、しょうがい児学校5.2%となっていることが明らかになりました。
北教組は、この道教委「教育職員の時間外勤務等に係る実態調査」結果公表に対し、以下の声明を発表しました。
道教委は9月11日、「教育職員の時間外勤務等に係る実態調査」の第1期の結果を公表した(第1期2016年11月7日~20日、第2期12月5日~18日)。
個人調査では、第1期において、週60時間を超える労働時間となっている教員の割合が、小学校23.4%、中学校教諭の46.9%、高校35.7%、しょうがい児学校5.2%となっていることが明らかになった。週60時間の労働は、月に換算すると80時間の超過勤務となり、厚労省の示す過労死認定ラインを超えるもので、労基法に反する違法な勤務実態が改めて明らかになった。教員1日あたりの勤務時間については、持ち帰り残業も含めて平均で、小学校10時間28分(08年度道教委調査10時間52分)、中学校10時間46分(同11時間21分)、高校10時間08分(同11時間06分)となった。また、勤務不要日における教員1日あたりの学内勤務時間(持ち帰り時間は含まない)は平均で、小学校25分(08年度調査28分)、中学校2時間53分(2時間01分)、高校2時間12分(1時間34分)と増加傾向にあることが明らかになった。
個人の意識調査では、「忙しさや負担感を解消するために必要なこと」の項目で多くの教職員が現場に必要なのは、「業務の見直し(廃止を含む)」「1クラスあたりの子どもの数を減らし、教員を増員し担当する授業数を減らす」とした。また、学校調査では、「校務を複数人で担当する」「校内会議の精選・会議の短縮」「学校行事の精選」「変形労働時間制や週休日の振替等の制度の活用」など道教委が掲げる業務の平準化・効率化・精選について、ほぼすべての学校で実施されているとした。
今回の道教委の結果公表は、学校の繁忙期にあたる12月に行った第2期の結果が示されていないこと、道教委が2011年に行った調査結果との比較が一切行われていないこと、など深刻な状況にある現場実態を十分に反映しておらず、何ら分析もされていないなど多くの問題を含むものである。何より調査実施から約10ヶ月経過してもなお道教委として何ら具体的な方策を示していないことは、現場で日々子どもたちのために過酷な勤務を行っている全道の教職員に対して、きわめて不誠実な姿勢と言わざるを得ない。
第1期の期間は、2006年の文科省委託「教員勤務実態調査」において、長期休業期間中を除いて残業が最も少ない時期にあたる。道教委は、結果報告において「時間外勤務がいずれも減少した」としているが、むしろ最も超勤が少ない11月の時期にあっても平均して1日2時間を超える残業となっている過酷な状況が明らかになったとみるべきである。
道教委はこの間、超勤解消に向け、学校行事等における「勤務時間の割振り等に関する要項」などにより超勤の実質的な回復を図る制度改善を行ってきたが、今回の学校調査の結果からも明らかなように、現場におけるとりくみだけでは既に限界に達している。このことは、調査結果・分析を待つまでもなく、教員の過密な日課を強いられている1日の勤務実態から、膨大な業務を到底勤務時間内に終えることができない構造の問題として以前から指摘されてきた。
現在、文科省・中教審は、「新学習指導要領を着実に実施」するために、チーム学校の推進や専門職員の配置などにより教職員の超勤を是正しようとしている。一方で、次期「学習指導要領」においては、小学校英語の導入により、小学校高学年で週29時間の授業となるなど、更なる授業時数増となる。今必要なのは、学校に過密な日課を強いている「学習指導要領」や全国学テとその結果にもとづく画一的な「学力向上策」の押しつけなどから、現場を解放することにある。教職員定数を増やし教員一人あたりの授業時数を削減することや部活動の社会教育へ移行することなど業務削減なしに抜本的な改善などありえない。また、4%の教職調整額によって現場に無制限・無定量の超勤を強いる温床となっている「給特法・条例」の見直しも必至である。「
給特法」の制定時に確認された、教職員が超勤を行った場合には回復措置を措置すること、長期休業期間中の教職員の自主的な研修を保障すること、などが形骸化された結果、現在の過労死ラインに匹敵する超勤実態となった経過を見過ごしてはならない。
道教委は、世論が教職員の働き方改革に注視している今こそ、過酷な現場実態にある教職員の悲鳴を真摯に受け止め、「点数学力向上策」の押しつけなど管理統制の教育政策を転換すべきである。
その上で、国・文科省に対して教員定数改善と授業時数削減、「給特法」の見直しなど抜本的な対策を求めるべきである。道教委に対して、国に追随するのではなく、まず自らが直ちに現場実態にもとづく実効ある超勤削減策を講ずるよう強く求める。
北教組は、教職員が子どもたちにゆとりをもって接し、寄り添うことができるよう、教職員の超勤解消など教育条件・勤務条件の改善に、引き続き全力でとりくんでいく。
2017年9月11日
北海道教職員組合
道教委2018年度「公立高等学校配置計画」および「公立特別支援学校配置計画」に対する声明
2017年9月6日
道教委は9月6日、2018年度から3年間の「
公立高等学校配置計画」および2018年度「公立特別支援学校配置計画」を決定しました。
北教組は、①「公立高等学校配置計画」が、北教組要請行動や地域別検討協議会における地域住民・保護者や教育関係団体からの高校の存続を求める声を蔑ろにし、これまでにない大規模な学級減を強行するものであること、②「公立特別支援学校配置計画」が、道内中卒者数は年々減少しているにもかかわらず、文科省・道教委が分離・別学を一層すすめているために、特別支援学校に入学する子どもは増え続けていることなどから、以下の抗議声明を発表しました。
道教委は9月5日、2018年度から3年間の「公立高等学校配置計画」および2018年度「公立特別支援学校配置計画」を決定した。
「
公立高等学校配置計画」の内容は、18年度について、①17年度において欠員が生じ1学級減とした12校のうち、余市紅志など5校は1学級復活、残る美唄尚栄など7校は1学級減のままとする、②上ノ国、雄武を
地域キャンパス校へ移行する、③滝川西を1学級減じ商業科を学科転換する、④小樽商業と小樽工業、留萌と留萌千望をそれぞれ統合し新設校とし単位制を導入する、など9校で10学級削減するとした。また、19年度について、①幕別町の私立江陵(普通科2、福祉科1)の募集停止に伴い、幕別を普通科3学級(2学級増)とする、②函館西と函館稜北を統合した新設校と、稚内の普通科と商業科に単位制をそれぞれ導入する、③札幌東豊など6校で6学級を削減する、とした。さらに、20年度について、①当初1学級減としていた岩見沢農業の削減を見送り、市立岩見沢緑陵を1学級減とする、②市立札幌清田を2学級減とし単位制を導入する、など24校で25学級減とした。
これらは、道教委「新たな高校教育に関する指針」(以下「指針」)にもとづき、3年間で再編・統合による1学級減(6校を募集停止とし3校を新設)を含め、40校で42学級減となる大規模削減を強行するもので、断じて容認できない。
今回の「決定」において道教委は、地域や子どもの実態を踏まえた高校のあり方について十分な分析・検討をすることなく、地域の学校を存続させるための生徒数確保の責任を学校 ・地域に転嫁するとともに、中卒者の増減に依拠し学科を無視した数合わせの機械的な間口削減に終始した。これらは、北教組要請行動や地域別検討協議会における地域住民・保護者をはじめとする教育関係団体からの高校の存続を求める声を蔑ろにするものである。
一方、「公立特別支援学校配置計画」では、18年度について、①高等支援学校の職業学科設置校を中心に学級減とする、②札幌伏見支援学校普通科と星置養護学校ほしみ高等学園を1学級増とした。また、19年度について、①函館稜北高校の空き教室を活用して新設校を開校し、五稜郭支援学校の2学級とあわせて4学級を確保する、②釧路鶴野支援学校の増築整備により3学級増とした。さらに20年度について、道北圏で3学級相当の間口の確保を検討する、など新たに今後の見通しを示し、差別・選別の施策をより一層すすめようとしている。
文科省・道教委「特別支援教育」が導入されたこの10年間で、道内中卒者数は年々減少しているにもかかわらず、特別支援学校に入学する子どもは増え続け、13校の特別支援学校が増設されるなど、分離 ・別学が一層すすめられている。道教委は、「分けることは差別につながる」とした「国連障害者権利条約」の理念にもとづき、しょうがいのある子どもたちの願いを受け止め、地元の普通高校への入学・進級・卒業に向け、すべての学校において「合理的配慮」が十分に保障されるよう早急に教育条件整備をすすめるべきである。
私たちはこれまで、道教委「指針」「配置計画」により、子どもたちの遠距離通学と保護者の経済的負担が増加し、「貧困と格差」が一層拡大するとともに、地域を疲弊させることから、「指針」の撤回 ・再考を求めてきた。中学卒業者数の減少期だからこそ道教委は、一人ひとりの子どもたちの要求に応え地域に高校を存続させ、希望するすべての子どもたちにゆたかな後期中等教育を保障すべきである。
私たちは引き続き、子ども・保護者・地域住民の高校存続を求める声を結集し、すべての子どもがしょうがいのある・なしにかかわらず地元で学べる「
地域合同総合高校」の設置など、子どもの教育への権利と教育の機会均等を保障するための道民運動を一層強化していくことを表明する。
2017年9月6日
北海道教職員組合
2017年度文科省「学力・学習状況調査」の結果公表に対する声明
2017年8月29日
文科省は8月28日、開始以来10回目となる17年度「 全国学力・学習状況調査」の結果を公表しました。 北教組は、この「全国学力・学習状況調査」の結果公表が、文科省・道教委「学力向上施策」の継続と自らの「施策」を正当化し、教育内容・方法に詳細に介入するとともに、一定の価値観を押し付け、国家のための人づくりを一層すすめようとしたものであることから、以下の抗議声明を発表しました。
文科省は8月28日、開始以来10回目となる17年度「
全国学力・学習状況調査」の結果を公表した。この中で、全体的に成績の底上げがすすむ一方、基礎的な問題に比べて応用問題に課題があるとするなど、自らの「施策」の継続を前提に実施を正当化するものできわめて問題である。また、今年度初めて政令市別の成績を公表し、同一道府県の地域と比較を行うとともに、序列化や過度な競争を防ぐためとして昨年から平均正答率を整数値で公表するとしたものの、上位県、下位県の差別化は変わらず、市町村教委による結果公表も依然として行われるなど、経済 ・社会の現状に対する分析を行うことなく、一層序列化や過度な競争を助長するものとなっている。また、「学校質問紙調査」において、「主体的 ・対話的で深い学びの実践」「カリキュラム ・マネジメントに関する取組」などの改悪「学習指導要領」にもとづく調査項目で、子どもや学校を評価するなど、教育内容 ・方法に詳細に介入し、一定の価値観を押しつけ、国家のための人づくりを一層すすめようとしている。
道教委も同日、「平成29年度全国学力・学習状況調査の結果のポイントについて~北海道(公立)における調査結果~」を公表した。その内容は、①すべての教科で全国平均以上に達していないものの、全国の平均正答率との差が、小学校国語A ・B、算数A ・B、中学校国語Bの5教科で縮まっている、②正答数の少ない児童生徒の割合が減少した、など「改善の傾向が見られる」と成果を強調した。これらは、「授業改善と望ましい生活習慣」「継続的な検証改善サイクル」の確立にとりくんだ成果であるとしている。また、経年変化を分析する必要があるとして、独自に小数点第1位まで算出し、微細な差にこだわり市町村間の競争を煽る姿勢は、数字ありきで全く本質を見失っている。
道教委は、これまで「全国平均以上にする」として「点数学力」偏重の教育を強要してきた。その結果、今学校は「過去問題・プリント」や「テストの結果」をあげるための宿題・家庭学習など、道教委の「教育施策」に追われ、断片的な知識・技能の「詰め込み」と「訓練」などによって、「学び」は矮小化させられている。また、道教委「学力向上施策」により決められたことを「こなす」ことや「そろえる」ことが重視され、創造的な活動が制限されており、子どもたちは、一層序列化、分断・孤立化させられる中で、居場所がなく「疲弊」し「学び」から逃避するとともに、不登校・自死など「苦悩」を顕在化させている。
道教委は「調査結果」を受け、「北海道で育つすべての子どもたちが自らの可能性を最大限に伸ばし、主体的に学習にとりくむ態度など、確かな学力を確実に身につけることができるよう、学校、家庭、地域、行政が一体となった学力向上の取組を進める」としている。しかし、「授業改善」「検証改善サイクル」の名のもとにすすめる「学力向上施策」は、子ども ・教職員を道教委の「施策」に従わせるもので、「主体的に取り組む態度」の育成とは矛盾するものである。道教委は自らの「施策」が破綻していることを認めるべきである。生きることと直結する子どもたちの学力は、学校や地域で課題を見つけ、解決しようとする活動の中で、仲間と協働することによって培われるものである。
「北海道子どもの生活実態調査」でも明らかとなったように、道内の子どもの「貧困」「格差」が拡大する中、子どもを取りまく社会的・経済的状況などについて何ら分析することなく、調査を正当化し自らに都合の良い「施策」を強化することは断じて容認できるものではない。
道教委は、「全国学力調査」「調査結果の公表」や、それにもとづく「学力向上施策」の押しつけを即刻中止し、各学校現場の教育活動を尊重するとともに、「子どもの貧困」解消、「教育格差」是正、さらに「過労死レベル」に達している教職員の勤務実態を解消するための定数改善など、本来なすべき教育条件整備に徹するべきである。
私たちは今後も、「わかる授業・たのしい学校」「差別・選別の学校から共生・共学の学校」をめざし、憲法・「
47教育基本法」・「
子どもの権利条約」の理念にもとづく「ゆたかな教育」の実現のため、一人ひとりの子どもによりそう教育実践を積み重ねるとともに、教育を市民の手にとりもどすための広範な道民運動をすすめていくことを表明する。
2017年8月29日
北海道教職員組合
道教委2018年度「公立高等学校配置計画案」および「公立特別支援学校配置計画案」撤回・再考を求める
北教組声明
2017年6月6日
道教委は6月6日、2018年度から3年間の「
公立高等学校配置計画案」および2018年度「公立特別支援学校配置計画案」を公表しました。
北教組は、この「配置計画」が、子ども・地域の実態・要望を踏まえず、中卒者数減に応じた機械的な間口削減にすぎないこと、18年度に上ノ国高校、雄武高校を
地域キャンパス校とする、一部の高校の学校数の決定を9月に先送りするなどは、いたずらに子どもたちや学校現場に混乱をもたらすものであることなどの問題点を指摘し、「配置計画案」の撤回・再考を求める以下の抗議声明を発表しました。
道教委は6月6日、2018年度から3年間の「公立高等学校配置計画案」および2018年度「公立特別支援学校配置計画案」を公表した。
「
公立高等学校配置計画案」の18、19年度分の変更内容は、①18年度に上ノ国、雄武を
地域キャンパス校とする、②第2次募集後の入学者に1学級相当の欠員が生じ学級減を行った美唄尚栄ほか11校の2018年度の学級数を中卒者数の状況や生徒の進路動向等を精査し、計画決定時に公表する、③19年度に幕別町の私立江陵が募集停止になること等を考慮し、幕別を2学級増とする、④19年度に函館西と函館稜北の再編による新設校と稚内の普通科と商業科に単位制を導入する、⑤19年度に1学級減としていた小学科について、室蘭工業は情報技術科、北見商業は商業科とする、としている。また20年度については、①岩見沢農業など23校を1学級減とする、②市立札幌清田を2学級減とし単位制を導入するなど、24校で25学級減とした。これらは、3年間で再編・統合による1学級減(6校を募集停止とし3校を新設)、学科転換を含め40校で42学級減を強行するなど、中卒者数減に応じた機械的な間口削減にすぎない。
18年度からの地域キャンパス校の導入は、準備期間が1年に満たず、教育課程の編成や人的配置などセンター校との十分な連携や調整が困難である。とりわけ雄武のセンター校となる紋別はすでに興部のセンター校でもあり、2校のキャンパス校との調整が必要となるなど、学校現場にさらなる混乱と多忙を強いるものであることから十分な教育条件整備が必要である。
また、今年度第2次募集後に1学級相当の欠員が生じ学級減となった美唄尚栄ほか11校の2018年度の学級数については、中卒者数の状況や生徒の進路動向等を精査し、9月の計画決定時に公表するとした。これは、いつの段階の「進路動向等」を精査し決定するのか不明確であり、ことさら子どもや保護者に不安を与えるものである。さらに、21~24年度までの見通しとして、「定時制課程について第1学年の在籍者が10人未満となり、その後も生徒数の増が見込まれない場合は、再編整備の検討が必要」と初めて言及した。
このように今回の「配置計画案」は、子ども・保護者や地域の高校存続を求める声を顧みず、道教委が財政論に依拠した「機械的な間口削減」を一層すすめ、希望するすべての子どもたちに高校教育を保障する責務を放棄し、教育の機会均等を阻害するものである。
「公立特別支援学校配置計画案」では、18年度は高等支援学校の職業学科設置校を中心に学級減としたが、19年度、20年度に再び学級増を計画するなど分離・別学を継続する姿勢を示している。文科省・道教委のすすめる「特別支援教育」は、分離・別学を一層すすめ、16年度に特別支援学校で学ぶ子どもの数は、5,672人と15年度より144人も増えている。道教委は、「分けることは差別につながる」とした「国連障害者権利条約」の理念を生かし、しょうがいのある子どもたちの地元の普通高校への入学や進級・卒業に向けた「合理的配慮」を行うことが急務である。
道教委「新たな高校教育に関する指針」にもとづく「配置計画」によりこの10年間で、道内の高校は40校減少し232校となり、高校のない市町村数は50となった。子どもたちは遠距離通学を強いられ保護者は経済的負担が増大するなど多くの問題が生じている。「指針」は地域を疲弊させ、子どもと保護者の「貧困と格差」を拡大 ・助長させている。4月に実施された「地域別検討協議会」においても地域の高校の存続を求める意見が出された。
私たちは改めて、子ども・保護者や地域住民の高校存続を求める声を結集するとりくみをすすめ、道教委に対して「指針」の抜本的見直しと、それにもとづく「配置計画案」の撤回・再考を求めるとともに財政論にもとづく機械的削減、受験競争の激化や高校の差別・序列化をさらに加速させている石狩一学区などの学区拡大や学校裁量問題、エリート校の設置等に反対し、30人以下学級などの少人数学級や「遠距離通学費等補助制度」の年限撤廃・適用拡大など、子どもの学習権と教育の機会均等を保障するための道民運動を一層強化していく。
2017年6月6日
北海道教職員組合
「次期学習指導要領の改訂案」に
対する北教組声明
2017年2月24日
文科省は2月14日、「小中学校の学習指導要領」と「幼稚園教育要領」の改訂案を公表した。その内容は、①グローバル化の進展や人工知能(AI)の進化などの社会の変化に対応するとして、国家や企業が求める「人材育成」をすすめる、②「前文」を新設し、改悪「教育基本法」にもとづく「愛国心」などの国の特定の価値観を押しつける、③「小学校英語」の教科化や「プログラミング教育」の必修化など授業内容や方法・評価にまで介入し、時数を大幅に増加させ教育現場にさらなる負担を強いる、など教育の目的を「人格の完成」から「国家のための教育」に変質させる戦後最悪・最大規模の「改訂案」となっている。
「改訂案」では、小学校5・6年の「英語」を教科化、3・4年に「外国語活動」を前倒しし、そのため授業時数を年35時間(週1時間)増やした。
これにより、「週28時間が限度」とされてきた時数が、小学校4年生以上で「週29時間相当」となった。増加した分の時数確保については、給食時間の後や下校時間前などの短時間学習や土曜授業の活用などを例示し、学校で工夫して捻出するよう求めた。これらは、教育課程を一層過密化させるばかりでなく、すべての子どもにわかる授業とゆとりを保障する「学校5日制」の理念を蔑ろにするものであり、断じて容認できない。さらには、小学校段階では母国語による理解力 ・思考力 ・表現力の向上を最優先させるべきであり、早期の「外国語」指導による弊害が危惧される。
先行して改悪された「特別の教科 道徳」は、「検定教科書」を導入し、国が定めた22項目の「徳目」を教え込むとともに、「評価」を実施することを明記した。
これらは、子どもたちに一方的な道徳観・価値観・家族観を押しつけるなど「従順な国民づくり」を企図するものである。また、「評価」は子どもの内心に踏み込むもので許されない。「道徳教育」については、全領域を通して人権教育をすすめ、「科学的認識」と「自主的判断力」を育み、平和と民主主義社会を担う主権者としての「人格の完成」へと結びつけていくべきである。
小・中学校の社会科において、「政府見解」を一方的に押しつけ、北方領土に加え、竹島や尖閣諸島を「固有の領土」と明記し、中国や韓国の立場について「並べて教えることは想定していない」とした。「領土」については、史実を正確に伝え、「領土」を取り巻く複雑な歴史や国際的な状況も合わせて学習することが重要である。
これまで私たちは、目の前の子どもの実態に合わせて、教育の目標や内容・指導方法を教育現場で創り上げてきた。今回の改悪では、これまで各教科の内容が中心だったものに詳細な目標を加え、教科の学習を通して「どのような資質・能力を目指すのか」を前面に打ち出すとともに、その達成に向けて学習内容から指導方法や評価のあり方にまで細かく言及した。その上で、現場に対して「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善を求めた。これらは、「カリキュラム・マネジメント」と称して現場の裁量や教職員の主体性・工夫を奪い、教育の画一化を招くとともに、「評価」のための授業となり、子どもたちのゆたかな学びを阻害するものである。
学校現場では、「学習指導要領」の画一的な押しつけや「点数学力向上施策」と「競争と管理」の教育の下、子どもたちは学ぶ楽しさや意欲を奪われ、学びから逃避し、いじめ・不登校など様々な形で苦悩を表出している。今回の「改訂案」は、新たな「格差」を生み出し、子どもたちを一層追い詰めるものである。
「連合総研」の調査では、労働時間が週60時間以上だった教員の割合は小学校72.9%、中学校86.9%に達しており、教職員が超勤多忙化の常態化に苦しんでいる実態が明らかになった。「質・量」ともに求める「改訂案」は、教職員から「子どもに寄り添う時間」「教材研究の時間」を奪い、限界を超えている現場を一層苦しめるものである。教育行政の責務は、教職員がこれ以上疲弊して子どもたちに向かうことのないよう、定数改善や超勤多忙化排除、自主的研修の保障などの教育条件整備を行うことであり、「改訂案」は本末転倒と言えるものである。
文科省は、年度内に「学習指導要領」改訂し、小学校は20年度、中学校は21年度から完全実施するとしている。また、18年度から「小学校外国語」を中心に前倒し実施を目論んでいる。
私たちは、「改訂学習指導要領」をはじめ「学習指導要領」体制を批判し、憲法・「
47教育基本法」・「
子どもの権利条約」の理念に則ったゆたかでゆとりある教育の実践をすすめるため、教育課程の自主編成運動と職場教研体制を強化するとともに、民主教育の確立を求めて道民運動を強力に展開していくことを表明する。
2017年2月24日
北海道教職員組合