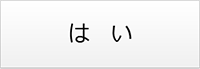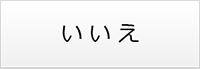2021年度道教委「全国学力・学習状況調査北海道版結果報告書」に
対する北教組声明
2021年11月30日
道教委は11月29日、2021年度「全国学力・学習状況調査北海道版結果報告書」(以下「報告書」)を公表した。「報告書」では、「すべての教科で全国平均に届いていない」「自分の考えをもち、筋道を立てて説明することなどに課題が見られる」「授業以外で勉強する時間が短い」などの傾向を示し、「主体的・対話的で深い学びの視点からの授業改善」「小学校と中学校の連携の強化」「望ましい学習・生活習慣の定着に向けた家庭や地域との連携」などを一層充実させる必要があると言及した。
「全道の状況」についても、依然として、①平均正答率の推移、②各教科領域の平均正答率、③正答数の状況、について全国との数値比較に留まった。また、質問紙調査と教科調査結果をクロス分析し、恣意的に「朝食の摂取状況」「ICT機器の活用状況」などの項目を挙げ、学習・生活習慣の確立やICT機器の活用を促している。さらに、管内および各市町村の状況についても、14管内の平均正答率の順位分布や各市町村の結果分析など、全国・全道平均との差異を強調する分析を行った。その上で、「北海道の学力向上の取組に関する改善の方向性」として、①検証改善サイクルの確立、②授業改善、③小学校と中学校が連携した取組の充実、④望ましい学習習慣の確立、の4項目を掲げ、「改善の方向性」とともに実践事例を示すなどしているが、これらは何ら例年と変わらない分析である。
現在、「いじめ」「不登校」「自殺」が過去最大となるなど、子どもたちの苦しみは増大している。また、厚労省「国民生活基礎調査」(20年7月)では、子どもの貧困率は13.5%と7人に1人の子どもが貧困状態にあり、とりわけひとり親世帯では48.1%と深刻な状態にある。さらに、新型コロナウイルス感染症の影響により所得が減少した世帯も多く、特にひとり親世帯においては貧困に苦しむ家庭が増加し、経済格差は拡大している。
北教組はこれまで、こうした問題の解消に向け就学援助制度・奨学金制度・高校授業料無償化制度など教育予算拡充の声を上げるとともに、子どもたちに寄り添う時間を保障するため超勤・多忙化解消を求めてきた。これに対して道教委は、「全国学テ」の結果をもとに学校と家庭のみに責任を押しつけ、全国・全道平均点との差異を強調して子どもたち・学校間の競争を煽り、序列化に拍車をかけてきた。また、本来学校にある教育課程の編成権に介入し、子ども一人ひとりや各学校の実態を蔑ろにした画一的な「学力向上策」を押しつけ、教職員の超勤・多忙化を加速させてきた。
こうした道教委の姿勢は断じて容認することはできない。今年もこれまでと何ら変わらない観点で調査結果を公表したことは、貧困に苦しみ学びたくても十分に学べない子どもたちの状況を何ら顧みず、全国順位の向上のみをめざす子ども不在の施策と言わざるを得ない。現実の子どもの苦悩に一切向き合うことなく膨大な時間・費用・労力をかけて、変わり映えのしない分析を毎年繰り返す道教委の硬直した姿勢こそが、改善されるべきである。
今、道教委がすべきことは、地域や子どもの実態に即し、ゆたかな教育を保障するため、押しつけの「学力向上策」を直ちに止め、①子どもの多様性を生かした「学び合い」を可能とする少人数学級を実現すること、②教育課程の弾力化や学校の裁量権を保障すること、③教職員の持ち授業時間数を減らすため定数を改善し、子ども一人ひとりとゆとりを持って接することができるようにすること、など教職員の超勤・多忙化解消と教育条件の整備・拡充をすすめることである。
以上のことから、北教組は、「報告書」「結果公表」に断固抗議するとともに「全国学テ」に反対し、子どもたちの「学び」を矮小化する「点数学力」偏重の「教育施策」の撤回を強く求める。
私たちは今後も、憲法・「47教育基本法」・「子どもの権利条約」の理念にもとづく「ゆたかな教育」の実現のため、「主権者への学び」をすべての教育活動の底流とした教育実践を積み重ね、市民とともに教育を子どもたちのもとへとりもどすための広範な道民運動をすすめていくことを表明する。
2021年11月30日
北海道教職員組合
第71次合同教育研究全道集会
アピール
2021年11月11日
北教組・道私教協は、10月29日から10月31日までの3日間、のべ1800人の組合員・保護者・地域住民の参加のもと、第71次合同教育研究全道集会を開催しました。2020年はじめから各地で蔓延した新型コロナウイルス感染症の影響により、昨年度の第70次全道合研は中止を余儀なくされました。今年度第71次については、対面での開催がかなわなかったものの、自主編成運動の歩みを止めてはならないとの思いから、オンライン開催としました。
改訂「学習指導要領」が本格実施となり、文科省は、国家に都合の良い「価値観」や「規律」を強要するとともに、教育内容・方法・評価まで詳細に介入して、政財界の求める「資質・能力」の育成を通した「国家のための人材づくり」をめざしています。また、20年2月末の一斉休校、そして再開後は、学校行事の中止・延期・内容変更など、子どもたちは人との関わりを制約される中、授業は「進度」「授業時数確保」が至上命題となり、さらには「全国学テ」の実施・活用が強要され、子ども主体の学びが阻害されました。さらに、「コロナ禍」においてGIGAスクール構想が前倒し実施となり、中教審はICTの活用による「個別最適な学び」の推進を文科省に答申しました。
教職員もまた、消毒作業や行事・授業内容の再三にわたる練り直しをせざるを得なくなり、これまで常態化していた「過労死レベル」の超勤実態がより深刻化しています。
私たちはこの「コロナ禍」の中で、改めて教育の本質を見つめ直し、子ども同士・子どもと教職員とのふれあいや対話を大切にした、子どもたちに寄り添いつながる教育の重要性を再認識しました。
現在の閉塞した教育の状況を学校から変えるため、北教組は21年1月「『自分らしく』『よりよく生きる』学びのための18の提言」(以下「18の提言」)を発行し、子どもを権利の主体者としてとらえる「主権者への学び」を基底とした教育活動をあらゆる教科・領域で実践することを提起しました。私たちは今次教研において、これまで積み上げてきた「抵抗と創造」の自主編成と、「主権者への学び」をもとにした教育実践について論議を深め、すべての子どもたちに民主教育を保障するとともに、今後の教研の発展に向けて次のことを確認します。
第1に、憲法改悪を断固阻止するため、院内外の統一闘争を構築し、護憲勢力の結集と拡大をめざしてとりくむこと。そのために、組合員一人ひとりが自らの言葉で語る「教育を語る全道対話運動」を通して、「平和憲法を守る」「子どもの貧困・教育格差解消」「教職員の長時間労働是正」を重点課題に、地域住民・保護者との連携を強化すること。
第2に、競争による差別・選別教育をおしすすめる改悪「学習指導要領」やこれにもとづく「学力向上策」「特別の教科 道徳」と対峙し、GIGAスクール構想をはじめとする中教審答申にもとづく教育内容・方法・評価への不当な介入を許さず、「18の提言」をもとに「主権者への学び」を中心とした自主編成運動を推進すること。
第3に、過酷な勤務実態を解消し、子どもと向き合う時間の確保とゆとりある教育活動をすすめるため、教育課程の過密化解消、官制研修の削減・縮小、部活動の社会教育への移行など具体的な業務削減を求めるとともに、「給特法・条例」の廃止・抜本的見直しを求めること。また、道教委に対して「北海道アクション・プラン」の見直しを求めるとともに、やむを得ず行った超勤に対しては、勤務時間の割振り変更により直近に実質的な回復を措置させること。
第4に、憲法・「47教育基本法」・「子どもの権利条約」にもとづく、子どもを主人公とした自主・自律の学校づくりをすすめること。また、「子どもの権利条例」の早期制定に向け、保護者・地域住民と連携し、連合・平和運動フォーラム・民主教育をすすめる道民連合など民主的諸団体との共闘を強め、「日の丸・君が代」強制反対の運動についてねばり強くとりくむこと。
第5に、文科省「特別支援教育」を実態化させず、「分けることは差別である」ことを確認するとともに、共生・共学をすすめること。また、共生社会の実現に向け、国連「障害者の権利条約」や「障害者差別解消法」の理念にもとづき、しょうがい者の社会的障壁を除去する「合理的配慮」をすすめること。
第6に、評価結果を賃金・任用・分限等へと反映させ、学校現場の協力・協働を阻害する「学校職員人事評価制度」については、撤廃を基本に、差別賃金・管理統制強化とさせず、すべての教職員の賃金改善とするよう、各級段階におけるとりくみを強化すること。また、定年引き上げ等に関する制度について、国に遅れることなく学校現場の実態に即した制度にしていくよう道教委に求めていくこと。
第7に、「主任制度」「主幹教諭制度」や「事務主幹制度」「新たなミッション加配」、中教審「特別部会」の「答申」にもとづく教職員の差別・分断、管理強化に反対し、自律的・民主的職場づくりと、主任手当の社会的還元を含め、組織強化・拡大を組織の総力をあげてすすめること。また、「協定書」破棄の実態化を許さず、諸権利定着・拡大、超勤・多忙化解消をはかること。さらに、「教員免許更新制」の早期撤廃に向けたとりくみを強化すること。
第8に、財政論に依拠した道教委「公立高等学校配置計画」の撤回・再考を求め、希望するすべての子どもたちが地元の学校へ通うことができるよう高校を存続させるとともに、「地域合同総合高校」の実現など、受験競争の解消とゆたかな高校教育改革をめざすこと。そのため、保護者・地域住民との連携を強化すること。また、公私間の学費格差解消に向け、私学助成拡充を求めること。
第9に、教育の機会均等を保障するため、「高校授業料無償化」への所得制限および朝鮮学校の無償化適用除外の撤廃、義務教育費国庫負担制度堅持・全額国庫負担を基本に、当面、負担率2分の1復元に向けて全国的な運動を展開すること。また、経済格差による「教育格差」の是正や「子どもの貧困」を解消するとともに「30人以下学級」の早期実現をめざし、当面、「教職員定数標準法」における中学校2・3年、高校への「35人以下学級」の実現や「道独自の少人数学級」の実施拡大、給付型奨学金制度の拡充、「就学援助」の拡大、教育費の保護者負担の解消など、教育予算増額に向けたとりくみを強化すること。
第10に、「生涯健康管理体制」の押しつけに反対し、集団フッ素洗口中止、食物アレルギーに特化した対応の一方的な導入阻止、HPV・日本脳炎などワクチンの定期接種化の中止などを求め、子どものいのちと健康を守るとともに、個人情報保護のとりくみをすすめること。また、特定の健康観の押しつけや差別につながる「全国体力・運動能力調査」の中止・撤回を求めること。
第11に、「女性差別撤廃条約」の理念にもとづき、学校や社会における性差別や性別役割分業の撤廃に向け、とりくみを強化し、女性参画を推進すること。ジェンダー平等に対する攻撃を排し、学校教育のあらゆる場面で「ジェンダーの視点」を取り入れた実践をすすめること。また、LGBTsや民族、外国につながる子どもなど多様性にかかわる人権教育を一層すすめ、すべての人の人権が保障される社会を実現すること。
第12に、未だに収束を見ない「フクシマ」の現状から、「人類と核は共存できない」ことを再確認し、反核・反原発の学習をすすめるとともに、泊・幌延・大間をはじめとしたすべての原子力施設の廃止・建設中止を求め、「核・原発のない社会の実現」に向けてとりくみを強化すること。また、寿都町・神恵内村の高レベル放射性廃棄物最終処分場に関する「文献調査」に反対し、「概要調査」にすすませないとりくみをすすめること。さらに、「被ばく」により、いのちを脅かされている子どもたちの状況の改善を求めるとともに、再生可能エネルギーへの政策転換を求め、自然との共存をめざす教育をすすめること。さらに、辺野古新基地・南西諸島への自衛隊配備阻止のたたかいを沖縄と連帯してすすめること。
私たちは、平和・人権・国民主権など憲法の原則を守り、個人より国家を優先する政府と文科省の政策を厳しく批判・分析し、「自分らしく」「よりよく生きる」教育の創造をめざして、地域・保護者と連帯して、自主編成運動をさらに押しすすめるとともに次世代へ継承することの重要性を再認識しました。
「教え子を再び戦場へ送るな!」の決意を新たにし、憲法改悪に断固反対するとともに「47教育基本法」・「子どもの権利条約」の理念にもとづく「平和を守り真実をつらぬく民主教育の確立」に向けたとりくみを一層前進させていくことを確認し、集会アピールとします。
2021年10月30日、31日
第71次合同教育研究全道集会
道教委2022年度「公立高等学校配置計画」および「公立特別支援学校配置計画」に対する北教組声明
2021年9月8日
道教委は9月7日、22年度から3年間の「公立高等学校配置計画」(以下、「配置計画」)と22年度および23年度以降の見通しを示した「公立特別支援学校配置計画」を公表した。
「公立高等学校配置計画」では、6月の「計画案」通り留辺蘂を23年度で募集停止とし、「計画案」からの変更点として、①24年に学級減を予定していた岩見沢東については、今後の市の検討結果を勘案し、市内再編を含め変更することがある、②22年度に大樹・標茶を1学級増とする、③市立札幌旭丘に設置する新たな学科を数理データサイエンス科とする、④本別、標津は、新たに地域連携特例校を導入する、と変更した。また、21年度入学者選抜後に1学級相当以上の欠員が生じて学級減となった23校のうち、栗山など14校が1学級増となったものの、砂川、札幌南陵、札幌東豊、札幌あすかぜ、北広島西、森、江差、本別、標津の9校は1学級減のままとした。23年度の美幌の未来農業科への転換・学級減、名寄と名寄産業の再編統合・単位制導入などは計画案通りとした。
「公立特別支援学校配置計画」では22年度について、全しょうがい児学校61校で、昨年度より定員が10人減の1,684人とし、「計画案」からの変更点として、22年度に1学級減としていた余市養護学校と北見支援学校、旭川養護学校の3校については学級数維持とした。また、「知的高等支援学校」の配置の見通しでは、23年度に道央圏で2学級相当、24年度は4学級相当の定員の確保を検討していたが、いずれも新設校を設けず、既設校の学級増で対応する見通しを盛り込んだ。
これらは道教委が依然として、「これからの高校づくりに関する指針」(以下、「指針」)にもとづき、子ども・保護者の声を無視した学級減などを機械的にすすめるもので、断じて容認できない。とりわけ留辺蘂の募集停止は、生徒・学校・保護者・地域が連携し、存続に向けとりくんできたにもかかわらず、一方的に「進路動向に変化はみられない」と断じ、地元の声を踏みにじるものである。地方の小規模校を「数」のみをもって募集停止・学級減とすることは、子どもを都市部へ一層流出させ、地域の活力をそぐものである。また、岩見沢東高校の学級減にかかわっては、結果的に道教委が「計画案」によって岩見沢西高校、岩見沢緑陵高校にまで学級減・再編統合の対象を広げて数合わせを行わせようとするものであり、地域に大きな混乱を生じさせるものである。またこの間の、入学者選抜結果による学級減の結論を、「計画」において決定する方法は、進学を考えていた子どもや保護者を翻弄するものである。
文科省・道教委「特別支援教育」は、中卒者数が減少傾向にもかかわらず特別支援学校への入学希望を年々増加させ、22年度も知的障害特別支援学校47校で5学級25人の定員増を計画するなど、分離・別学を一層すすめているものとなっている。道教委は、「分けることは差別につながる」とした「国連障害者権利条約」の理念にもとづき、希望する子どもたちの地元の普通高校への進学を保障するため、すべての学校において「合理的配慮」などの教育条件整備を早急にすすめるべきである。
本「配置計画」は、地域の経済と文化の衰退を招くとともに、遠距離通学者や保護者の経済的負担の増加など、「貧困と格差」を拡大させるもので断じて容認できない。今後も中卒者数の減少が見込まれる中で、広大な北海道の地域性を何ら考慮せず、機械的に削減し続ける「指針」「配置計画」の撤回・再考を求めるとともに、希望するすべての子どもがしょうがいのある・なしにかかわらず地元で学べる「地域合同総合高校」の設置など、子ども一人ひとりの要求に応えるゆたかな後期中等教育を保障するため、道民運動を一層強化していくことを表明する。
2021年9月8日
北海道教職員組合
2021年度 文科省「全国学力・学習状況調査」の結果公表に対する
北教組声明
2021年9月3日
文科省は8月31日、21年度「全国学力・学習状況調査」の結果を公表した。文科省は全国の状況について、「改善の傾向が見られたものがある一方、依然として課題が認められるものがある」などと例年と何ら変わらない分析を行った。文科省は「調査」の目的を「学校における児童生徒への教育指導の充実や学習状況の改善等に役立てる」としているものの、この間、各都道府県教委は学力調査の「目標値」を設定し、「学力向上」の名の下、過去問題のくり返しや事前対策、学習規律の徹底など画一的な「授業改善」を現場に強いている。
道教委も同日、文科省の公表に追随し「全国学力・学習状況調査 調査結果のポイント」を公表した。教育長のコメントでは「すべての教科で全国平均に届いていない状況にある」「誰一人取り残すことのない教育活動の充実に向けた一層の取組が必要である」「コロナ禍においても学びを止めない指導体制を構築しつつ、GIGAスクール構想で整備された1人1台端末などICTを効果的に活用した授業改善などをすすめる」などとした。
道教委がすすめる全国学力調査の実施・結果公表は、学校現場を過度な競争的環境に置くもので、学びの主体となるべき子どもは、蔑ろにされ続けている。また、「学力向上策」として「望ましい生活習慣の確立」を押しつけることで、子どもたちは息苦しさを感じている。こうしたことが要因となって、「いじめ」「不登校」の増加に歯止めがかからない現状を生じさせている。道教委は、「誰一人取り残すことのない教育活動の充実」としているが、これまでの教育施策を振り返り、過去最大の件数となっている「いじめ」「不登校」の解消にとりくむべきである。さらに「調査」の目的が、「全国的な児童生徒の学力や学習状況を把握・分析し、教育施策の成果と課題を検証し、その改善を図る」のであれば、「貧困と格差」が「教育格差」につながっていることを分析し、施策に反映させることを最重要課題としなければならない。しかし、一向にこうした検証・分析は行われず、「ICTを効果的に活用した授業改善」など一方的に画一的な施策の強要に終始している。
今求められるのは、教える側の発想ではなく、子どもの学びを最大限引き出すための子どもの側に立った施策に転換することである。そのために「点数学力の向上」ではなく、学校・子どもの安心・安全を確保し、子どもたちが学びの主体となる環境を整えること、教職員に十分なゆとりをもたせることが急務である。
道教委は、「全国学力調査・結果公表」とそれにもとづく「点数学力向上策」の押しつけを即刻中止し、各学校の自主的・創造的な教育活動と一人ひとりの子どもに寄り添う実践を保障するとともに、教職員をはじめ、保護者・地域の声を真摯に受けとめるべきである。また、「子どもの貧困」解消と「教育格差」是正をすすめ、定数改善や「給特法」の廃止・見直し等、超勤・多忙化解消のための法改正を文科省に求めるなど、本来すべき勤務条件・教育条件整備に徹するべきである。
北教組は今後も、子どものゆたかな学びを阻害する「全国学力調査」に反対し、憲法・「47教育基本法」・「子どもの権利条約」の理念にもとづく「わかる授業・たのしい学校」「差別選別の学校から共生・共学の学校」をめざして、「主権者への学び」を基盤とした教育実践を積み重ねるとともに、教育を市民の手にとりもどすための広範な道民運動をすすめていくことを表明する。
2021年9月3日
北海道教職員組合
第132回 定期大会
委員長あいさつ
2021年7月30日
北教組第132回定期大会に結集いただいた代議員・役員の皆さんに感謝申し上げ、開催にあたって北教組本部を代表して、ご挨拶申し上げます。
まず、感染症対策をはじめ、学校現場おいて、子どもたちのために日々奮闘されている組合員・役員の皆さんに心より敬意を申し上げます。
本定期大会も、感染症が収束していないことから、代議員数等を限定することや、時間を短縮して開催せざるを得ない状況にあります。お集まりいただいた皆さんには、これらの制約を乗り越えることができるような、活発な議論をしていただくよう、まず、お願い申し上げなければなりません。
さて、北教組は、「超勤多忙化解消をはじめとする勤務条件改善」 そして、「自主編成運動による民主教育の確立」を運動の柱として、すべてのとりくみを組織強化・拡大に結合させることを大前提に、具体的な運動の展開において「焦点化・効率化」が必要であるとの意志統一のもと検討をすすめ、本定期大会を迎えることとなりました。
北教組運動の歴史と経過をふり返り、根幹となる方針・理念については残しつつ、焦点化によって活動しやすい組織を再構築し、効率化をはかることによって組合員負担の軽減をすすめ、少数分会で奮闘する組合員にもとりくむことができ、若年層組合員が将来的な展望をもてる、「組合組織づくり」をめざして一致団結していくことが、10年後20年後を見据えた、新たな北教組の運動のあり方であることを全組合員で共有したいと考えています。
「教え子を再び戦場に送らない!」の不滅のスローガンのもと、北海道の教育を担っている組合員とともに、「日の丸・君が代」「学習指導要領」「研修」「主任制度」「職員会議」、いわゆる5項目に対する考え方は堅持するものの、形式にとらわれていたとりくみをスリム化して「誰もがやりがいを実感することができること」「多忙化を極める現場実態に配慮すること」を重点に、本部・支部は現場組合員の実態把握と運動の検証を怠らず、方針転換と安易に誤解されないよう、教育労働者としての自信と誇りを持ち、これまで通り「自律的・民主的な職場づくり」そして「抵抗と創造の自主編成運動」などのとりくみを基本に、試行錯誤しながら、組織強化をしていかなければならないと考えています。
今次、第132回定期大会は、新たな北教組のスタートとして全道の組合員の期待に応えるための重要な位置づけになることから、代議員・役員、本部執行部が議論を深め、意志統一することができ、本定期大会が成功することをお願いして、甚だ簡単でありますが、ご挨拶とさせていただきます。
本日はよろしくお願いいたします。
ともに頑張りましょう。
2021年7月30日
北海道教職員組合
道教委2022年度「公立高等学校配置計画案」および「公立特別支援学校配置計画案」の撤回・再考を求める北教組声明
2021年6月2日
道教委は6月1日、2022年度から3年間の「公立高等学校配置計画案」および2022年度「公立特別支援学校配置計画案」を公表した。
「公立高校配置計画案」は、23年度について①留辺蘂を募集停止する、②美幌を生産環境科学科および地域資源応用科から未来農業科に学科転換し1学級減とする、③名寄及び名寄産業の再編統合による新設校は、普通科4学級、情報技術科1学級とし単位制を導入する、と変更した。新たに公表した24年度については、22~23年度に4校で4学級増(1校は計画決定時に公表)、7校で7学級減とした上で、岩見沢東などを6校で6学級減とした。また、今年度の2次募集後に1学級相当の欠員が生じ学級減となった栗山など全日制23校、定時制1校の学級数は、9月の計画決定時に公表するなどとした。さらに野幌・千歳北陽に導入する新たな特色ある高校の総称を「アンビシャススクール」とした。
これらは、地域の実態を顧みず、「これからの高校づくりに関する指針」にもとづき「1学年4~8学級」を適正規模として中卒者数の減少を口実にした機械的な間口削減と再編統合などによる学級減を強行するとともに、これまで以上に高校の序列化に拍車をかけるものである。留辺蘂の募集停止は、昨年「北見市内の高校配置に関する今後の地域における検討状況等を勘案するため期間を置く」としたものの、計画案では「中卒者数の状況、学校規模、募集定員に対する欠員の状況、地元からの進学率」など数字のみをもとにした機械的な判断で、設置者としての存続責任を放棄するばかりか、高校の特色や地域の学校存続を求める声を考慮しておらず、容認することはできない。また、野幌・千歳北陽に導入する「アンビシャススクール」は、子ども・高校を差別・序列化させかねないもので、「基礎的・基本的な知識・技能の確実な定着や社会的・職業的自立に向け必要な能力や態度の育成に重点を置く」ことは、すべての子ども・保護者の願いであり、そのために必要な教育環境整備を道教委は行うべきである。地域連携特例校については、本別・標津を22年度の募集学級数が1学級の場合に新たに導入するとし、平取・興部・阿寒については「所在市町村をはじめとした地域における、高校の教育機能の維持向上にむけた具体的取組とその効果を勘案」して再編整備を留保するとした。しかしその基準は曖昧で、該当地域は子どもたちのためではなく、道教委に留保を認めてもらうための学校づくりをすすめてしまう危惧がある。
大幅に人口減少・都市部への一極集中がすすむ道内において、こうした機械的な間口削減・再編統合、差別選別を一層すすめる「公立高等学校配置計画」によって、都市部を除く地域は高校が減少し、疲弊・衰退が加速するとともに、子どもの学びが侵害されている。地域の教育機能を維持・向上させることは重要な課題であり、地域の特性や実情を十分に考慮するために「これからの高校づくりに関する指針」を抜本的に見直す必要がある。
「公立特別支援学校配置計画案」は、22年度の進学希望見込数を1,352人とし、定員を全しょうがい児学校61校で1,665人(昨年比8学級29人減)とした。しかし、職業学科を含む知的高等支援学校24校では、定員を904人(昨年比2学級16人増)と増加した。さらに23年度には「道央圏で2学級相当の定員の確保を検討」、24年度には「道央圏で4学級相当の定員の確保を検討」するとしていることから、将来的には、しょうがい児学校の定員増により、一層分離・別学に拍車がかかることは明らかである。これは、文科省・道教委のすすめる「特別支援教育」が「分けることは差別につながる」とする「国連障害者権利条約」の理念に反し、どの子も共に学ぶ「インクルーシブ教育」を阻害していると言わざるを得ない。道教委は、しょうがいのある子どもたちの地元の普通高校への入学および進級・卒業に向けた「合理的配慮」など、教育環境整備を早急に行うべきである。
北教組は、「これからの高校づくりに関する指針」や「配置計画案」が、受験競争の激化や高校の序列化を加速させるとともに、子ども・保護者や地域住民の高校存続を求める声を無視するものであることから、引き続き、道教委に対し撤回・再考を強く求める。また、どの地域に暮らしていてもしょうがいのある・なしにかかわらず希望するすべての子どもが地元で学べる「地域合同総合高校」の理念を生かしたゆたかな高校教育の実現と子どもの教育への権利と教育の機会均等の保障をめざし、「道民運動」を一層強化していく。
2021年6月2日
北海道教職員組合
「改憲手続法」改正案の可決に抗議し、憲法改悪を断固許さない声明
2021年5月11日
本日、きわめて問題のある「改憲手続法」改正案が衆議院を通過した。北教組は、本法案の可決に強く抗議する。今、政治が全力でとりくむべき課題は新型コロナウイルス感染症への対策であり、「改憲手続法」改正ではない。
「改憲手続法」改正案は、一部の課題を検討事項として附則に盛り込む修正が行われたものの、CM・インターネット広告の規制や運動費用の制限がないこと、最低投票率の定めをおかず「有効投票の過半数」で成立すること、改正案の発議について「内容において関連するごと」として一括投票の余地を残していること、などの問題が払拭されてはいない。また、「公選法並び7項目」の内容についても、「期日前投票の弾力的運用」や「繰延投票の告示期間の短縮」など、「投票環境の向上」という法改正の目的に反する事態をもたらすおそれがあり、許されない。
自民党は、新型コロナウイルス感染症拡大に乗じて、私権制限を伴うより強い対策のためには「緊急事態条項」が必要であると喧伝し、改憲論議を加速させようとしている。しかし、新型コロナウイルス感染症対策は、諸外国においても、現行法の範囲内で迅速に対応し、生活補償、休業補償などが実施されている。このことは、「緊急事態条項」に該当する憲法を有する国にあっても同様で、緊急時において様々な規則を細かく定めるのは、国家の基本原理を定める憲法ではなく、個別の法律の役割である。その上、自民党が憲法改正草案で示した「緊急事態条項」は、発動要件が曖昧な上に、国会の関与なしに内閣が法律と同じ効力を持つ政令を出すことができるなど、三権分立・地方自治・基本的人権の保障などの憲法秩序を停止し内閣の独裁を招きかねない内容となっており、他国の「緊急事態条項」や新型コロナウイルス感染症対策とは全く性質が異なるものである。
以上のように、自民党が目論む憲法「改正」は、日本国憲法の「平和主義」「民主主義」「基本的人権の尊重」の基本原理を蔑ろにするもので、断じて容認できるものではない。
私たちは、「改憲手続法」の廃案を求めるとともに、少なくとも問題点の修正を強く求めていく。また、「教え子を再び戦場に送らない」の理念のもと、憲法の平和主義と民主主義を破壊し「戦争をする国づくり」をすすめようとする憲法改悪の動きを決して許さない。引き続き憲法改悪を断固阻止するため、民主的諸団体と連携し、さらに運動を強化していく。
2021年5月11日
北海道教職員組合
第125回 中央委員会
中央執行委員長あいさつ
2021年3月16日
北教組第125回中央委員会に結集いただいた中央委員・役員の皆さんに感謝申し上げ、開催にあたって北教組本部を代表して、ご挨拶申し上げます。
新型コロナウイルス感染症対策をはじめ、学校現場おいて、日々奮闘されている組合員・役員の皆さんに心より敬意を申し上げます。
本日の中央委員会も、感染症の収束が道半ばであることから、対策を講じているとは言え、前回中央委員会同様、ご不便をおかけする形で開催せざるを得ないことに理解をいただいていることにお礼を申し上げなければなりません。
さて、感染症が終息しない中で、「自粛要請」が一人歩きし、「同調圧力」、さらには「自粛警察」といった偏見が幅を利かせる社会のあり方が問題になっていると感じています。
北教組が実施した教育課程実態調査においても、3割近い学校で、新型コロナウイルスの影響により、保健室を利用する子どもが増えたとの報告があり、不安や、学校生活の大きな変化・制約によって子どもたちが大きくストレスを抱え、落ち着きがなくなったり、不安を訴えるようになっている状況が伺えます。
過剰に同調を強いられることによるストレスは、ネットの世界のみならず学校においても、他者へのいじめや攻撃となって歪んだ形で発散されることが心配されます。
現・菅政権の状況をみると、自らを正当化しようとする姿勢が顕著となり、その結果、差別や蔑視・排除を容認する状況が生まれており、安倍政権が掲げた憲法改悪を旗印にするだけではなく、科学的根拠がない「否定」や「すれ違い答弁」、国民の声に耳を傾けず黙らせ、「自助」として経済的な淘汰路線をあからさまに公言し、差別や格差を容認する姿がその本質であると考えます。
同様のことが、教育・学校現場において起きているのではないでしょうか。我々の調査で授業の進度が12月末現在、58%の学校が休校による遅れを取り戻し、さらに、例年より進んでいる学校が14%にもなっているにもかかわらず、教育課程の進捗状況のみに固執し、子どもたちの負担や興味・関心、現状には目を向けず、授業時数確保に躍起となっている実態に差別や格差を容認する姿と重なるものがあります。
さらに、「コロナ禍」において、教育をめぐる様々な問題が顕在化している中、家庭でのIT環境を考慮せずにオンライン授業の推奨や予算を拡充し、一層、教育格差を拡大させようとしていることは極めて問題です。
このような中、1月に発行された「18の提言」は、社会秩序や経済発展など国・企業の都合に適う非科学的な教育制度・内容を優先する施策を批判し、学習指導要領体制を乗り越え、だれもが「排除」されない社会のあり方を再考し、「自分らしく」「よりよく生きる」ためを原点として、教育実践を通して民主的な教育に立ち返るため、編集・発行されたものとなっています。
私たちは、提言を積極的に活用し、学習・実践・総括を通して、いみじくも同時期に出された、中教審答申「子どものあるべき姿」や「個別最適な学び」によって、子どもたちの将来が自己責任論に転嫁されないよう、「学校とは何か」について改めて問い直し、若い教職員とともに自主編成運動の重要性の理解を深め、超勤多忙化解消、「一年単位の変形労働時間制」については一方的導入を許さないとりくみにおいて未組織者に寄り添い、組織強化拡大をすすめていくことが重要です。
各級段階の運動にも、依然として多くの制約が生じることとなっており、例年通りの運動の検証は不十分となっています。一方で、止めることのできない、動き続けなければならない運動も山積しています。
今次、第125回中央委員会は、7月開催予定の第132回定期大会につながる極めて重要な位置づけになるものです。先程、申し上げた自主編成運動、超勤多忙化解消、当面、「一年単位の変形労働時間制」の一方的導入を許さないとりくみ、組織強化拡大なとどとともに、22年4月からの本部負担支部専従、中央執行委員の削減など直面する重要課題に対して、運動の焦点化・効率化を前提にこれまでの北教組運動を再構築するための分岐点をどう迎えるかが、本日の中央委員会の課題であり、中央委員・役員、本部執行部が議論を深め、一致団結することが極めて重要となります。
最後に、本中央委員会が全道津々浦々の1,500余りの分会で奮闘している組合員の期待に応えるものにして、成功させることをお願いして、ご挨拶とさせていただきます。
本日はよろしくお願いいたします。
ともに頑張りましょう。
2021年3月16日