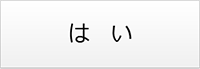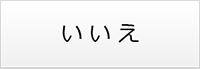道教委2021年度「公立高等学校配置計画」および「公立特別支援学校配置計画」に対する北教組声明
2020年9月8日
道教委は9月7日、21年度から3年間の「公立高等学校配置計画」と21年度および22年度以降の見通しを示した「公立特別支援学校配置計画」を公表した。
「公立高校配置計画」は、21~22年度に14校で15学級減(昨年度決定)を行うこととした上で、6月の「計画案」から①美幌は、新型コロナウイルス感染症対策の影響に伴う地域の検討状況等を勘案し、23年度に学級減とする学科を21年度に決定すること、②23年度に募集停止とされていた留辺蘂は、北見市内の高校配置に関する今後の地域における検討状況等を勘案するための期間を置くことから21年度に決定すること、に変更した。また、名寄・名寄産業をそれぞれ募集停止とし再編により新設校を設置すると変更した。一方で、小樽潮陵、室蘭栄、市立函館、旭川北、旭川南、旭川永嶺の6校は6月の「計画案」通り、23年度に1学級ずつの減とした。また、入学者選抜後に1学級相当以上の欠員が生じ学級減となった21校については、長沼など9校が1学級復活したものの、札幌東豊、札幌あすかぜ、野幌、千歳北陽、浦河、斜里、音更、清水、大樹、白糠、標茶、伊達緑丘の12校は1学級減のままとした。
「公立特別支援学校配置計画」は21年度について、全しょうがい児学校61校で、昨年度より定員が60人減の1,694人としたものの、6月の「計画案」で1学級減としていた札幌伏見支援学校と平取養護学校の普通科を学級数維持と変更した。さらに、知的障害特別支援学校高等部の配置の見通しでは、22年度に「道央で4学級相当の定員の確保を検討」、23年度には「道央圏で2学級相当の定員の確保を検討」するとした。
道教委は、「1学年4~8学級」を適正規模とした「これからの高校づくりに関する指針」(以下、「指針」)にもとづき、中卒者数の減少により生徒数を確保できないことをもって「教育機能の低下」として再編統合をすすめてきた。これは子どもたちへの高校教育の保障を放棄することで、断じて容認できない。23年度に計画されていた「留辺蘂の募集停止の決定を21年度に延期」としたが、単に中卒者数や地元からの進学者数による数合わせにこだわるのではなく、子ども・保護者の願いを最大限に尊重するとともに、地域事情を十分に考慮し、学校を存続させるべきである。20年度入学者選抜後に欠員が生じ学級減とした21校のうち、12校は1学級減のままとなった。16年までは、6月の「計画案」公表時に判断していたが、「計画」決定時に判断することとなってからは、進学を考えていた子どもや保護者にとって、進路変更の検討を余儀なくされるなど、大きな混乱を生じさせるものである。また、野幌、千歳北陽を新たな特色ある高校として、「基礎的・基本的な知識・技能の確実な定着や社会的・職業的自立に向け必要な能力や態度を育成する学校に位置づける」としたが、こうした子どもや保護者の願いである学びの充実は、一部の学校に特化して行うものではなく、すべての学校における課題である。文科省・道教委「特別支援教育」の名のもとにすすめる差別・選別の施策は、中卒者数が減少傾向にもかかわらず特別支援学校への入学希望を年々増加、とりわけ「知的障害」の進学者数の割合を増加させ、分離・別学を一層すすめているものとなっている。また、「分けることは差別につながる」とした「国連障害者権利条約」の理念にもとづき、希望する子どもたちの地元の普通高校への進学を保障するため、すべての学校において「合理的配慮」などの教育条件整備を早急にすすめることが、果たすべき最大の役割である。
本「配置計画」は、地域の経済と文化の衰退を招くとともに、遠距離通学者や保護者の経済的負担の増加など、「貧困と格差」を拡大させるもので断じて容認できない。私たちは引き続き、子ども・保護者・地域住民の高校存続を求める声を結集し、「指針」「配置計画」の撤回・再考を求めるとともに、希望するすべての子どもがしょうがいのある・なしにかかわらず地元で学べる「地域合同総合高校」の設置など、一人ひとりの子どもたちの要求に応えるゆたかな後期中等教育を保障するため、道民運動を一層強化していくことを表明する。
2020年9月8日
北海道教職員組合
第124回 中央委員会
中央執行委員長あいさつ
2020年9月4日
北教組第124回中央委員会に結集いただいた中央委員・役員の皆さんに感謝申し上げ、開催にあたって北教組本部を代表して、ご挨拶申し上げます。
新型コロナウイルス感染症による一斉休校措置、学校再開後の対応など学校現場の組合員の多くのご苦労に心より敬意を申し上げます。この件に関して、先日の教育長着任交渉において、教育長からの現場で奮闘する組合員へ「感染症対応への感謝」ということで「子どもたちのへの尽力」「教職員自身の健康への留意」への謝意が述べられたところです。
本日、感染症の収束が見通せないことから、対策を講じたとは言え、ご不便をおかけする形で本中央委員会開催にご理解をいただきたいことに皆さんにお礼を申しあげなければなりません。
感染症対策によって、各級段階の運動にも多くの制約が生じることとなっております。従来の活動ができないことにより、職場で教育実践の悩みを相談できない、当然の権利を要求して確保できない教職員が一人でもいるとすれば、その思いに寄り添うとともに、私たち組合がこの課題にどのように機能すべきかを改めて考え直なければならないと考えています。
こうした中で、私たち北教組は、職場での活動を基本とした組織強化拡大・自主編成運動などを提起しています。収束後の運動の足掛かりとなる成果として、日々の教育実践と同様、試行錯誤をくり返しながら子どもたちと一緒に歩んでいくように、仲間と対話により信頼関係が深まり、これにもとづく分会活動によって、北教組運動の土台が強化されることが必要であります。
第201回通常国会においては、感染症への対応をもりこんだ総額32兆円もの第2次補正予算が成立しました。第1次補正予算に加えると総額は、約58兆円となります。
第2次補正予算においては、教職員を追加配置するとして310億円が計上されていますが、未だに「人を集められない」との理由で予算の完全な執行ができない状況となっており、「新しい生活様式」への対応などが付加されている教職員は一層疲弊しています。
検温・健康観察のための始業前時間外勤務、子どもの下校後終業時刻を過ぎての校舎・教室の消毒業務・トイレ清掃、翌日の授業準備、家庭連絡、事務処理等。「ビルド&ビルド」にビルドされたことにより、さらに過酷な勤務実態になっている、との声は北海道のみならず全国各地の現状となっています。
こうした状況にも拘らず、第2次補正予算の全体における文科省事業予算の割合は1%にも達していません。全国的な教員不足が指摘され、教育崩壊も危惧されていますが、「給特法7条が改正され、給特法の廃止・抜本的見直し」に向けて動き出している中で、教育委員会や管理職は教職員の使命感や献身性を求めてはなりませんし、そのような姿勢が現実にあることは大きな問題点です。私たちは、教職員の安全と健康の確保のため、処遇改善や大胆な定数改善等の教育条件整備の予算を拡充すること求め続けなければなりません。
国難突破と気勢を上げ、危機を煽って改憲項目に「緊急事態条項」を持ち出し、平和を蔑ろにする。そして、教育予算を抑制する中で経済効率と市場原理によって子どもたちを追いつめている政治姿勢を断じて容認してはなりません。
子どもたちが平和と平等な社会で暮らすことから遠ざけ、弱肉強食、かつ自己責任一辺倒の状況に追い込み、コロナ禍で一層深刻とさせた今の社会のあり方を変えていくことが、民主教育確立の根幹であることを私たち教育労働者は再認識し、「対話運動」や「自主編成運動」「組織強化拡大」「反戦・平和・護憲運動」など具体的な運動を組合員が手を取り合って積み重ねていかなければなりません。
最後になりますが、本中央委員会の開催にあたって、参加中央委員の皆さんの積極的な質疑討論によって、当面する運動の方針が確立できることをお願いしてご挨拶とさせていただきます。本日はよろしくお願いいたします。
2020年9月4日
道教委2021年度「公立高等学校配置計画案」および「公立特別支援学校配置計画案」の撤回・再考を求める北教組声明
2020年6月4日
道教委は6月2日、2021年度から3年間の「公立高等学校配置計画案」および2021年度「公立特別支援学校配置計画案」を公表した。
「公立高校配置計画案」は、新たに公表した23年度について、①留辺蘂を募集停止とする、②小樽潮陵・室蘭栄・市立函館・旭川北・旭川南・旭川永嶺・美幌を各1学級減とする、とした。昨年度決定した21~22年度の計画によって6校で6学級増、14校で15学級減を行う上で、①函館中部・北見北斗の普通科1学級を理数科に転換する、②普通科フィールド制の札幌丘珠・野幌は普通科、千歳北陽は総合学科に転換する、③野幌・千歳北陽を「新たな特色ある高校」として位置づけるなどと変更した。また、今年度の2次募集後に1学級相当の欠員が生じ学級減となった長沼など21校のうち、再編を予定している伊達緑丘高校を除く20校の21年度の学級数は、9月の計画決定時に公表するとした。さらに、月形・穂別・南茅部・上ノ国については、「所在市町村をはじめとした地域における、高校の教育機能の維持向上にむけた具体的取組とその効果を勘案」して再編整備を留保するとした。これらは、「これからの高校づくりに関する指針」にもとづき「1学年4~8学級」を適正規模として、中卒者数の減少を口実にした機械的な間口削減と再編統合などによる学級減の強行とともに、これまで以上に高校の序列化に拍車をかけるもので断じて容認できない。
留辺蘂の募集停止は唐突に示されたものであり、通学にかかる負担や地元から通いたい子どもの思いなど、地域の実情を考慮することなく、「指針」にもとづき中卒者の減少などを理由としたものである。今後、同様の課題を抱える学校への波及が危惧される。また、野幌・千歳北陽は「新たな特色ある高校」として、「基礎的・基本的な知識・技能の確実な定着を図る」としてフィールド制から転換されたが、こうした子どもや保護者の願いである学びの充実は一部の学校に特化して行うものではなく、すべての学校における課題であり、そのために必要な教育環境整備を道教委は行うべきである。
この間、大幅に人口減少・都市部への一極集中がすすむ道内において、こうした機械的な間口削減・再編統合、差別選別を一層すすめる「公立高等学校配置計画」によって、一層地域の高校を減少させ疲弊・衰退を加速させるとともに、子どもの学びが侵害されている。道教委は、今後開催される「第2回地域別検討協議会」において地域の声を真摯に受け止め、高校存続に向けた体制を早急に構築するべきである。
「公立特別支援学校配置計画案」は、21年度の進学希望見込数を1,381人とし、定員を全しょうがい児学校61校で1,678人(昨年比12学級76人減)とした。また、22年度には「全道で3学級相当の定員の確保を検討」、23年度には「道央圏で2学級相当の定員の確保を検討」するとした。
21年4月には、苫小牧市に小・中学部の知的しょうがい児学校が開校することから将来的な高等部の設置の動きが予想される。また、知的しょうがい児学校高等部への進学者の増加傾向に歯止めがかからず、一層分離・別学に拍車がかかることは明らかである。これは、文科省・道教委のすすめる「特別支援教育」が「分けることは差別につながる」とする「国連障害者権利条約」の理念に反し、どの子も共に学ぶ「インクルーシブ教育」を阻害していると言わざるを得ない。道教委は、しょうがいのある子どもたちの地元の普通高校への入学および進級・卒業に向けた「合理的配慮」など、教育環境整備を早急に行うべきである。
北教組は、「これからの高校づくりに関する指針」や「配置計画案」が、受験競争の激化や高校の序列化を加速させるとともに、子ども・保護者や地域住民の高校存続を求める声を無視するものであることから、引き続き、道教委に対し撤回・再考を強く求める。また、ゆたかな高校教育の実現をめざし、どの地域に暮らしていてもしょうがいのある・なしにかかわらず希望するすべての子どもが地元で学べる「地域合同総合高校」の設置など、子どもの教育への権利と教育の機会均等の保障をめざし、「道民運動」を一層強化していく。
2020年6月4日
北海道教職員組合
新型コロナウイルス感染症から
子ども・教職員の
いのちと健康を守り、
学校の安全・安心と子どもたちの
ゆたかな学びの保障に向けた要請書
2020年5月21日
日頃より、北海道の教育の発展にご尽力されていることに敬意を表します。
さて、国の緊急事態宣言延長にともない、特定警戒都道府県に指定された道内では、すべての自治体で5月中の休校が決定しました。子どもたちは、一年の基盤となる年度始めを校内で過ごすことができず、友人と会えない遊べない日々が続いています。また、楽しみにしていた行事の中止・延期や年度末から続く未学習範囲の拡大、さらには見通しの持てない部活動などに大きな不安やストレスを抱えています。こうした中で教職員は、子どもや家庭と定期的に連絡をとりあい、関係性を保ち学びの機会を様々な手段で確保すべく奮闘しています。学校は、道教委から「在宅勤務」が奨励されているにもかかわらず、「『子どもの居場所』として学校を開設している」「消毒作業や分散登校準備で毎日出勤している」など、国が基準とする接触8割減に遠く及ばない勤務実態となっています。
道教委として、今後、学校を集団感染源の場としないことはもちろん感染経路とさせないため、具体的な対応策を示す必要があります。
また、国の補正予算における「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」は、109の活用事例の中に「修学旅行等の中止に伴うキャンセル料」や「家庭学習教材の作成・購入」「通信・交通に要する経費等」「子育て世帯や家計急変学生への支援」等に活用が可能とされています。しかし、一括の地方財政措置となっていることから、各市町村において確実に学校にかかわる予算を確保させる必要があります。さらに、道・道教委は、コロナ禍によって経済的に苦しむ家庭や各学校に対し財政的な支援を行うため、様々な観点で国に要求していくことが重要です。
学校は本来、子どもたちと教職員が向き合い、また子ども同士がわかり合い、励まし合ってこそ真の学びが育まれる場です。したがって、子どもたちの健康・安全に配慮しつつ、直接的なかかわりを大切にした学びを最大限確保すべきです。以上のことから、学校の休業・再開に関わり、子ども・教職員のいのちと健康を守り、学校の安心・安全と子どもたちのゆたかな学びの保障のために、下記について要請します。
記
1. 子ども・家庭・学校の安心・安全を守るための支援について
①休校による子どもの心のケアを十分行えるよう学校体制を整備すること。
②マスク・消毒用アルコール・ハンドソープ・非接触型体温計など、感染防止に必要な物品を十分に配備すること。
③安全な教育環境確保のため、消毒作業を行うための人員を配置すること。
④寄宿舎やスクールバス添乗での指導など、子どもと密接した教育活動を行う環境に対し3密対策や消毒作業等を徹底すること。
⑤夏季に向けてマスク着用での生活が想定されることから、校内への冷風機の設置など熱中症対策を講じること。
⑥健康診断や集団フッ素洗口については感染拡大防止のため、少なくとも当面は中止するよう指導・助言すること。
⑦新型コロナウイルス感染症に関する休校や登校などの判断および対応については、学校・教職員対応とせず、道・市町村教委が責任を持って保護者に対し説明を行うこと。
2. 子どもたちのゆたかな学びの保障について
①教育課程の編成権は学校にあることから、画一的な判断を押しつけず学校の判断を最大限尊重すること。また、この間中止・延期となった行事等については、子どもに学校生活の楽しさ・喜びをとり戻す観点から、代替措置を最大限構築すること。
②土曜授業や長期休業期間の短縮、7時間授業など過密な日課は子どもの負担増となることから、文科省通知にもとづき標準授業時数を弾力的に扱い、時数の確保のみにとらわれることのないよう配慮すること。
③未履修分に専念できる環境を確保するため、全国学力調査や全国体力調査を道独自の判断で行わないことは当然として、チャレンジテスト、新体力テストなど授業時数を圧迫するものは実施しないこと。また、子どもの主体的な学びを確保するため、他単元や他学年の類似学習内容部分と合わせて学習するなど、現場の工夫を妨げるようなことはしないこと。
④中止・延期となった各種大会・コンクール等については、この間の子どもたちの努力を認め今後の目標設定の場として、教育活動を妨げない範囲で代替措置を講じるなど配慮を行うこと。併せて部活動の社会教育の移行を一層推進すること。
⑤「9月入学・始業」については、様々な課題があり十分な検討が必要なことから、当面、子どもたちの学びの保障および最善の状態での学校再開を優先し、拙速な議論は行わないこと。
3. 教育費支援および教育環境整備に向けた財政確保について
①「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」を教育支援に活用するよう道に求めること。また、各市町村においても同様の要請を行うこと。
②マスク等感染予防のための備品整備や消毒作業等の人員については、学校や個人のボランティアに頼ることなく予算を確保すること。
③臨時休校対応にともなう諸経費(家庭訪問旅費、郵送代、電話代、印刷代)の増加分を措置すること。また、教職員が子どもの健康・安全確認等で必要な経費を個人負担することがないようにすること。個人負担していた場合は、確実に補償すること。
④年度内で発生した修学旅行や校外学習等のキャンセル料及び追加費用について、保護者負担とせず全額補償すること。また、給食費を無償とすること。
⑤家庭の経済環境等に左右されずすべての子どもが多様な教育活動を受けることができるよう、情報機器の整備や通信環境の整備を早急にすすめること。
⑥保護者の経済状況悪化に対応するため、給付型奨学金の支給要件の緩和や支給対象者の拡大をはかること。また、家計の急変による授業料等の負担を軽減するため、現役高・大・専門学校生等を対象とした長期間の生活保障支援の財源を確保するようを国に要望すること。さらに、道独自でも同趣旨の財源を確保すること。併せて市町村に対し、就学援助制度の年度中途認定について柔軟な対応および周知徹底を要請すること。
4. 教職員が教育活動に専念できる職場環境・労働条件の整備について
①教室などの過密化を防止する観点から、30人以下学級を実現するため国にはたらきかけること。また、当面は分散登校の基準となっている20人以下の少人数指導に向けて教員や学習支援員等の増員をすすめること。そのため、教員免許保持者確保の観点から免許更新制度の廃止・休止を文科省に要請すること。
②学校再開後は教育課程の過密化が懸念されることから、指定研究事業・各種法定研修事業の中止・規模縮小をはかること。また、指導主事訪問やそれに伴う特設公開授業を行わないこと。併せて、市町村独自の研修等については、教職員や子どもたちの負担軽減の観点から凍結するよう要請すること。
③教職員の健康と安全の確保のために、勤務時間の遵守および管理を適切に行うこと。
④新型コロナウイルス感染症対応は、「上限方針」の「児童生徒に係る臨時的な特別な事情」の対象とはしないこと。また、「要領」の対象業務に新たに盛り込むなど、やむを得ず行った超勤や週休日の勤務については実質的な回復を措置すること。
⑤感染防止のための在宅勤務の推奨を徹底すること。
⑥子どもの学びの保障にかかわり勤務日の変更などについては、教職員の超勤・多忙化とならないよう、週休日の振替や勤務時間の割振り変更を完全措置するとともに、休暇等についても確実に行使できるよう配慮を行うこと。
⑦勤務条件に関することは、北教組と十分協議・交渉を行うこと。
2020年5月21日
北海道教職員組合 中央執行委員長