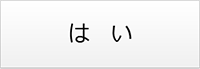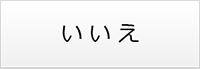「安全保障3文書」に抗議する声明
2022年12月19日
岸田政権は12月16日、「安全保障3文書(国家安全保障戦略、国家防衛戦略、防衛力整備計画)」の改定を閣議決定した。「敵基地攻撃能力(反撃能力)」の保有に踏み込むとともに軍事大国化や米軍との一体化を一層加速させるなど、憲法9条を蔑ろにして「戦争をできる国」に突き進もうとすることは、断じて容認できない。また、専守防衛の原則にもとづく戦後日本の安全保障政策の大転換であるにもかかわらず、国会での議論を経ずに閣議決定で行うことは、暴挙以外の何ものでもない。岸田政権によるこの閣議決定に対し強く抗議する。
これまで政府は、性能上専ら相手国国土の壊滅的な破壊のために用いられる「攻撃的兵器」の保有は「いかなる場合にも許されない」とし、日米安保条約の下、敵地攻撃は米軍に依存し、自衛隊は防御に徹するとしてきた。しかし、今回の「国家安全保障戦略」では、外国領域を直接攻撃する能力を持つと宣言し「反撃能力」の保有を明記した。日米による共同対処が前提となる「反撃能力」の保有により、米軍との一体化がさらに加速することは避けられない。政府は、専守防衛に徹する方針は今後も変わらないとする一方で、相手が攻撃に「着手」すれば憲法上反撃できると説明している。しかし、判断を誤れば憲法・国際法に違反する先制攻撃となりかねない。
また、「国家安全保障戦略」は、中国について「これまでにない最大の戦略的な挑戦」、北朝鮮について「一層重大かつ差し迫った脅威」、ロシアについて「安全保障上の強い懸念」と表現を改めた。軍事力強化により米国とともに対中などの抑止をめざす政府の姿勢は、緊張を高める行為と言わざるを得ない。
さらには、2027年度に防衛費と関連経費を合わせた予算水準を現在の国民総生産の(GDP)比2%まで増額する方針も掲げた。これにより防衛費は23~27年度の5年間で43兆円程度となり、世界からは軍事大国化ととらえられかねない。
安全保障の目的は、国民を守ることにあり、国家の役割は、国民生活を脅かす衝突や危機を防ぎ戦争を回避することにある。「安全保障3文書」は、防衛力を強化すれば、相手に侵攻を思いとどまらせることができると強調している。しかし、軍事力増強で日本の平和と安全を守れる確証はない。軍事力の強化は、抑止力にはつながるどころか、互いの疑心暗鬼を招き、かえって他国の軍拡を招くなど際限のない軍拡競争に陥る懸念すらある。
日本は、平和国家という政治的価値観を損なうことのないよう、武力によらない安全保障を確保する姿勢を示し、意思疎通や対話を通じて緊張状態を回避し、地域の安定をはかるべきである。また、平和憲法を持つ日本は、文化的交流・平和国家という政治的価値観・外交政策を最大限に活かして平和を守っていくとともに、率先して軍拡競争に歯止めをかけ世界平和に寄与していくべきである。
私たちは、「教え子を再び戦場に送らない」のスローガンのもと、憲法の理念を護るため、平和を望む多くの広範な市民と連帯し、今後もあらゆる戦争につながる動きを断固阻止するよう、組合員の総力を結集して全力でたたかう。
2022年12月19日
北海道教職員組合
2022年度 道教委「全国学力・学習状況調査 北海道版結果報告書」に対する北教組声明
2022年11月2日
道教委は11月2日、2022年度「全国学力・学習状況調査北海道版結果報告書」を公表した。その中で、「小学校のすべての教科で全国平均との差が縮まるとともに、小学校理科、中学校国語と理科の3教科で全国平均とほぼ同水準となるなどの改善傾向が見られる」とした。一方で、「すべての教科で全国平均に届いていない」「自分の考えをもち、筋道を立てて説明することなどに課題が見られる」「授業以外で勉強する時間が短い」などとし、「組織的な授業改善」「望ましい学習・生活習慣の定着」など、昨年度とほぼ同様の「分析」を行った。
「本道の状況」では、1人1台端末と各教科の平均正答率の関連について、①「ほぼ毎日」使用させたと回答した学校ほど高い傾向にある、②持ち帰って家庭で利用できるようにしている学校は、持ち帰らせていない学校に比べて高い傾向にある、などICT機器の活用による成果を強調する分析を行っている。また、「PDCAサイクルや組織的な取組に関連する質問に肯定的に回答した学校ほど各教科の平均正答率が高い傾向にある」として、自らがすすめる「検証改善サイクルの確立」を正当化した。
地域差が拡大し、人口の少ない町村部の平均正答率が低かったことに対しては、「学習塾との連携」など学校外での学習に言及するとともに、公営塾を開設している市町村のように他市町村にも、「地域全体で学習支援する」自助努力を求めるなど、「塾がない地域」「経済的理由により塾に通えない子ども」などを一切顧みず、公教育の役割を没却する無責任な提言を行っており、断じて容認できない。
北教組の調査では、北海道の小中学校において、「過去問や道教委提供の『チャレンジテスト』による事前対策が『当たり前』となってきていることが負担」といった実態が明らかになっている。毎年「全国上位」とされる石川県について、4月は事前対策に追われ、「1~5時限すべて過去問を解いている学校もある」「教職員の負担やプレッシャーが大きく、子どもと向き合う時間が減少している」などの様子があらゆるメディアで報じられている。
文科省・道教委も「調査により測定できるのは学力の特定の一部分」としながら、23年度から27年度「北海道教育推進計画 素案」において、「小中学校の国語、算数・数学の平均正答率が全国以上の教科数」を「新しい時代に必要となる資質・能力の育成」の指標として「目標値」を設定しようとしている。現状においても、到達目標に達成できない子どもは差別・選別されており、点数学力偏重の学校になじめず不登校となる子どもも一向に減少していない。また、教職員も、11月に結果公表がなされるにもかかわらず調査実施後に解答用紙をコピーし、直ちに自校で採点・分析後、授業改善が命じられるなど、調査に翻弄され超勤・多忙化は一向に解消されていない。「序列化や過度な競争が生じないよう配慮を」と報道機関に要請する道教委が、管内の平均をグラフ化し、市町村別の結果を公表することで、「他管内・他市町村には負けられない」とした競争を生じさせている。また、地域間格差が生じる根本的な要因を分析することなく、「検証改善サイクルの確立」「授業改善」「小中学校の連携した取組の充実」「望ましい学習習慣の確立」「ICT機器の活用」のみを「改善策」として画一的な教育を押しつけている。
「義務教育の機会均等とその水準の維持向上の観点から、全国的な児童生徒の学力や学習状況を把握・分析し、教育施策の成果と課題の検証・改善に役立てる」目的なのであれば、隔年調査や抽出調査でも十分である。過去問やチャレンジテストによる事前対策を事実上「強制」し、全道に画一的な授業改善を指示する教育施策が本当に子どものゆたかな学びにつながっているのか、今一度問い直すべきである。子どもが夢や希望を持ち、自分で考え行動する力を身につけられるためには、どういった教育が必要なのか明確な理念とビジョンを持ち、地域や子どもの実態に応じたカリキュラム編成を達成することこそが求められている。
直ちに道教委がすべきことは、膨大な時間・費用・労力をかけて変わり映えのしない分析を毎年くり返す硬直した姿勢の改善であり、不登校やいじめ、ストレスなど現実の子どもの苦悩に向き合うことである。地域や子どもの実態に即しゆたかな教育を保障するため、押しつけの「学力向上策」を止め、①少人数学級の実現や就学援助など教育予算の拡充、②教育課程の弾力化や学校の裁量権の保障、③教職員の持ち授業時間数を減らすため定数を改善したうえで、子ども一人ひとりとゆとりを持って接する時間の保障、など教育条件の整備・拡充と教職員の超勤・多忙化解消に全力でとりくむことを求める。
北教組は、「報告書」「結果公表」に断固抗議するとともに「全国学力・学習状況調査」に反対し、子どもたちの「学び」を矮小化する「点数学力」偏重の「教育施策」の撤回を強く求める。
私たちは今後も、憲法・「47教育基本法」・「子どもの権利条約」の理念にもとづく「ゆたかな教育」の実現のため、「主権者への学び」をすべての教育活動の底流とした教育実践を積み重ね、市民とともに教育を子どもたちのもとへとりもどすための広範な道民運動をすすめていくことを表明する。
2022年11月2日
北海道教職員組合
道教委2023年度「公立高等学校配置計画」および「公立特別支援学校配置計画」に対する北教組声明
2022年9月8日
道教委は9月6日、23年度から3年間の「公立高等学校配置計画」と23年度および24年度以降の見通しを示した「公立特別支援学校配置計画」を公表した。
「公立高等学校配置計画」では、6月の「計画案」からの変更点として、23年度に募集停止としていた留辺蘂を「特色ある教育活動の一部を近隣校に引き継ぐため」として、募集停止時期を1年延期した。また、22年度入学者選抜の結果、第2次募集後の入学者に1学級相当以上の欠員が生じ学級減としていた20校のうち、栗山などの9校は1学級増としたものの、札幌丘珠、札幌南陵、札幌あすかぜ、札幌白陵、北広島西、当別、岩内、美瑛、天塩、大樹、標茶の11校は1学級減のままとした。加えて25年度穂別を募集停止、夕張・長万部・豊富・倶知安農業については「所在市町村をはじめとした地域における、高校の教育機能の維持向上にむけた具体的取組とその効果を勘案」して再編整備を留保するとし、その他は計画通りとした。これにより、23年度は、天塩と弟子屈へ地域連携特例校を導入。24年度は、①利尻商業科1学級減、②釧路商業の4学科を1学級減とし学科転換、③釧路湖陵、大樹の学科転換による普通科新学科設置。25年度は、①深川東、室蘭工業を1学級減、②岩見沢東を岩見沢西と再編して2学級減し、岩見沢緑陵を1学級増、③富良野と富良野緑峰を再編し5学級の新設校、が確定した。
留辺蘂については地域の声を受け止めて募集停止延期となったものの、撤回はされず残念な結果と言わざるを得ない。また穂別については、地理的に統廃合が難しい「地域連携特例校」が募集停止となったことで地元の子どもたちの進路選択の幅を奪うものであり、他の地域連携特例校の地域・保護者・子どもたちに大きな不安を与え看過できない。
「公立特別支援学校配置計画」では、23年度について、定員を全しょうがい児学校61校で昨年度より22人増の1,706人とした。「計画案」からの変更点として、22年度末で白糠養護学校を閉校、23年度に1学級減としていた室蘭養護学校については学級数維持、南幌養護学校と真駒内養護学校を1学級増とした。また、「知的高等支援学校」の配置の見通しでは、24年度に道央圏で2学級相当、道北圏で1学級相当の定員の確保を検討していたが、いずれも既設校で対応する見通しを盛り込んだ。
進学希望見込み数によりしょうがい児学校の学級数を増減することは、現場の思いをくんだうえで計画策定しているもので一定程度理解できるものの、中卒者数減にもかかわらずしょうがい児学級定員が増加し続けている現状は、「発達障害」等をあぶり出し普通学級からの分離・別学をすすめている教育施策によるもので容認できない。これは、「障害者差別解消法」等に反し、共生社会を実現するためのインクルーシブ教育を否定するものである。「分けることは差別につながる」とした「国連障害者権利条約」の理念にもとづき、希望する子どもたちの地元の普通高校への進学を保障するため、すべての学校において「合理的配慮」などの教育条件整備を早急にすすめるべきである。
今後も少子化がすすんでいくことは明らかであることから、これまで同様に学級減などを機械的にすすめることは、子どもを都市部へ一層流出させ、地域の活力をそぐことにつながる。道教委は、地方の小規模校を「数」のみをもって募集停止・学級減とせず、地元から高校進学が可能な配置計画や、少人数でも運営できる学校形態などの施策を「これからの高校づくりに関する指針」に盛り込むべきである。北教組は、機械的に削減し続ける「これからの高校づくりに関する指針」「配置計画」の撤回・再考を求めるとともに、希望するすべての子どもがしょうがいのある・なしにかかわらず地元で学べる「地域合同総合高校」の設置など、子ども一人ひとりの要求に応えるゆたかな後期中等教育を保障するため、道民運動を一層強化していくことを表明する。
2022年9月8日
北海道教職員組合
安倍元首相の「国葬」および学校に弔意の強制をすることに反対する
北教組声明
2022年8月24日
岸田内閣は7月22日、安倍元首相の「国葬(国葬儀)」を9月27日に日本武道館で行うと閣議決定した。
北教組は、「国葬」を行うことについて、憲法上問題があり、民主主義の観点からも疑義があることから反対する。とりわけ、学校における弔意の実質的強制につながりかねず、子どもたち・教職員の思想・良心の自由の保障と民主主義を担う主権者教育をすすめる観点から、重大な懸念があり認められない。
政府は、「国葬」とする理由について、「歴代最長の期間、総理大臣の重責を担い、内政・外交で大きな貢献をした」などとしている。 しかし、安倍元首相は、特定秘密保護法制定、集団的自衛権行使を容認する「解釈改憲」、安全保障関連法の制定、共謀罪の制定など国論を二分した問題の数の力による強行や、国会における度重なる虚偽答弁など、立憲主義を破壊してきた。
これらの安倍内閣の各政策を「国に対する功績」と評価して「国葬」を行うことは、立憲主義の要諦である国家の価値中立性に反するとともに、憲法の基本理念を揺るがすものであり容認できない。政府が特定の政治家についてその業績を一方的に高く評価し、その評価をたたえる儀式として「国葬」を国費によって行うことは、「国家として当該個人への弔意を表すもの」となり、すべての国民に弔意を事実上強制する意味をもつ。これは、憲法で保障されている思想・良心の自由の侵害にあたる。さらには、故人の評価を国是として国民に同調を求め、安倍元首相を礼賛する実際上の効果により「神格化」されかねず、民主主義の根幹が問われるものである。
日本では、「大日本帝国憲法」下で1926年公布の「国葬令」のもと、皇族と「国家に偉功ある者」に対して「国葬」が行われてきたが、47年日本国憲法施行の際、平等主義や政教分離など、憲法規定に不適合なものとして「国葬令」は失効した。
戦後唯一、67年の吉田茂元首相の「国葬」が実施された際には、翌年の国会で当時の大蔵大臣が「法的根拠はない」と答弁しており、75年佐藤榮作元首相死去に際し「国葬」実施が検討されたときも「法的根拠が明確でない」とする内閣法制局の見解等で見送られた経緯がある。その後首相経験者の葬儀は、内閣と自民党との「合同葬」が慣例となっている。政府は、内閣府設置法で内閣府の所掌事務とされている「国の儀式」として閣議決定があれば実施可能としているが、「国の儀式」に「国葬」が含まれる法的根拠はなく、認められない。
吉田元首相の「国葬」の際には、弔旗掲揚、黙祷の実施、官公庁・公立学校の半休、歌舞音曲をともなう行事の差し控え、娯楽番組放送の中止などの「お願い」が出された。安倍元首相の「国葬」の際にも学校に同様の「お願い」がされ、弔意表明の事実上の強制が行われかねない。現に安倍元首相の葬儀にあたり、山口県、福岡県、東京都、兵庫県三田市、神奈川県川崎市、大阪府吹田市、宮城県仙台市の教育委員会が葬儀に合わせて学校現場における「日の丸」の半旗掲揚を求めた事例が生じた。北海道では帯広市において、葬儀当日午後の市教委からの電話要請にもかかわらず、市内全小中学校39校のうち35校で半旗掲揚が行われた。
「教育基本法」では、14条2項で「特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない」と明記しており、様々な専門家からも「学校が個別の政治家について、弔意を表明することは、子どもに特定の政治的な価値判断を押しつけることになり、教育基本法に反する」「教育委員会の弔意表明の要請は、教委の政治的な中立性を損なう行為でもある」などが指摘されている。「国葬」実施によって国家をあげてまつりあげることにより、子どもたちに安倍元首相が「特別な人として刷り込まれる」ことになりかねない。このことは、民主主義を担う「自ら判断して行動する主権者」の育成を阻害するものである。
先にあげた当該教育委員会は、「協力を要請しただけ」「掲揚は各校の判断に任せた」「弔意を強制したつもりはない」などとしているが、この件にかかわらず現在の学校現場において、教育委員会の様々な要請を校長判断で「実施しない」ということはほぼあり得ず、実質上の「指示」「強制」がまかり通っている。
以上のことから北教組は、「国葬」実施、および学校現場に対し各自治体・教育委員会による弔意の実質的強制につながる通知または口頭などの働きかけに反対する。
2022年8月24日
北海道教職員組合
2022年度 文科省「全国学力・学習状況調査」の結果公表に対する
北教組声明
2022年8月4日
文科省は7月28日、22年度「全国学力・学習状況調査」(以下、「全国学テ」)の結果を公表した。これを受け地方新聞等では、子どもの学習環境を整えられない実態や経済状況等の背景を抜きに、全国や前年度の数値と比較をしながら、順位や正答率などを強調し、数ポイントの差によって「高い・低い」と評価して報道している。とりわけ今年度は、中学校で新「学習指導要領」の実施後初となる4年ぶりの理科の調査結果について、平均正答率が5割を切り、新「学習指導要領」が求める科学的探究の力を測る問題で正答率が低いと分析された。文科省は「調査」の目的を「学校における児童生徒への教育指導の充実や学習状況の改善等に役立てる」としているものの、この間、各都道府県教委は学力調査の「目標値」を設定し、「学力向上」の名の下、過去問題のくり返しや事前対策の徹底など画一的な「授業改善」を現場に強いている。
道教委も同日、文科省の公表に追随し「全国学力・学習状況調査 調査結果のポイント」を公表した。教育長は「小学校のすべての教科で全国の平均正答率との差が縮まるとともに、小学校の理科、中学校の国語と理科の3教科で全国の平均正答率とほぼ同水準となるなど改善の傾向が見られる」とし、各市町村教育委員会及び学校の「最大限の尽力で一定の成果として現れてきつつある」などとコメントした。
文科省・道教委がすすめる「全国学テ」の実施・結果公表は、学校現場を過度な競争的環境に置くもので、学びの主体となるべき子どもは、蔑ろにされ続けている。「学力向上策」に偏った授業や「学習規律」「望ましい生活習慣の確立」を押しつけることで、子どもたちは疲弊し自ら学ぼうとする意欲を失っている。国連子どもの権利委員会は日本政府に対し「高度に競争主義的な学校環境が、就学年齢にある子どもの間のいじめ、精神的障害、不登校・登校拒否、中退および自殺の原因となることを懸念する」「過度に競争主義的な環境が生み出す否定的な結果を避けることを目的として、大学を含む学校システム全体を見直すこと」を勧告しているが、勧告は無視され続け、むしろ競争に拍車がかかっている。こうしたことから、「いじめ」「不登校」の増加に歯止めがかからない現状が生じている。
道内では、全国平均との比較にとどまらず、毎年11月に公表される管内別の報告書により、管内・市町村の競争や序列化を生じさせ、「学力向上」のための校内対策会議等開催や、独自の「チャレンジテスト」の問題演習の強要などが行われている。また、7月末の結果公表前に「早期に自校の傾向を把握することが重要」として、各学校では4月のテスト実施後、回答(解答)用紙をコピーし自校で採点・分析させられ研修への持参が強要されるなど、教職員の超勤・多忙化に拍車がかかっている。
道教委は「貧困と格差」が「教育格差」につながっていることを分析し、施策に反映させることを最重点としなければならないにもかかわらず一向にこうした検証・分析は行われずに、「ICTの活用を含めた授業改善」「学校、家庭、地域の連携協働による望ましい学習・生活習慣の確立、習熟度別学習の拡大」など現場実態を顧みない一方的で画一的な施策の強要に終始している。
北教組は、「点数学力の向上」ではなく、学校・子どもの安心・安全を確保し、子どもたちが学びの主体となる環境を整えること、教職員に十分なゆとりをもたせることが急務であるとこれまで訴えてきた。文科省・道教委は、「全国学力調査・結果公表」とそれにもとづく「点数学力向上策」の押しつけを即刻中止し、各学校の自主的・創造的な教育活動と一人ひとりの子どもに寄り添う実践を保障するとともに、教職員をはじめ、保護者・地域の声を真摯に受けとめるべきである。また、少なくとも欠員不補充を早急に改善した上で、教職員の超勤・多忙化解消をすすめ授業準備・教材研究を勤務時間内に行えるようにするとともに、「子どもの貧困」解消と「教育格差」是正をすすめるなど、本来すべき勤務条件・教育条件整備に徹するべきである。
北教組は今後も、子どものゆたかな学びを阻害する「全国学力調査」に反対し、憲法・「47教育基本法」・「子どもの権利条約」の理念にもとづく「わかる授業・たのしい学校」「差別選別の学校から共生・共学の学校」をめざして、「主権者への学び」を基盤とした教育実践を積み重ねるとともに、教育を市民の手にとりもどすための広範な道民運動をすすめていくことを表明する。
2022年8月4日
北海道教職員組合
第126回中央委員会
中央執行委員長あいさつ
2022年6月20日
北教組第126回中央委員会にお集まりいただいた、中央委員、役員の皆さんにお礼を申し上げるとともに、来賓として日本教職員組合中央執行委員長の瀧本司さんにお越しいただいたことは、大変光栄であり北教組の組合員を代表して感謝申し上げます。中央委員会開催にあたり、ご挨拶させていただきます。
「育児放棄」や「虐待」を受けた子どもたちの悲しい報道が相次いでいます。「コロナ禍」で人々の心が益々、痛んでいるのではないかと思います。私たちは自主編成運動のとりくみの中で、ゆたかな教育の創造をめざしていますが、感染症の影響によって子どもたちの心の中で社会、大人たち、自分自身をどのように見ているのか、心の変化を学びの実践の中で注視することや、それに対応した教育課程の編成が必要となっています。「自分を大切にできる」「大人や他者を信頼できる」「不安な時に受け止めてくれる」ということなどを学校の中でも実感できるよう、一人ひとりの子どもを支えることができる学校づくりをめざすことが大切であることを改めて、皆さんと共有したいと思います。
そのためにも、子どもの状況・様子を語ること、対話すること、実践の悩みや疑問を出し合うために、声をかけ合い集まることの真の中心となれるのが、私たち教職員組合であります。当然、現状を考えれば「多忙化解消」「業務削減」「定数改善」との両立した運動が必要であり、労働組合として本来の機能も果たさなければなりません。
本中央委員会では、子どもと学び、学校のあり方、働く者としての権利拡大、職場づくり・仲間づくりの強化を基本とした、活発な論議をぜひともよろしくお願いします。
こうした中、7月10日に第26回参議院議員選挙を迎えることになります。この間、日教組を中心とした全国連帯のとりくみによって、「給特法の改正」「教員免許更新制の廃止」など、とりくみの成果が徐々に組合員に浸透しつつある中、この完遂をめざして「教育の議席」を守りぬき、私たちの要求・悲願を何としても実現しなければなりません。
ロシアによるウクライナ侵攻は、一部の人々を刺激し、「専守防衛の見直し」賛成がJNN調査で52%となっています。こうした世論を背景に憲法改悪の動きが今後、具体化されることが危惧されます。首相の指導性、物価・経済問題等で覆い隠し、一気に選挙戦に臨むことが考えられます。こうした機運が煽られる中、私たちは「教え子を再び戦場に送らない」のスローガンを再確認し、「教育の議席」の持つ意味をすべての教職員、退職者に伝え切り、日教組・北教組の政策制度要求の影響力を示すために、北教組一致団結して共にがんばりましょうということを申し上げ、中央委員会開催にあたっての挨拶といたします。
2022年6月20日
道教委2023年度「公立高等学校配置計画案」および「公立特別支援学校配置計画案」の撤回・再考を求める北教組声明
2022年6月8日
道教委は6月7日、2023年度から3年間の「公立高等学校配置計画案」および2023年度「公立特別支援学校配置計画案」を公表した。
「公立高校配置計画案」は、20年度「配置計画」で再編整備留保となっていた穂別を25年度に募集停止すると新たに公表した。また、23年度については、天塩と弟子屈を地域連携特例校の導入と変更、24年度については、①利尻を商業科1学級減、②釧路商業の4学科を1学級減とし学科転換、③釧路湖陵、大樹の学科転換による普通科新学科設置、とした。25年度については、①深川東、室蘭工業を1学級減、②岩見沢東1学級減としていた計画を岩見沢西と再編して2学級減し、岩見沢緑陵を1学級増、③富良野と富良野緑峰を再編し5学級の新設校、などとした。また、夕張・長万部・豊富・倶知安農業については、「所在市町村をはじめとした地域における、高校の教育機能の維持向上にむけた具体的取組とその効果を勘案」して再編整備を留保するとした。
これらは、「中卒者数の状況、学校規模、募集定員に対する欠員の状況、地元からの進学率」など数字のみをもとにした機械的な判断で、募集停止とされる地域の子どもたちは、遠距離通学や下宿などによって保護者の財政的負担も増加する。また、北海道の多くの地域は、公共交通機関の便が限られ通学に時間を取られることで、友人との時間や学習時間等が奪われ心身共に負担が大きい。さらに、管外への進学者も増加し、人口減少・都市部への一極集中がさらにすすむことから、都市部を除く地域は疲弊・衰退が加速するとともに、子どもの学びが侵害されている。再編留保は、該当地域に対して継続した自助努力を求めるものと言わざるを得ない。また、子どもたちのためではなく、道教委に留保を認めてもらうための学校づくりをすすめてしまう危惧がある。
「これからの高校づくりに関する指針」にもとづき「1学年4~8学級」を適正規模として中卒者数の減少を口実にした機械的な間口削減と再編統合などによる学級減を強行し続けることは、これまで以上に高校の序列化に拍車をかけ差別選別を一層すすめるものである。少子化がすすんでいる実態があるものの、機械的な間口削減や再編統合、募集停止によって通学が困難になったり遠方へ進学せざるを得ない子どもを生じさせることは看過できない。だからこそ「指針」を抜本的に見直し、少人数でも運営できる学校形態を確立する必要がある。その一例として北教組は、近隣複数校が連携し、1年時は共通科目を地域の校舎で、2年時以降進路希望に応じて子どもが他校舎を行き来できる「地域合同総合高校」を提唱してきた。
「公立特別支援学校配置計画案」は、23年度の進学希望見込数を1,374人とし、定員を全しょうがい児学校61校で1,690人(昨年比2学級6人増)とした。職業学科を含む知的高等支援学校24校では、22年度と同様、定員を904人とした。また、24年度には「道央圏で2学級相当」「道北圏で1学級相当」の定員の確保を検討するとしている。中学校卒業者数の推計は減少し続けているにもかかわらず、しょうがい児学校の定員が増加していることは、一層分離・別学に拍車をかけるものである。これは、文科省・道教委のすすめる「特別支援教育」が、「分けることは差別につながる」とする「国連障害者権利条約」の理念に反し、どの子もともに学ぶ「インクルーシブ教育」を阻害している。道教委は、しょうがいのある子どもたちの地元の普通高校への入学および進級・卒業に向けた「合理的配慮」など、教育環境整備を早急に行うべきである。
北教組は、「これからの高校づくりに関する指針」や「配置計画案」が、受験競争の激化や高校の序列化を加速させるとともに、子ども・保護者や地域住民の高校存続を求める声を無視するものであることから、引き続き、道教委に対し撤回・再考を強く求める。また、どの地域に暮らしていてもしょうがいのある・なしにかかわらず希望するすべての子どもが地元で学べる「地域合同総合高校」の理念を生かしたゆたかな高校教育の実現と子どもの教育への権利と教育の機会均等の保障をめざし、「道民運動」を一層強化していく。
2022年6月8日
北海道教職員組合
ロシアによるウクライナ侵攻に抗議し、即時撤退を求める声明
2022年3月15日
ロシアは、ウクライナに侵攻し、子どもを含む多くの市民のいのちを奪っている。ロシアによる侵攻は、ウクライナ東部の市民を守るためと主張していたが、戦禍はウクライナ全土に広がっており、民間人の犠牲者についての報道が続いている。ウクライナ東部地域の一方的な独立承認や軍事侵攻は、領土と主権を侵害し、紛争の平和的解決を義務づける国際法に著しく反するものである。
また、プーチン大統領は、核兵器使用をほのめかす発言をし、侵攻前には核兵器搭載可能な大陸間弾道ミサイルを使った軍事演習を実施するなど、核による威嚇を繰り返してきた。ロシア軍は、チェルノブイリ原発を占拠し作業員を拘束するとともに、他の原発も占拠しようとしている。広島・長崎・福島での惨事を経験した私たちは、これら核・核兵器による威嚇に対し激しく抗議し、核兵器の廃絶を求める。
戦争は、最大の人権侵害であるとともに、永久に消えることのない憎しみの連鎖を生じさせる最悪の手段である。軍事的行為はいかなる理由があろうとも、絶対に許すことはできない。「武力で平和はつくれない」ことはイラクやアフガニスタンの現状をみれば明らかである。ロシアのウクライナ侵攻に対して強く抗議し、即時撤退を求める。
日本の一部の政治家は、ことさら台湾、北方領土、竹島を例にあげ、主権や領土への侵害の危機を煽り、憲法9条の改憲議論に拍車をかけようとしており、ウクライナ侵攻に乗じて改憲を推しすすめようとすることは、断じて許されない。
また、岸田政権は、「防衛装備移転三原則」の「運用指針」の防衛装備品が輸出できる案件に「国際法違反の侵略を受けているウクライナ」を加えた上で、閣議決定を早々に行い空輸した。安倍元首相に至っては、米国の核兵器を日本国内に配備し日米で共同運用する「核シェアリング」の導入を検討すべきと非核三原則の根本を揺るがす発言を行った。
平和主義を基本理念とする日本は、国際紛争を助長する武器の輸出や核武装ではなく、医薬品や衛生用品など非軍事物資の提供など人道的支援を行うとともに、事態打開にむけて対話による外交的解決がはかられるようにはたらきかけていくべきである。
私たちは、「教え子を再び戦場に送らない」のスローガンのもと、ロシアのウクライナ侵攻に抗議し、平和を望む多くの広範な市民と連帯し、今後もあらゆる戦争や軍事的行為等を許さないとりくみをすすめていく。
以 上
北海道教職員組合