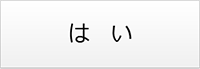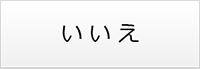文科省「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別
措置法の一部を改正する法律案」
可決・成立に対する北教組声明
2019年12月5日
政府・与党は12月4日、第200回臨時国会参議院本会議において、多くの課題が日政連議員等から指摘される中、国会会期末が迫っていることを理由に「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部を改正する法律案」(以下、「給特法改正案」)を与党・日本維新の会による賛成多数で可決・成立させた。
「給特法改正案」は、超勤時間を「月45時間、年360時間以内」と定めた「上限ガイドライン」を指針化するとともに、都道府県毎に条例により教育職員に「1年単位の変形労働時間制」を適用可能とするものである。文科省は、「上限ガイドライン」の遵守を前提に、課業中の一部の勤務時間を延長(例示では週3時間13週で計39時間延長)し、その分で長期休業期間中に休日の「まとめ取り」(5日)を可能として教職員の勤務実態を改善するとしている。
しかし、これらはいずれも何ら超勤を削減するものではなく、むしろ、現状の超勤実態を追認し、固定化・助長しかねないもので、断じて容認できるものではない。この間の国会における日政連・北政連議員などの追及により、衆参両院において「1年単位の変形労働時間制の導入が、(中略)長期休業期間中等に休日を与えることを目的としている」など多くの附帯決議をつけさせたが、そもそも抜本的な超勤解消につながるものではない。
政府・文科省は、「1年単位の変形労働時間制」導入の大前提は「上限ガイドライン」の遵守としているが、これまでの審議において「月45時間、年360時間以内」とするための具体的な業務削減策は何ら示されていない。
文科省は、スクールサポートスタッフの配置などによって、年間360時間の在校時間の縮減が可能としたが、週27時間の授業を担当するなど所定の勤務時間のほとんどが子どもと接する時間となっている小学校教員にとって、授業時数が削減されない限り改善は見込めない。また、部活動指導員等外部人材の活用によって、年間160時間の在校時間の縮減が可能としたが、中学校において部活動指導員が配置されている学校が依然として2割程度にとどまっている地域も多く、学校に一人の配置では効果は期待できない。文科省の想定は、現場実態と著しく乖離した机上の空論と言わざるを得ず、現状「月45時間、年360時間以内」が遵守されるとは到底考えられないことから、1年単位の変形労働時間制導入はその前提を欠いている。また、仮に夏休みの「まとめ取り」が可能となったにしても、超勤の回復は直近に行わなければ過労死や健康被害を防ぐことができないのは明らかである。
北教組は、独自要請も含め日政連「水岡俊一」、日政連・北政連「勝部賢志」議員らと連携し国会対策を強化してきた。「給特法改正案」にかかわる日政連議員等の追及に対して文科省は、勤務時間は勤務条件であり「地公法」55条に規定される交渉・協定の対象であることは認め、「導入に当たっては各地方公共団体において、職員団体との交渉を踏まえつつ検討されるもの」「校長がそれぞれの教師と対話をし、その事情などをよく酌み取ることが求められる」などとしたものの、各級段階での交渉が必須であるとまでは明言しなかった。
また、この間の追及により、所定の勤務時間外に明示・黙示に拘わらず校長の指揮・命令下で行った業務は、「校務であるが、地公法(労基法)上の労働時間にあたらない」とする文科省の不当答弁など、「給特法」の矛盾と、矛盾をそのままに今回の「改正」を行うことの不合理が一層明らかになり、参院において「三年後を目途に教育職員の勤務実態調査を行った上で、本法その他の関連法令の規定について抜本的な見直しに向けた検討を加え、その結果に基づき所定の措置を講ずる」との附帯決議をつけさせた。
北教組は、道教委交渉を強化し、2020年の「上限ガイドラインの指針化」、2021年「1年単位の変形労働時間制導入」の一方的な条例化を許さず、超勤排除に向け大幅な業務削減を求めるとともに、「原則時間外勤務は命じない」「命ずる場合は限定させる」ことを遵守させ、やむを得ず行った超勤に対しては直近に実質的な回復を措置させるよう全力でとりくんでいく。また、「長時間労働是正キャンペーン」により世論喚起をすすめ、引き続き「タダで働かせ放題」を容認する「給特法」の廃止・抜本的見直しを求めるとともに、部活動の社会教育への移行をはじめとした大幅な業務削減、教職員定数増などによる教員一人あたりの持ち授業時数の削減など、抜本的な超勤解消策を求め運動を強力にすすめていく。
以 上
北海道教職員組合
2019年度道教委「全国学力・学習状況調査北海道版結果報告書」に
対する北教組声明
2019年11月7日
道教委は11月6日、2019年度「全国学力・学習状況調査北海道版結果報告書」(以下「報告書」)を公表した。今回の報告では、178市町村が結果公表に同意し(昨年比3町村増)、平均正答率の実数公表も24市町と昨年より増加した。こうした状況は、道教委が各市町村教委に対して執拗に公表を求め続けてきた結果であり、子どもはもとより学校間・地域間を競争・序列化させる姿勢は断じて容認できない。
道教委は、「習熟度別指導などにより、正答数の少ない子どもの割合が減少するなど改善の傾向が見られる一方、全ての教科で全国平均に届いていない」とし、「結果は学力の特定の一部」としているにもかかわらず、「報告書」では点数に特化して全国との比較に終始した。また、「考えたり話し合ったりする知識を活用する授業の改善が十分とは言えない」「授業以外で勉強する時間が全国と比べ短い」など、一方的に課題を挙げ、「『主体的・対話的で深い学び』の実現に向けた授業改善や、家庭や地域と連携した望ましい学習習慣・生活習慣の定着に向けた取組を一層充実させる必要がある」と、子どもや学校・家庭の実態を顧みずにさらなる努力を求めている。
「全道の状況」についても、今年度の調査は「知識と活用を一体的に問う」としてA・B問題の構成を見直して実施したが、依然として①平均正答率の推移、②各教科領域の平均正答率、③正答数の状況、について全国との数値比較に留まっており何ら変わっていない。また、質問紙調査と教科結果をクロス分析し、「学校のきまり〔規則〕を守っていますか」「授業では、課題の解決に向けて、自分で考え、自分から取り組んでいたと思いますか」などの項目で肯定的な回答をしている児童生徒や学校の方が教科の平均正答率が高いとして、恣意的に学習・生活習慣や規範意識を強要している。さらに、管内および各市町村の状況についても、14管内の平均正答率の順位分布や各市町村の結果分析など、まったく例年と違わず全国平均との差異を意識させつつ列挙されている。
また、今年度の「報告書」では、冒頭に「学力向上の取組に関する改善の方向性」として、①授業改善、②検証改善サイクルの確立、③小学校と中学校が連携した取組の充実、④望ましい学習習慣の確立、の4点を掲げ、詳細にわたって点数向上に特化した「改善の方向性」を示している。これらは、本来学校にある教育課程の編成権に不当介入し、子ども一人ひとりや各学校の実態を蔑ろにした画一的な「点数学力向上策」に一層拍車がかかるものである。
子どもたちは、「いじめ」「不登校」「自殺」が過去最多になるなど苦しみを表出させている。この苦しみの一端は、ゆたかな「学び」が保障されるべき学校において、「学力向上」の名の下に常に点数競争に煽られ、差別・選別されるとともに、多様性や自分らしさが認められないことにある。教職員もまた、超勤・多忙化に歯止めがかからず、子どもに寄り添う時間が生み出せずにいるとともに、管理強化・点数主義によって自主的・創造的な授業づくりが阻害され、子どもたちに学ぶ楽しさを伝えられず苦悩を重ねている。
今、道教委がすべきことは、地域や子どもの実態に即し、ゆたかな教育を保障するため、押しつけの「学力向上策」を直ちに止め、①子どもの多様性を生かした「学び合い」を可能とする少人数学級を実現すること、②教育課程の弾力化や学校の裁量権を保障すること、③教職員定数を改善し教職員がゆとりを持って子どもと接することができるようにすること、など教職員の超勤・多忙化解消と教育条件の整備・拡充をすすめることである。
以上のことから、北教組は、「学力調査・結果公表」に断固反対し、子どもたちの「学び」を矮小化する「点数学力」偏重の「教育施策」の撤回を強く求める。
私たちは今後も、憲法・「47教育基本法」・「子どもの権利条約」の理念にもとづく「ゆたかな教育」の実現のため、一人ひとりの子どもに寄り添う教育実践を積み重ね、市民とともに教育を子どもたちのもとへとりもどすための広範な道民運動をすすめていくことを表明する。
2019年11月7日
北海道教職員組合
第69次合同教育研究全道集会
アピール
2019年11月3日
北教組・道私教協は、夕張市において11月1日から11月3日までの3日間、全道各地よりのべ3500人の組合員・保護者・地域住民の参加のもと、第69次合同教育研究全道集会を開催しました。
安倍政権は、「戦争する国づくり」に向け、9条に自衛隊を明記する改憲を目論んでいます。また、それを下支えする「国家のための人材づくり」に向け、子どもたちの貧困と「教育格差」が固定化・拡大する中で、改訂「学習指導要領」にもとづき、政財界が求める「資質・能力」の育成と「道徳の教科化」による「愛国心」「規範意識」の押しつけなど、競争と管理の教育をおしすすめています。
こうした中、2018年10月公表の文科省調査において、2017年度の「いじめ」「不登校」はいずれも過去最多となりました。また、政府の「自殺対策白書」(2019年7月)では、10代の自殺が過去最悪となり、その第一の要因が「学業不振」であることが明らかになりました。
こうした状況に対し、国連子どもの権利委員会は、1998年以降の総括所見の中で、「高度に競争的な学校環境がいじめ、校内暴力、精神障害、不登校、中途退学、自殺を助長している可能性があること」「ストレスの多い学校環境から子どもを解放するための措置を強化すること」など指摘し続けてきました。しかし、政府・文科省は、これらを一顧だにせず、依然として「学力テスト」とその公表などにより競争を煽る差別選別と管理強化の教育をすすめており、子どもたちの苦悩は、年々深刻さを増すばかりです。
教職員も「点数学力向上」が至上命題とされる中で、「学校スタンダード」などとして画一的に「学習規律」や授業展開を押しつけられ創意ある教育実践が阻害されるとともに、押しつけられる業務も増大し、「過労死レベル」の超勤が一層深刻化しています。こうした中、10月18日に「1年単位の変形労働時間制」導入を可能とする給特法「改正」案が閣議決定されました。「1年単位の変形労働時間制」について文科省は「働き方改革」の一環として「まとめどり」をするとしていますが、これは教員の超過勤務を解消するものではなく、むしろ超勤実態を追認し、固定化・常態化させかねないものであり、給特法「改正」法案の一方的な導入を断じて許してはなりません。
私たちは今次教研において、今まさに危機に直面している「平和を守り真実をつらぬく民主教育」の確立をめざし、全道各地の「抵抗と創造」の自主編成にもとづく教育実践について論議を深め、未来の主権者であるすべての子どもたちに民主教育を保障するため、次のことを確認しました。
第1に、憲法改悪を断固阻止するため、院内外の統一闘争を構築し、護憲勢力の結集と拡大をめざしてとりくむこと。そのために、組合員一人ひとりが自らの言葉で語る「教育を語る全道対話運動」を通して、「平和憲法を守る」「子どもの貧困・教育格差解消」「教職員の長時間労働是正」を重点課題に、地域住民・保護者との連携を強化すること。
第2に、競争による差別・選別教育をおしすすめる改悪「学習指導要領」やこれにもとづく「学力向上策」「特別の教科 道徳」と対決し、教育内容・方法・評価への不当な介入を許さず、個人の尊厳を尊び平和を希求する主権者を育むため、人権教育・「主権者への学習」、憲法学習などをすすめ、子どもの多様な「学び」を保障する自主編成運動を強化すること。
第3に、過酷な勤務実態を解消し、子どもと向き合う時間の確保とゆとりある教育活動をすすめるため、「1年単位の変形労働時間制」の導入を可能とするなどの給特法「改正」案の一方的な導入を許さず、教職員定数増・欠員解消、持ち授業時数減、部活動の社会教育への移行とともに、「給特法・条例」の廃止・抜本的見直しを求めること。また、道教委に対して「北海道アクション・プラン」の見直しを求めるとともに、やむを得ず行った超勤に対しては、勤務時間の割振り変更により直近に実質的な回復を措置させること。さらに「通報制度」「実地調査」など主体的・創造的な教育活動を阻み、教育の自由を侵害する不当な圧力をはね返し、民主教育の確立に向けて組織の総力をあげてたたかうこと。
第4に、憲法・「47教育基本法」・「子どもの権利条約」にもとづく、子どもを主人公とした自主・自立の学校づくりをすすめること。また、「子どもの権利条例」の早期制定に向け、保護者・地域住民と連携し、連合・平和運動フォーラム・民主教育をすすめる道民連合など民主的諸団体との共闘を強め、「日の丸・君が代」強制に反対する運動などにねばり強くとりくむこと。
第5に、文科省「特別支援教育」を実態化させず、「分けることは差別である」ことを確認するとともに、共生・共学をすすめること。また、共生社会の実現に向け、国連「障害者の権利条約」や「障害者差別解消法」の理念にもとづき、しょうがい者の社会的障壁を除去する「合理的配慮」をすすめること。
第6に、評価結果を賃金・任用・分限等へと反映させ、学校現場の協力・協働を阻害する「学校職員人事評価制度」については、撤廃を基本に、差別賃金・管理統制強化とさせず、すべての教職員の賃金改善とするよう、各級段階におけるとりくみを強化すること。
第7に、「主任制度」「主幹教諭制度」や「事務主幹制度」「新たなミッション加配」、中教審「特別部会」の「答申」にもとづく教職員の差別・分断、管理強化に反対し、自律的・民主的職場づくりと、主任手当の社会的還元を含め、組織強化・拡大を組織の総力をあげてすすめること。また、「協定書」破棄の実態化を許さず、諸権利定着・拡大、超勤・多忙化解消をはかること。さらに、「教員免許更新制」の早期撤廃に向けてとりくむこと。
第8に、財政論に依拠した道教委「これからの高校づくりに関する指針」の撤回・再考を求め、希望するすべての子どもたちが地元の学校へ通うことができるよう高校を存続させるとともに、「地域合同総合高校」の実現など、受験競争の解消とゆたかな高校教育改革をめざすこと。そのため、保護者・地域住民との連携を強化すること。また、公私間の学費格差解消に向け、私学助成拡充を求めること。
第9に、教育の機会均等を保障するため、「高校授業料無償化」への所得制限および朝鮮学校の無償化適用除外の撤廃、義務教育費国庫負担制度堅持・全額国庫負担を基本に、当面、負担率2分の1復元に向けて全国的な運動を展開すること。また、経済格差による「教育格差」の是正や「子どもの貧困」を解消するとともに「30人以下学級」の早期実現をめざし、当面、「第8次教職員定数改善計画」の策定や「道独自の少人数学級」の実施拡大、給付型奨学金制度の拡充、「就学援助」の拡大、教育費の保護者負担の解消など、教育予算増額に向けたとりくみを強化すること。
第10に、「生涯健康管理体制」の押しつけに反対し、集団フッ素洗口中止、食物アレルギーに特化した対応の一方的な導入阻止、HPV・日本脳炎などワクチンの定期接種化の中止などを求め、子どものいのちと健康を守るとりくみをすすめること。また、特定の健康観の押しつけや差別につながる「全国体力・運動能力調査」の中止・撤回を求めること。さらに、個人情報保護の問題が危惧され、一層多忙化を助長させる道教委「校務支援システム」の早期撤廃、一方的な導入阻止に向けてとりくむこと。
第11に、「女性差別撤廃条約」の理念にもとづき、女性参画を推進し、学校や社会における性差別や性別役割分業の撤廃に向け、とりくみを強化すること。ジェンダー平等に対する攻撃を排し、学校教育のあらゆる場面で「ジェンダーの視点」を取り入れた実践をすすめること。また、LGBTなど性の多様性にかかわる人権教育を一層すすめ、インクルーシブな社会を実現すること。
第12に、未だに収束を見ない「フクシマ」の現状から、「人類と核は共存できない」ことを再確認し、反核・反原発の学習をすすめるとともに、泊・幌延・大間をはじめとしたすべての原子力施設の廃止・建設中止を求め、「核・原発のない社会の実現」に向けてとりくみを強化すること。また、「被ばく」により、いのちを脅かされている子どもたちの状況の改善を求めるとともに、再生可能エネルギーへの政策転換を求め、自然との共存をめざす教育をすすめること。さらに、辺野古新基地・南西諸島への自衛隊配備阻止のたたかいを沖縄と連帯してすすめること。
世界の恒久平和を誓った憲法とその理念の実現をめざす民主教育は、今、戦後最大の危機に直面しています。私たちは、平和・人権・国民主権など憲法の原則を守り、個人より国家を優先する政府と文科省の政策を厳しく批判・分析し、「自分らしく」「よりよく生きる」教育の創造をめざして、地域・保護者と連帯して、自主編成運動をさらに押しすすめるとともに次世代へ継承することの重要性を再認識しました。
「教え子を再び戦場へ送るな!」の決意を新たにし、憲法改悪に断固反対するとともに「47教育基本法」・「子どもの権利条約」の理念にもとづく「平和を守り真実をつらぬく民主教育の確立」に向けたとりくみを一層前進させていくことを確認し、集会アピールとします。
2019年11月3日
第69次合同教育研究全道集会
第69次合同教育研究全道集会
中央執行委員長あいさつ
2019年11月1日
第69次合同教育研究全道集会に参加された組合員・保護者・共同研究者の皆さん大変ご苦労様です。また、集会の成功に向け準備万端を整えていただきました空知支部の組合員をはじめ地元夕張市の教育関係者の皆様に心より感謝申し上げます。
夕張での開催は2008年以来11年振りとなります。政府の失政によって招いた財政破綻から12年、市民生活の再建と子どもたちの教育環境づくりにとりくんでこられた皆さんに敬意を表します。今次教研をまたこの地で開催できることは、全道の組合員の熱い連帯の意志の表明です。厳しい現実に直面しながらも、これに屈することなく、未来を担う希望に満ちた子どもたちを育むための集会となることを願います。
さて、今年7月に公表された政府の「自殺対策白書」は、「10代の自殺が前年より増え過去最悪」となったことを明らかにしました。特定できた原因・動機で最も多いのは「学校問題」で、その内訳は多い順に、学業不振、進路の悩み、学友との不和、入試の悩み、いじめとなっています。「学業不振」が第一の要因というのは、政府・文科省が点数を唯一のものさしに学校や自治体を競わせ、子どもたちを追い詰めてきたことの表れです。
一方、9月に公表されたOECD調査では、日本の教育予算は対GDP(国民総生産)比2.9%とはじめて3%を切りました。加盟35か国中で3年連続最下位となり、改めて、教育支出の多くを家計が負担している現状が明らかになりました。
受験競争に勝ち抜いた子どもの家庭は所得が高いことが明らかになっており、経済格差が一層「教育格差」となって影響しています。こうした中で、2020年に始まる大学入学共通テストに導入される英語民間試験に関して、「身の丈に合わせて」とする文科大臣の発言は、「格差」を容認し、生まれた地域や経済力の差に目をつむり、憲法に保障された子どもたちの教育を受ける権利や機会均等を奪うもので、断じて許されません。
今、教員の欠員が生じ、採用試験の倍率が低下するなど、深刻な「教職離れ」がすすんでいます。教員不足で蔓延する免許外教科の指導や多忙化による教材研究、研修時間の不足は、「子どもの学習権」の侵害と言えます。
子どもたちや教職員を追い詰め苦悩させている競争と管理の政策を転換し、抜本的な勤務条件と教育条件の改革が、子どもたちの「真の学力向上」につながることは明らかです。
政府・文科省は、今臨時国会において、「給特法」をそのままに、月45時間を上限として規制する「ガイドライン」の指針化と「1年単位の変形労働時間制」導入を可能とする法「改正」を上程しました。国通りの制度「改正」はむしろ超勤を追認し、固定化・常態化させるものです。
原則超勤は命じない・命じる場合を限定させ、やむを得ず行った超勤については、直近での完全回復を基本に長期休業中における実質的回復を確実に措置させることが必要です。あわせて、業務の削減と一人の教員の持ち授業時数削減に向けた定数改善、「給特法」の廃止・抜本的見直しなどの改善を実現するため、日政連・北政連議員をはじめ、地域・保護者の皆さんと固く連帯し、院内外の運動を引き続き強化してまいります。
今年の8月、日教組が1953年に制作した映画「ひろしま」がNHKのEテレで放映されました。この映画は、被爆した市民8万8千人が撮影に参加し平和への強い願いのもと制作されたもので、国際的評価も受けましたが、大手映画会社が「反米的」と配給を棚上げし、推薦を見送る県教委もでるなど上映に厳しい壁が立ちはだかりました。しかし、当時の総評や労組、市民団体の協力を得て上映に漕ぎつけ、北教組は1953年から翌年にかけて、上映運動を積極的にすすめ、各地で大きな反響があったと北教組史に記されています。今、この映画の価値が見直され、世界中で上映されてきています。
原爆の悲惨さや反戦・平和のメッセージだけでなく、被爆者や戦災孤児への差別や偏見、貧困と格差、人間の尊厳や生存権など、現在の社会につながる根源的な問題を問いかけています。戦前・戦中の記憶が風化されようとする中で、戦争とは何か、改めて、学ぶためにふさわしい映画と言えます。
今、安倍政権のもと、憲法9条を死文化して「戦争する国」づくりに邁進する動きとともに、「国家のための人材づくり」の教育がすすめられようとしています。
こうした中で迎える今次教研は、「平和と教育」を自らと国民の手で守り創ることを原点に、69次にわたって積み重ねてきた、自主教研運動の真価が問われる大事な集会といえます。
教研集会に参加した皆さん。すべての分科会で、持ち寄った実践をもとに交流してください。
今、私たちが置かれている社会・経済状況と政府・文科省の政策がめざすものを厳しく分析・批判し、子どもの現実や地域・社会と教育のかかわりなどについて議論を深めてください。平和で民主的な社会を希求する主権者を育むため、抵抗と創造の自主編成運動を強化し、地域・保護者と連帯して具体的運動をすすめる方向性を確認していただきたいと思います。
本集会が、「教え子を再び戦場に送るな!」の固い誓いのもと、子どもたち誰もが夢や希望を持ち、意欲をもって学ぶことができるよう、「平和と真実を貫く民主教育の確立」に向けて、さらなる前進をはかる場となることを願い挨拶とします。ともに頑張りましょう。
2019年11月1日
北海道教職員組合 中央執行委員長
文科省「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部を改正する法律案」に
対する北教組見解
2019年10月23日
文科省は、第200回臨時国会に上程する「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部を改正する法律案」(以下、「給特法改正案」)を公表した。その内容は、「働き方改革」を推進するためとして、①現行第5条の「地公法」の読み替え規定を整備し、自治体の判断で条例により教育職員に対して1年単位の変形労働時間制を導入できるようにする(2021年4月1日施行)、②7条を新設し、「勤務時間の上限に関するガイドライン」を「業務量の適切な管理等に関する指針」(以下「上限ガイドライン(指針)」)に格上げし文科大臣が策定及び公表する(2020年4月1日施行)、とするものである。
文科省は、「上限ガイドライン(指針)」の遵守に向け、現状小学校で月約59時間、年約800時間の所定勤務時間外の「在校等時間」を月45時間、年360時間以内にする業務の削減を行った上で、学校行事等で業務量の多い時期(計13週を想定)の所定の勤務時間を週当たり3時間増加させ、その分の39時間(約5日分)を長期休業期間中(8月)に休日の「まとめ取り」として実施することをイメージしている。また、文科省は、2022年を目途に勤務実態調査を実施し「給特法等の法制的な枠組みを含め、必要に応じて検討を実施する」とした。
これらは何れも教員の超過勤務を解消するものではなく、むしろ超勤実態を追認し、超勤を固定化・常態化させかねないものである。また、何ら「上限ガイドライン(指針)」の遵守に向けた具体的な業務削減も示されていないことから、小学校の月約59時間の超勤を月45時間時間以内にすることすら困難であり、部活動などにより月約81時間の超勤がある中学校においては机上の空論と言わざるを得ない。さらには、文科省が「閑散期」と考えている長期休業期間中についても、教員は部活動や官制研修、会議・打ち合わせなど様々な業務に忙殺されている現実にある。その上、労基法上、「1年単位の変形労働時間制」導入にあたっては、労働組合との「協定」を必要としているにもかかわらず、文科省は「勤務条件条例主義」を口実に労基法上の労使交渉・協定を蔑ろにする姿勢を示している。加えて、北海道においては、これまで労使交渉を経て、修学旅行など深夜・早朝に及ぶ超勤に対しては、「4週の期間における勤務時間の割振り変更(1ヶ月単位の変形労働時間)」により、週休日における勤務に対しては「週休日の振替・特例」により、可能な限り直近に1日単位の実質的な回復を措置させてきた経過があり、1年単位の変形労働時間制導入によりこれらの制度の改悪となることが懸念される。何より「本来業務」自体が過多となり、正規の勤務時間内に終えることができずに超勤が常態化している実態を改善しなければならない。
以上のことから北教組は、正規の勤務時間内ですべての業務を終えることができるよう大幅な業務削減を求め超勤の常態化に歯止めをかけるよう全力でとりくむ。そのため、引き続き「長時間労働是正キャンペーン」により世論喚起をすすめ、教職員定数増、教員一人あたりの持ち授業時数の削減、部活動の社会教育への移行など抜本的な超勤解消策を求めていく。
「1年間の変形労働時間制」に対しては、少なくとも長期休業期間中の業務の大幅削減により「繁閑の差」をつくり、やむを得ず行った超勤に対しては、直近の回復を基本に長期休業期間においても実質的な回復を行うことで、教職員が確実に休むことができる制度とするようとりくむとともに、長期休業期間中の校外研修の措置を求めとりくむ。「指針」に対しては、文科省が所定の勤務時間外の「在校等時間」を労基法上の労働時間ではないとしていることに対し、明示の命令の有無にかかわらず、やむを得ず行った超勤については労基法上の労働時間とするよう「給特法」の廃止、若しくは第3条・第5条の抜本的な見直しを求めていく。また、「1年間の変形労働時間制」「上限ガイドライン(指針)」については、各級における労使交渉事項であることの周知・徹底を求めるとともに、超勤解消策については常に当局にその効果の検証と不断の改善を迫り、実効あるものとさせる必要がある。そのため、「給特法改正案」の問題点を追及し一方的な導入とさせないよう、日政連・北政連議員と連携し、日教組とともに院内外のとりくみを強化し、全力でとりくむ。
以 上
北海道教職員組合
道教委2020年度「公立高等学校配置計画」および「公立特別支援学校配置計画」に対する北教組声明
2019年9月3日
道教委は9月3日、2020年度から3年間の「公立高等学校配置計画」と20年度および21年度以降の見通しを示した「公立特別支援学校配置計画」を公表した。
「公立高校配置計画」は、20~21年度に39校で40学級減(昨年度決定)を行う上で、①21年度に伊達(3学級)と伊達緑丘(4学級)を再編統合し新設校(6学級)を設置する、②既に1学級減を決定している中標津と苫小牧工業(定時制)で学科転換を行う、③福島商業(地域連携特例校)の再編整備を留保する、など6月の「計画案」通り決定した。また、計画決定時に公表するとしていた入学選抜後に1学級相当以上の欠員が生じ学級減となった26校については、長沼など14校が1学級復活したものの、芦別、札幌南陵、札幌東豊、野幌、千歳北陽、八雲、檜山北、上川、名寄、浜頓別、弟子屈、羅臼の12校は1学級減のままとした。このことにより、羅臼は20年度から「地域連携特例校」の導入が決定し(中標津が協力校)、八雲は21年に計画されていた1学級減が1年前倒しとなった。
今回復活されなかった12校のうち学年1学級となる上川、浜頓別、弟子屈は、今後、存続に向けて一層努力を強いられることとなる。また、羅臼については、ここ数年「町内の中卒者数の状況等を総合的に勘案し」複数学級を確保してきたものの、1学級減と「地域連携特例校」の導入が決定したことによって、今後の学級増の可能性は極めて低くなった。
これらは、「1学年4~8学級」を適正規模とした「これからの高校づくりに関する指針」(以下、「指針」)にもとづき、中卒者数を口実に再編統合・学科転換などによって機械的な間口削減を強行するものであり、断じて容認できない。
道教委はこの間、子どもたちへの高校教育の保障を放棄し、生徒数を確保できないことをもって「教育機能の低下」として再編統合をすすめてきた。また、「地域連携特例校」の再編留保の要件である「所在市町村をはじめとした地域における、高校の教育機能の維持向上にむけた具体的取組とその効果」を地域・学校に求め、無用な競争を煽り続けてきた。また、学級数の決定を9月まで先延ばしすることは、子どもや保護者に不安を与え、混乱を生じさせるものである。
「公立特別支援学校配置計画」は、20年度について、6月の「配置計画案」で2学級減としていた東川養護と真駒内養護の普通科(重複)学級を1学級減へと修正し、全しょうがい児学校61校で、昨年度より定員が1人増の1,754人となった。また、知的障害特別支援高等部の配置の見通しでは、22年度に「道央圏で6学級相当の定数増」を検討するとしており、文科省・道教委「特別支援教育」の名のもとにすすめる差別・選別の施策は、中卒者数が減少傾向にもかかわらず特別支援学校への入学希望を年々増加させ、分離・別学を一層すすめるものとなっている。
道教委は、「分けることは差別につながる」とした「国連障害者権利条約」の理念にもとづき、希望する子どもたちの地元の普通高校への進学を保障するため、すべての学校において「合理的配慮」などの教育条件整備を早急にすすめることが、果たすべき最大の役割である。
本「配置計画」は、地域の経済と文化の衰退を招くとともに、遠距離通学者や保護者の経済的負担の増加など、「貧困と格差」を拡大させるもので断じて容認できない。私たちは引き続き、子ども・保護者・地域住民の高校存続を求める声を結集し、「指針」「配置計画」の撤回・再考を求めるとともに、希望するすべての子どもがしょうがいのある・なしにかかわらず地元で学べる「地域合同総合高校」の設置など、一人ひとりの子どもたちの要求に応えるゆたかな後期中等教育を保障するための道民運動を一層強化していくことを表明する。
2019年9月3日
北海道教職員組合
2019年度 文科省「全国学力・学習状況調査」の結果公表に対する
北教組声明
2019年8月2日
文科省は7月31日、19年度「
全国学力・学習状況調査」の結果を公表した。今年度の調査(小6・中3を対象とした悉皆調査)は、新たに中3で「英語」を加えるとともに、「知識と活用を一体的に問う」とし、これまでのA問題・B問題の構成を見直して実施した。文科省は、全国の状況について、「上位と下位の差はおおむね1問程度で、平均正答率プラスマイナス10%の範囲内」「前年同様、下位の底上げ傾向は続いている」などと分析した。
今年度は、問題構成を変更しこれまでと異なる調査であるにもかかわらず、過去の数値との比較に終始しており、分析は公平性・妥当性を欠くものである。また、調査は「知識偏重からの脱却」をめざすとして改訂「学習指導要領」の内容を前倒しする内容となっており、分析も改訂内容に合わせて国の求める「資質・能力」の育成に誘導し、本来あるべきゆたかな学びをめざすものとなっていない。
初めて実施した「英語」については、「話すこと」の調査において「録音環境の設置・確認など事前に膨大な作業を要した」「一度に調査できる人数が限られるため、生徒の入れ替えや試験監督に教職員を多数配置せざるを得なかった」など現場での多大な負担増が報告されるとともに、「隣席の声が漏れていた」「機材の不備によって録音されていなかった」など調査の信頼性を揺るがす事態が生じた。また、「英語」の結果は、外国人や英会話教室などが多い都市部が好成績となるなど、現場の努力だけでは解決できない問題が露呈しているにもかかわらず、分析はこうしたことに何ら踏み込むものとなっていない。
道教委も同日、例年同様に「正答数」や「正答率」「無回答率」などについて全国との数値比較に終始する「全国学力・学習状況調査の結果のポイントについて」を公表した。また、「全国との差が最大で小学校-2.1ポイント・中学校-1.8ポイントで、すべての教科で全国平均に届いていない」「全国との平均正答率の差はこれまでと同様であり、十分に改善されていない」と数値のみに拘泥し、何ら子どもの実態を表したものとなっておらず、現場の努力を顧みないコメントを行った。また、こうした問題ある分析の上に立って「継続的な検証改善サイクルの確立」「主体的に学習に取り組む態度を養う授業改善」「家庭や地域と連携した望ましい学習習慣・生活習慣の定着に向けた取組」などを「更に進める」とした。
今、学校現場では、道教委による管理強化のもと「家庭学習提出100%」「チャレンジテスト解答率100%」など子どもたちを追い込む方策が矢継ぎ早に強要されている。教職員も、調査直後の自校採点・報告・検証をはじめ、日々「宿題」「過去問題」などテスト対策に膨大な時間を割かれ、自主的な教材研究や授業準備が十分に行えずに苦しんでいる。
道教委の「点数至上主義」のこれまでの施策は、子どもの「学び」への思いや願いを置き去りにし、地域の実態を顧みない押しつけに過ぎず、むしろ子どもの学びを阻害している。また、教職員は長期休業中に強制的な集合研修が多数課せられており、その上に本結果をもとにした「夏休み中の結果分析と対策の構築」「休み明けからの改善方策の実施」を求めることは、道教委がすすめようとしている教職員の超勤・多忙化解消策にまったく逆行し、学校現場を一層追い詰めるものであり、断じて容認できない。
道教委は、「全国学力調査・結果公表」とそれにもとづく「点数学力向上策」の押しつけを即刻中止し、各学校の自主的・創造的な教育活動と一人ひとりの子どもによりそう実践を保障するとともに、「子どもの貧困」解消と「教育格差」是正をすすめ、定数改善や「給特法」の廃止・見直し等、超勤・多忙化解消のための法改正を文科省に求めるなど、本来なすべき勤務条件・教育条件整備に徹するべきである。
北教組は今後も、子どものゆたかな学びを阻害する「全国学力調査」に断固反対し、憲法・「47教育基本法」・「子どもの権利条約」の理念にもとづく「わかる授業・たのしい学校」「差別・選別の学校から共生・共学の学校」をめざして、「主権者教育」を基盤とした教育実践を積み重ねるとともに、教育を市民の手にとりもどすための広範な道民運動をすすめていくことを表明する。
2019年8月2日
北海道教職員組合
第130回 定期大会 委員長挨拶
2019年7月9日
北教組第130回定期大会にお集まりいただきました代議員、傍聴者の皆さん、おはようございます。
また、大変お忙しい中をご出席下さいました、ご来賓の皆様に心よりお礼申し上げます。
さて、北教組は、昨年6月の定期大会以降今日まで、憲法改悪阻止・戦争法撤廃、改訂「学習指導要領」の押しつけに対峙する自主編成と組織の強化・拡大、差別賃金・超勤排除など勤務条件改善、そして、統一地方選挙での北政連議員の完勝をめざして、組織の総力を挙げたたかって参りました。
これらの闘いの中で、現状の厳しさに直面しながらも、私たち北教組の運動の意義と組織の団結力を確認し、今後の闘いにつながる成果を勝ち取ることができました。
今次統一地方選挙は、北海道議会議員選挙において、3人の新人「江別市・木葉淳」「十勝・小泉まさし」「札幌市北区・山根まさひろ」と合わせて「函館市・平出陽子」「後志・市橋修治」「岩見沢市・中川ひろとし」の6人の北政連道議の当選を勝ち取ることができました。また、市町村議員選挙においても、「札幌市・竹内ゆみ」「旭川市・横山けいいち」「岩見沢市・日向きよかず」、新人3人を含む18人全員の当選を果たすことができました。全道の組合員・退職者の皆さんの奮闘に改めて感謝申し上げます。
しかし、16年ぶりの新人対決でありながら、石川知事を実現できず、道議会自民党の単独過半数を許し、小樽市・川澄候補の道議再選を逃したことはきわめて残念であり、組織として重く受け止めなければなりません。
今次の闘いの成果と課題について、本日の議案において総括を行っておりますので、充分に議論を頂き、参院選勝利に向けて、改めて北教組現退の組織固めをしっかりとすすめ、とりくみを強化していかなければなりません。
5月3日の憲法記念日、安倍首相は改憲派の集会にビデオメッセージを寄せ、「2020年の改正憲法施行に変わりはない」と述べ、「改元を機に、憲法改正に向けた議論を加速させるよう」呼びかけました。祝賀ムードを利用して改憲に向けた機運を煽ろうとする姑息な姿勢が露わです。また、この中で「9条への自衛隊明記」と「教育の無償化」を強調し、改憲を訴えています。
5月10日、消費税増税を財源に「幼児教育・保育、高等教育の無償化」と銘打って、改正「子ども・子育て支援法、大学修学支援法」が可決されました。
しかし、日政連神本参議院議員も本会議の反対討論で指摘しましたが、「待機児童解消や保育園の定員増を後回しにし、修学金の支援対象や要件もきわめて限定されている」ことなど、憲法26条が保障する「すべての子どもの学ぶ権利」や「教育の機会均等」を保障するものではありません。真の無償化とはかけ離れた偽看板で、改憲のための「呼び水」です。
そもそも憲法26条2項は、「義務教育はこれを無償とする」と定めていますが、現実は、教材費や給食費、修学旅行費など保護者に大きな負担を強いています。まずは、義務教育段階の膨大な保護者負担を無償化した上で、幼・保や大学教育の無償化を実現すべきであり、本末転倒です。
なお、「憲法26条」について、札幌弁護士会「憲法応援団」の一員として北教組弁護団・後藤徹弁護士がYouTubeで条文解説3分間メッセージを行っています。その中で、日本国憲法が「義務とされた教育を、等しくすべての子どもに権利として保障した意義」を、現在の「教育政策」への厳しい問題指摘とともに、解説しています。是非、観ていただきたいと思います。
今年1月に出された超勤・多忙化解消に向けた中教審「答申」は、私たちが求めてきた「給特法」廃止・見直しをはじめとした法整備や一人の教員の持ち授業時間数削減に向けた定数改善など抜本的な改革を先送りしました。業務の効率化と勤務時間管理に重点が置かれた「時間外勤務の上限を45時間」とする文科省「ガイドライン」と、労基法の趣旨をさらに逸脱させる「1年単位の変形労働時間」導入を可能とするもので、多忙化を一層加速させかねないものです。その根底には、改訂「学習指導要領」にもとづく差別・選別の「国のための教育」の徹底と財政論を最優先し、教育現場の実情を顧みない、日教組敵視の政権の姿勢があります。
私たちは、競争と管理の「政策」に対峙し、子どもたちのゆたかな教育を培うため民主的な職場づくりと自主編成を強化するとともに、一方的な国の制度変更を許さず、抜本的な勤務・教育条件の改善を要求し、引き続き全国的な運動を強化していかなければなりません。
今、子どもたちが犠牲となる事件が相次いでいます。子どもたちのいのちが失われた事実は重く、いのちと安全を守り、一人ひとりの子どもに寄り添う環境整備を社会全体ですすめることが急務です。
一方で、川崎市の殺傷事件の後、「死にたいなら一人で死ね」いう非難に対し、「控えてほしい」「社会はあなたを大事にしているし、何かができるかもしれない。社会はあなたの命を軽視していないし、死んでほしいと思っている人間などいない」というメッセージこそ必要だと警鐘を鳴らした、生活困窮者の支援を行うNPO代表の発信が注目を集めました。事件を繰り返さないためには、社会から阻害された人々を突き放すのではなく、むしろ、彼らの尊厳を大切に思っていると社会がメッセージを出すことの重要性を指摘しています。
今、自由競争と自己責任にもとづく政府の「政策」によって、財界や強いもののための社会がつくられ、「頑張っても報われない」深刻な「貧困と格差」がさらに広がっています。「アンダークラス」と言われる「非正規労働者」が928万人存在し、平均個人年収は186万円、就業者の14.9%を占めるなど、「格差社会」が一層拡大し「階級社会」となっている報告がされています。
憲法で保障されている働く権利や最低限の生存権が侵害され、将来に対する絶望感や閉塞感が蔓延し、社会とつながりが絶たれ、苦しむものが増え続けています。私たちは、現在の社会・経済・政治状況を厳しく問い直し、根強い自己責任論を排し、働くことの価値と尊厳が保障され、「誰一人取り残さない」共生と連帯、多様性と包摂性のある社会に変えていくとりくみをすすめなければなりません。
子どもたちも、格差社会の中で、将来の「希望」さえ家庭の経済状況に左右され、多くの子どもは学校を卒業しても働く場がないなど、努力しても報われない不安感を持ちながら学校生活を過ごしています。
こうした社会状況と子どもたちの要求と乖離した競争と管理の「教育政策」によって、子どもたちは孤立・分断化され、排他的な競争意識や自他への不信感を拡大させ、学習離れが一層すすみ、いじめ・暴力・不登校・引きこもり、自殺など様々な形で大人に苦悩を発信しています。
(毎日新聞朝刊の「余禄」で紹介されましたが)詩人の「吉野弘」さんは、「奈々子」という詩で、誕生した長女に、こう呼びかけます。
お父さんが
お前にあげたいものは
健康と
自分を愛する心だ。
ひとが
ひとでなくなるのは
自分を愛することをやめるときだ
自分を愛することをやめるとき
ひとは
他人を愛することをやめ
世界を見失ってしまう、・・・
お前にあげたいのは、香りのよい健康と
かちとるのにむずかしく
はぐくむのにむずかしい
自分を愛する心だ ・・・と。
人は自分を愛せなくなれば、他人や世界も意味を失い、道徳も倫理も底が抜けてしまいます。私たちは、現在の社会状況と密接に関係する子どもたちの現実をしっかりと受け止め、誰もが、自分を愛する心を育み、夢や希望を持って生きて行けるよう、将来の主権者たる子どもたちの教育とそのための社会づくりをすすめていかなければなりません。
2019・20年度の運動課題について述べます。
課題の第1は、改憲発議を断じて許さず、平和憲法を守り、民主主義を取り戻すため「対話」を基盤とした道民運動を強化すること、第2に、超勤・多忙化解消をめざし、「給特法」廃止・見直しや定数改善など抜本的な勤務・教育条件改善をすすめること、第3に、改訂「学習指導要領」に対峙し、人権や民主主義を根づかせる主権者を育む実践を強化すること、第4に、北教組の運動と組合参加の意義を伝え、連帯するとりくみを通して、若い教職員の加入拡大につなげることです。
最後に、当面の最大の課題は、参議院選挙の勝利です。
私たちは、安倍政権が「9条改憲」に突き進む中で、「教え子を再び戦場に送るな!」の決意を新たに、断じて戦争を許さず、平和・人権・民主主義が保障される社会と民主教育の確立をめざさなければなりません。
失った労働の尊厳を回復し格差社会を転換させ、「国民の側に立つ政治」と「等しく子どもたちに教育が保障される社会」を取り戻すため、北海道選挙区「勝部けんじ」、比例区「水岡俊一」両候補の完勝に向けて、現退一致で、組織の総力を挙げて闘うことを確認し合いたいと思います。
そして、衆参同日選挙は見送りとの報道ですが、私は10月消費増税と来年のオリンピック開催を考えれば、そう遠くない時期に解散総選挙があると思っております。北教組は、「解散総選挙を求める」との方針で、常に臨戦態勢です。その場合は、日政連・1区「道下大樹」、4区「本多平直」衆議院議員をはじめ、連合推薦候補者全員の圧倒的勝利をめざし、闘おうではありませんか。
本定期大会が、皆さんの真摯な討議によってたたかう北教組の方針が確定す ることを心よりご期待申し上げ、中央執行部を代表しての挨拶とします。とも に頑張りましょう。
2019年7月9日
北海道教職員組合
道教委2020年度「公立高等学校配置計画案」および「公立特別支援学校配置計画案」の撤回・再考を求める北教組声明
2019年6月5日
道教委は6月4日、2020年度から3年間の「公立高等学校配置計画案」および2020年度「公立特別支援学校配置計画案」を公表した。
「公立高校配置計画案」は、昨年度決定した20~21年度の計画によって39校で40学級減を行う上で、①21年度に伊達(3学級)と伊達緑丘(4学級)を再編統合し新設校(6学級)を設置する、②羅臼は20年度の募集学級数が1学級の場合に地域連携特例校とする、③既に1学級減を決定している中標津と苫小牧工業(定時制)で学科転換を行う、④福島商業(地域連携特例校)の再編整備を留保する、などと変更した。今年度の2次募集後に1学級相当の欠員が生じ学級減となった長沼など26校の20年度の学級数は、9月の計画決定時に公表するとした。また、新たに公表した22年度については、①20年度に学級減としている札幌月寒・北陵・手稲・丘珠の4校および恵庭北を各1学級増とする、②釧路北陽(市立)の「フィールド制」を見直し普通科「単位制」とする、とした。
これらは、今後3年間で、「これからの高校づくりに関する指針」にもとづき「1学年4~8学級」を適正規模として、中卒者数を口実にした機械的な間口削減や調整と、再編統合・学科転換などによる学級減を強行するもので断じて容認できない。
伊達と伊達緑丘の再編統合は自治体の検討結果を勘案したものとされているが、そもそも「指針」にもとづく統廃合に向けた圧力によってやむを得ず判断したものであり、今後、複数の高校を抱える自治体への波及が危惧される。また、福島商業について、「所在市町村をはじめとした地域における、高校の教育機能の維持向上にむけた具体的取組とその効果を勘案」し、再編整備を留保するとしたことは、高校教育を保障する責務を放棄し当該自治体に存続の努力を強要するとともに、入学を希望する子どもや保護者に不安を与え進路変更を余儀なくさせるもので、統廃合へ向けた勧告に過ぎない(昨年度も6校が留保)。
大幅に人口減少がすすむ道内において、こうした機械的な再編統合や間口削減を行う「公立高等学校配置計画」が、一層高校を減少させ地域の疲弊・衰退を加速させてきた。道教委は、今後開催される「第2回地域別検討協議会」において地域の声を真摯に受け止め、知事部局等と連携し高校存続に向けた体制を早急に構築するべきである。
「公立特別支援学校配置計画案」は、20年度については、全しょうがい児学校61校で5学級5人の定員減とした。これは、肢体不自由児および病弱児学校で15人の定員減の一方で、知的しょうがい児学校47校において10人の定員増としたことによるものである。また、「特別支援学校」が未配置となっている苫小牧市において、21年度に小・中学部の知的しょうがい児学校を新設するとしており、将来的には高等部の設置につながることが予想される。さらに22年度は、「道央圏で6学級相当の定員の確保を検討する」としており、分離・別学を一層すすめる姿勢を示している。
19年度の特別支援学校入学者数は、中卒者が年々減少傾向(18年44,989人、19年44,255人)にあるにもかかわらず、1,282人(18年1,268人)と14人増加した。このように、文科省・道教委のすすめる「特別支援教育」が「分けることは差別につながる」とする「国連障害者権利条約」の理念に反し、どの子も共に学ぶ「インクルーシブ教育」を阻害している実態は許されるものではない。道教委は、しょうがいのある子どもたちの地元の普通高校への入学および進級・卒業に向けた「合理的配慮」など、教育環境整備を早急に行うべきである。
北教組は、「これからの高校づくりに関する指針」や「配置計画案」が、受験競争の激化や高校の序列化を加速させるとともに、子ども・保護者や地域住民の高校存続を求める声を無視するものであることから、引き続き、道教委に対し撤回・再考を強く求める。また、ゆたかな高校教育の実現をめざし、どの地域に暮らしていてもしょうがいのある・なしにかかわらず希望するすべての子どもが地元で学べる「地域合同総合高校」の設置など、子どもの教育への権利と教育の機会均等の保障をめざし、「道民運動」を一層強化していく。
2019年6月5日
北海道教職員組合
第122回 中央委員会 挨拶
2019年4月15日
北教組第122回中央委員会にお集まりいただきました中央委員、傍聴者の皆さん、おはようございます。
また、大変お忙しい中をご出席下さいました、ご来賓のみなさまに心よりお礼申し上げます。
さて、学校における働き方改革を議論してきた「中教審」は1月、文科省に「答申」を提出しました。私たちの運動によって、学校現場の超勤問題を社会問題化させ、議論を巻き起こし、対策を出さざるを得ない状況をつくり出してきたことは大きな成果と言えます。
しかし、本「答申」は、私たちが求めた教職員の「定数改善」や「一人当たりの持ち授業時間数削減」など抜本的な改善に踏み込むことなく、「ただ働き」を助長してきた「給特法」の見直しも中長期的な検討事項として先送りしました。
一方で、文科省が策定した「時間外勤務の上限を45時間とするガイドライン」を設け、「1年単位の変形労働時間」導入を可能としました。これは、十分な予算もかけず、安上がりの対症療法的な対策で、自民党教育再生実行本部「第11次答申」そのままの政権の意図にもとづく、きわめて政治的なものです。
中教審「答申」は、「給特法」を維持することで、矛盾を拡大させ、労基法から一層逸脱させました。そもそも、「給特法」は「原則超勤を命じない」「命じる場合は臨時または緊急のやむを得ない必要があるときの4項目」に限ることを条件に、労基法36条・37条を適用除外しました。しかし、「ガイドライン」は、限定4項目以外の業務を「在校等時間」として「勤務時間」に新たに加える一方で、時間外勤務等手当は支払わず、「月45時間」まで「ただ働き」を認める二重基準です。これまで「自主的・自発的な勤務」としてきた業務を超勤として認めたものの、支払うべき超勤手当等は頬被りし、4%調整額に包含しているとする立場で容認できません。
「1年単位の変形労働時間」は、既に民間で明らかになっているように、常態化する長時間労働を容認し、見かけ上、時間外勤務をなくし合法化させる制度で、国通りの制度では超勤に拍車をかけかねません。中教審は、2019年中に「制度改正」を行い、20年中に「自治体の判断にもとづき条例改正等」を図り、「具体的な変形労働の在り方を確定」して、21年度の実施をめざすとしています。
北教組はこれまで、道教委との交渉を強化し、「原則超勤を命じない」ことを遵守させる中で、やむを得ず行った時間外勤務を「勤務の割り振り変更」によって回復する限定的な変形労働時間によって、実質的な回復を図ってきました。1月の予算交渉においても、「子どもたちに関わるすべての引率」と「入学式・卒業式と事前準備」を対象業務に新たに加えさせ、制度の積極的な活用を徹底させることを確認しました。
私たちは、中教審「答申」や文科省「ガイドライン」の問題を確りと明らかにし、教職員の「定数改善」と「一人当たりの持ち授業時間数の削減」、「給特法」の廃止・見直しなど、抜本的な勤務・教育条件の改善を要求し、引き続き院内外の運動を強化していかなければなりません。あわせて、一方的な国の制度変更を許さず、当面、「原則超勤を命じない」「命じる場合は限定4項目」遵守を基本に、やむを得ず行った超勤は完全に回復させるよう、交渉にもとづく改善策を要求し、超勤解消に向けて全力でとりくんでまいります。
さて、総務省が2月に「統計の日(10月18日)」に向けて、「標語」を募集しました。「不景気も 統計一つで 好景気」「この数字 君が良いねと言ったから 偽装であっても統計記念日」。ネット上には、杓子定規に募集を行う役所仕事と統計のいい加減さを皮肉る「標語」が溢れ「大喜利」状態となっています。統計不正と賃金偽装問題によって政府の政策の正当性が失われ、森友・加計学園同様、官邸の関与が疑われています。
こうした中で、安倍首相は、「9条に自衛隊を明記する改憲」の理由として、「6割以上の自治体が自衛官募集に協力しない」との発言を行いました。これは、そもそも「自治体が住民情報を自衛隊に渡す」ことから、地方自治や個人情報保護に反することはもとより、改憲の意図が「戦争する国」に向け、「国民を戦場に駆り立てる体制づくり」にあることを露にするものです。
北教組は1月、平和憲法を守る運動を強化するため、「護憲運動推進本部」を設置しました。憲法が戦後最大の危機を迎えている今こそ「教え子を再び戦場に送るな!」のスローガンのもと、憲法理念を実現し生かすとりくみをすすめるためです。憲法・「改憲手続法」「自民党改憲案」の学習とともに、保護者・地域住民との対話をすすめ、改憲阻止に向けた広範な運動を強化していかなければなりません。
先月、私は岩手県高教組の70周年行事に参加しました。その中で、かつて花巻農業高校の教員であった「宮沢賢治」が、農民の方々と働きながらともに学ぶためにつくった「教科書」の冒頭に書いた言葉が語られました。「世界がぜんたい幸福にならないうちは 個人の幸福はあり得ない」というものです。
今、世界中で、差別と分断、排他的な風潮が強まり、平和や人権、民主主義という最も大切な普遍的な価値観が蔑ろにされ、自分だけが良ければという考えが大手を振る中で、「世界中の人々の幸せを願い、平和を求める大切さ」を賢治は時代を超えて、私たちに伝えていると強く感じました。また、スピーチの中で先輩の方が、「もし、賢治が今も教員だったら、間違いなく組合員だ」と話したことも印象に残りました。
私たちは安倍政権が、「9条改憲」に突き進む中で、憲法に保障された「平和」の意味を問い直し、断じて戦争を許さず、平和憲法を守る1年にしなければなりません。そのため、今年の知事選をはじめとする統一地方選挙、そして7月の参議院選挙は、まさに天王山です。
7月の参議院議員選挙では、北海道選挙区「勝部けんじ」、比例区「水岡俊一」候補予定者を勝利させるため、北海道教育フォーラムと連携し、現退一致で組織の総力を挙げて闘うことを確認したいと思います。
この中央委員会が、皆さんの真摯な討議によって、たたかう北教組の当面方針が確定することを心よりご期待申し上げ、中央執行部を代表しての挨拶とします。ともに頑張りましょう。
2019年4月15日
北海道教職員組合
中教審答申「新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のための学校における働き方改革に関する総合的な方策」および「公立学校の教師の勤務時間の
上限に関するガイドライン」に
反対する声明
2019年1月28日
1月25日、中教審は文科大臣に対し、「新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のための学校における働き方改革に関する総合的な方策」(以下、「答申」)を答申した。
「答申」は、改訂「学習指導要領」の円滑な実施を最優先に、①学校及び教師が担う業務の明確化、②勤務時間を客観的に把握し集計するシステムの構築、③「1年単位の変形労働時間制」の導入、④「主幹教諭」の配置をはじめとした学校運営体制の見直し、⑤労働安全衛生管理体制の整備、などにとどまっており、教職員定数増や教員一人当たりの持ち授業時数の削減、時間外勤務手当化など問題の本質を改善する方策は示していない。
また、文科省が策定した「時間外勤務時間の上限を45時間」とする「公立学校の教師の勤務時間の上限に関するガイドライン(以下、「ガイドライン」)は、何ら法的強制力のないものにとどまっている。これらは、何れも現状の抜本的な改善にはなり得ず、教職員の労働者としての権利を蔑ろにするもので許されない。
とりわけ、「1年単位の変形労働時間制」導入は、現状の超勤実態を追認し恒常化させることで、むしろ現行の「給特法」以上に超勤を黙認して時間外勤務手当等不支給の違法を助長するシステムとなりかねないものである。また「ガイドライン」は、「部活動を含む週休日の在校時間等を勤務時間に加える」としたものの、「1日の勤務時間は7時間45分」とした「勤務時間条例」や「原則として時間外勤務は命じない」とした「給特条例」の規定を形骸化し、月45時間まで超勤を許容する二重基準となることが懸念されるものである。
加えて、「学校及び教師が担う業務の明確化」は、本来担うべき業務を明確化した上でそれ以外の業務の主体を学校・教職員以外に移行していくとしているが、教職員以外の部活動指導員やスクールサポートスタッフなど配置数は極少数であり、きわめて不十分と言わざるを得ない。また、専門スタッフの人員確保について何ら担保されておらず、地方・郡部においては確保が困難な状況が生じることは明らかである。これら専門スタッフの導入は、賃金や処遇も不十分なもので、予算もかけない安上がりな施策であり、学校のあり方を変質させかねないものである。
超勤・多忙化の要因は、教員の担当授業時数が多く、授業が正規の勤務時間の大半を占めて、正規の勤務時間内で授業以外の必要な仕事を処理することは困難であることにある。しかも教職員が超勤をして行っている業務は、子どもたちの学習権を保障するために何れも直ちに処理しなければならない差し迫った業務であり、その業務を行わないで済ますことはできないものばかりである。現状、教職員は過労死と隣り合わせと言っても過言ではない。2018年度「過労死等防止対策白書」においても、教員の平均勤務時間が11時間を超えるなど、「過労死ライン」を超えている異常な状態がはっきりしている。
「答申」は、こうした現実を直視せず教職員の「働き方」に「効率と成果」を求め、「学習指導要領」改訂に伴う授業時数増に対して必要な教職員定数改善を行ってこなかったことなど根本的な問題を棚上げして、教職員の超勤の意識・自己責任の問題に矮小化している。そのため、超勤を助長する元凶となっている「給特法・条例」の時間外勤務手当・休日手当・割増賃金の不支給も一切見直さず、文科省が第一に行うべき必要な法改正と定数改善に向けた予算措置など、問題の核心には手をつけずに放置するもので、断じて容認できない。
さらには、今回の「答申」は、子どもたちにゆたかな教育を保障するための見地や、それを支える協力・協働による民主的職場の確立の観点からも、きわめて問題の多いものである。その顕著な例が、「人事評価で、同じ成果であればより短い在校等時間の教師に高い評価をつける」など、個人の業務処理能力や効率化など自己責任論に矮小化させ、教育が人格の完成に向け子どもたちと教職員のふれあいの中で行われることや子ども・地域の実態から教材や授業構想が行われるべきことなど、教育の本質を蔑ろにするものである。また、「学校運営体制の見直し」については、「チーム学校」としての機能を強化するとともに、「主幹教諭」を全校配置しミドルリーダーがリーダーシップを発揮できるようにするとしているが、「校長」を中心とした上意下達の「学校運営体制」を強化し、管理統制を図ろうとするものに他ならない。これらは、教育の地方自治を否定し、画一化・中央集権化を目論むなど、47教育基本法の理念を根本から覆すもので断じて容認できない。
これまで北教組は、子どもたち一人ひとりに寄り添うゆたかな教育を行うためには、教職員が生活時間を確保し、心身ともにゆとりを持って教育に専念できる環境整備が必要であることを訴えてきた。そのために、「一人当たりの持ち授業時間数の削減」や「『給特法』の廃止、または3条2項・5条の見直し」など抜本的な超勤・解消策を求め運動を行ってきた。
北教組は、文科省・道教委に対して授業時数増やゆとりのない教育課程、過密な日課など、子どもたちからゆとりを奪い学校現場に超勤・多忙化を強いる学習指導要領体制、「点数学力向上策」の押しつけなどの教育政策の転換を求めるとともに、「持ち授業時間数削減」に向けた教職員定数改善や現場実態と大きく乖離している「給特法・条例」の廃止・見直しなど実効ある超勤解消策を求め、引き続き院内外のとりくみを強化し、全力でとりくんでいく。
2019年1月28日
北海道教職員組合