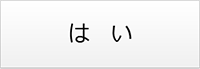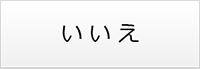2023年度 道教委「全国学力・学習状況調査 北海道版結果報告書」に対する北教組声明
2023年11月9日
2023年度 道教委「全国学力・学習状況調査 北海道版結果報告書」に対する北教組声明
道教委は11月7日、2023年度「全国学力・学習状況調査北海道版結果報告書」を公表した。その中で、「平均正答率が全国平均に達していないものの、その差が小学校の算数及び中学校の数学と英語の3教科で縮まり、07年度の調査開始以来初めて、全ての教科で2.0ポイント以内となるなど改善の傾向が見られる」とした。また、「目的や条件に応じて、理由や根拠を示したり、筋道を立てて考え説明したりすること」「授業以外で勉強する時間が短い」など例年同様の課題をあげた。その上で、①調査を客観的な指標とし、エビデンスに基づいて検証改善サイクルの充実を図る、②ICT端末も積極的に活用しながら授業改善を進める、③小中連携の推進、④児童生徒がICT端末を日常的に活用し、計画的に勉強する習慣を身につけさせるなど、昨年と大きく変わらない理念なき4つの改善の方向性を示した。
4つの改善の方向性は、①教員各々が日常的に行っている教育評価活動よりも調査にもとづく形式的なPDCAサイクルが優先され多忙化に拍車をかけている、②授業改善や小中連携と称して子どもの実態を無視した画一的な授業展開を押しつけられる、③ICTの活用を強制されるなど、いずれも教育内容・方法の管理統制と一層の超勤・多忙化を招くばかりか、教職員から自主性・創造性を奪い意欲を削ぐものとなっている。
また、道教委が毎年各教科の管内平均正答率の分布を明示することで、チャレンジテストの強制に加え、管内独自のテストや研修等、各市町村・学校においてさらなる対策が求められることになり、事前対策の強化や学習規律重視など短絡的な対策が横行している。学校現場では、過労死レベルにある超勤・多忙化が解消されていない中、11月に結果公表が行われるにもかかわらず調査実施後に解答用紙をコピーし、直ちに自校で採点・分析後、授業改善が命じられるなど、教職員はまさに調査に翻弄されている。そもそも教職員は、超勤・多忙化で疲弊しきっており、十分に教材研究や授業準備を行う余裕がない。こうした状況に追い打ちをかけているのが、全国学力調査に他ならず、本末転倒と言わざるを得ない。教育全体の問題を見ても、子どもたちのいじめ・不登校の増加には歯止めがかからず、教職員のなり手不足も深刻化している。
道教委は学力調査における数ポイント差にこだわる「木を見て森を見ず」の教育施策ではなく、現場を信頼し教職員・子ども同士が対話を通してかかわり合う環境づくりのための人的・物的両面での環境整備に徹するべきである。また、国連子どもの権利委員会の日本に対する「あまりにも競争的な制度を含むストレスフルな学校環境から子どもを解放すること」とした勧告を真摯に受け止め、競争的・管理的な学校から子どもたちを解放すべきである。併せて、文科省・道教委に対して、07年の学力調査開始以降の教育政策・施策の検証改善を強く求める。
北教組は、教職員の自発性・創造性を尊重し、子どもたちが「わかるよろこび」を感じることができる学校をめざす観点から、「報告書」「結果公表」に断固抗議するとともに「全国学力・学習状況調査」に反対し、子どもたちの「学び」を矮小化する「点数学力」偏重の「教育施策」の撤回を強く求める。
私たちはこれまでと同様、今後も、憲法・「47教育基本法」・「子どもの権利条約」の理念にもとづく「ゆたかな教育」の実現のため、子どもの主体性・創造性を尊重し、意見表明権を保障した教育実践を積み重ね、市民とともに教育を子どもたちのもとへとりもどすための広範な道民運動をすすめていくことを表明する。
2023年11月9日
北海道教職員組合
【声明】道教委2024年度「公立高等学校配置計画」および「公立特別支援学校配置計画」に対する北教組声明
2023年9月6日
道教委2024年度「公立高等学校配置計画」および「公立特別支援学校配置計画」に対する北教組声明
道教委は9月5日、24年度から3年間の「公立高等学校配置計画」(以下、「配置計画」)と24年度および25年度以降の見通しを示した「公立特別支援学校配置計画」を公表した。
「配置計画」では、6月の「計画案」で示した通り、26年度に奈井江商業、25年度に穂別、24年度に留辺蘂を募集停止とした。また、24年度については、利尻の商業科1学級および釧路学区4校(釧路湖陵・釧路商業・釧路明輝・釧路東)の各1学級減、25年度については、①深川東、室蘭工業を1学級減、②岩見沢東と岩見沢西(現8学級)を再編し6学級の単位制新設校設置、③富良野と富良野緑峰(現7学級)を再編し5学級の単位制新設校設置、などとした。26年度は、函館水産の1学級減とニセコ定時制の総合学科転換とした。23年度入学者選抜の結果、第2次募集後の入学者に1学級相当以上の欠員が生じ学級減とした18校のうち、岩見沢東などの14校は1学級増へと戻したものの、北広島西、余市紅志、広尾、札幌白陵を1学級減のままとし、札幌白陵については単位制から学年制に転換した。
道教委「これからの高校づくりに関する指針 改定版」(23年3月。以下、「指針」)では、「望ましい学級規模は1学年4~8学級」との記載を削除したものの、「在籍者数が2年連続で20人未満」の再編整備基準は固持し、3年連続となった奈井江商業を募集停止とした。一方で、留辺蘂は、22年度20人、23年度に22人の入学者数がいたにもかかわらず、24年度の募集停止は変わっていない。以上のように道教委は、依然として「中卒者数や欠員の状況、地元からの進学率」などを口実に機械的な間口削減をすすめており、この20年間で60校の公立高校が廃校となった。
これらは、子どもたちの選択肢を狭め、遠距離通学を強いるなど学習権の侵害や負担増につながっており、断じて認められない。また、高校の廃校によって、若年層の家族を含めた都市部転出、職業学科の学級減や学科転科による高卒後の地元の就職者減など、地域経済・文化の活力をも奪っていると言わざるを得ない。さらには、道教委が募集停止や間口減を懸念する高校に対し、「特色ある高校づくり」を求めることで、当該学校の教職員の超勤・多忙化を助長し、子どもたちの実態にもとづく教育を歪めていることに対し、重大な懸念を表明する。
「公立特別支援学校配置計画」では、24年度について、定員を全しょうがい児学校60校で昨年度より2人増の1,708人とした。「計画案」からの変更点は、学級数が266から5学級増の271へと、定員が1,678人から30人増の1,708人へとなったことである。また、25年度には「道北圏で2学級相当」、26年度には「道央圏で7学級相当」の定員の確保を検討し、既設校で対応するとした。
依然として中学生の人口が減少しているにもかかわらず増加している要因は、「特別支援教育」により分離・別学をすすめていることにある。これは、「障害者差別解消法」等に反するとともに、「国連・障害者権利委員会勧告」(22年9月)の「すべての障害のある児童に対して通常の学校を利用する機会を確保すること」など、国際的なインクルーシブ教育の基準からはかけ離れたものとなっている。また、現状、特別支援学校において特別教室を普通教室に転用するなど施設の不足が課題となっていることから、道教委は教育環境整備を責任をもってすすめることはもとより、「合理的配慮」をすべての学校において十分に行うべきである。
広域な北海道においては、少子化に歯止めがかからない中にあって、少人数でも運営できる学校形態を確立し、地域に高校を存続させるモデルの構築が急務である。道教委は、「指針」で「一定の圏域内における各高校の役割等を勘案した高校配置の必要性を踏まえ、1学年1学級の高校においても圏域全体で必要な定員調整をあらかじめ行うことで存続を図ることも選択肢となる」とした方針を深化・発展させ、私たちが求めてきた「地域合同総合高校」を早期に具体化すべきである。
北教組は、「指針」「配置計画」の撤回・再考を求めるとともに、希望するすべての子どもがしょうがいのある・なしにかかわらず地元で学べる「地域合同総合高校」の設置など、子どもの教育への権利と教育の機会均等の保障を実現させるため、道民運動を一層強化していくことを表明する。
2023年9月6日
北海道教職員組合
第134回 定期大会 委員長あいさつ
2023年6月27日
北教組第134回定期大会の開催にあたって北教組本部を代表して、ご挨拶申し上げます。
まず、感染症の影響が残る中、学校現場おいて、子どもたちのために日々奮闘されている組合員・役員の皆さんの本大会への結集に心より感謝申し上げます。
さらには、全国連帯の日教組運動の先頭に立ってとりくみをけん引している日教組瀧本司中央執行委員長、そして、道民運動をはじめ多くの運動に連帯していただいている連合北海道杉山元会長のお二人に来賓としてご臨席いただいていることに組合員を代表して厚く御礼申し上げます。ありがとうございます。
さて、前回の定期大会は、感染症が収束していないことから、代議員数等の制限、時間短縮での開催となりましたが、本定期大会が、これらの制約がほぼない開催に漕ぎつけたことは、今後の北教組運動強化・発展の契機となりうるもので、現場実態にもとづく、闊達な議論をしていただくよう、冒頭、お願いを申し上げさせていただきます。
北教組は、この2年間、「超勤多忙化解消をはじめとする勤務条件改善」 、「自主編成運動による民主教育の確立」を運動の基軸として、あらゆるとりくみを組織強化・拡大に結合させることを目標に、「運動の焦点化・効率化」の考えのもと、とりくみをすすめ、本定期大会を迎えることとなりました。
私たち北教組運動の原則は、子どもたち・教職員・地域社会の現状を捉え、運動の歴史を振り返り、運動方針・理念にもとづき議論をして行動、そして総括をし、新たな方向性を導き出すというものです。その手順は、一つも欠かすことのできない重要なものでありますし、学校現場でのゆたかな教育をめざした実践と同じ過程を経るものではないでしょうか。
「教え子を再び戦場に送らない」のスローガンも痛恨の極みを経た振り返りであることは間違いありません。国民学校の教壇に立ち、戦争の悲惨な歴史を振り返った元組合員の熊谷克治さんは、北教組結成30周年に寄せた詩に、「教科書に黒々と墨を塗る震えた指先を見て、教え子を戦場に送るためにチョークを握っていた日々を思い出し、洗っても落ちない血まみれの指先でふたたびチョークを握る胸の苦しさ」と詠い、心からの叫びとして、「教え子を再び戦場に送らない」と誓っています。こうした、先輩諸氏の振り返りを北教組運動の原則とし、守れ抜く私たちの運動に貴重な意義、そして誇りを感じるものであります。
さて、今現在、これ以上の痛恨の極みとなるものは幸いながら、存在しないものの、子どもたちは過度に競争的なカリキュラムの中でストレス、負担が多い学校環境にいること。そして、教職員・組合員も、ほとんどの時間外勤務が自主的・自発的勤務とされる矛盾した給特法制下で、「学校の働き方改革」の成果・効果が見えておらず、生活時間が確保されず、病気休職者が増加し、教員不足が深刻化する状況はこれ以上放置できるはずはありません。自民党特命委員会の提言や中教審への文科省諮問事項は超勤を容認していることに、一人ひとりの組合員が危機感・怒りをもち、勤務時間内に業務が終わることをめざした運動の展開を全組合員で行うことが最大の課題となっています。未来、後輩教職員たちが、教職の魅力は不偏であるものの、生活のすべてを犠牲にしなければならない仕事と変わり果てたとき、子どもたちを一層苦しめることになってしまったと、振り返らないよう、今、私たちは全力でこの問題に立ち向かい、共感者を組合員・仲間にしていく絶好の機会に直面している状況にあります。
振り返れば、来た道はいつも嵐、といった先輩組合員がいます。しかし、確実に歩んで来た誇りをもてば、まだまだ団結してすすめるはずです。
今次、定期大会が、とりくみの中で仲間として一つになり、そして、行動することによって力をつける、展望のもてる北教組運動のスタートとなるよう、代議員・役員、本部執行部が議論を深め、成功することを祈念して、甚だ簡単でありますが、ご挨拶とさせていただきます。ともに頑張りましょう。
2023年6月27日
北海道教職員組合